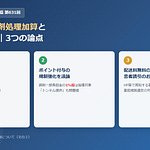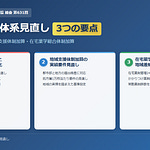令和7年度第13回入院・外来医療等の調査・評価分科会において、透析医療に関する検討結果がとりまとめられました。慢性維持透析患者数は約34万人で2022年から減少傾向にあり、透析患者全体の高齢化が進んでいます。この患者動向の変化に対応し、災害対策の強化、シャントトラブルへの連携促進、腹膜透析の推進、情報提供の充実、緩和ケアの実施といった医療提供体制の課題が明らかになりました。分科会では、患者のQOLを考慮した質の高い透析医療を推進する観点から、人工腎臓の評価方法を見直すべきという意見が示されています。
分科会での検討により、透析医療における5つの重要課題が浮き彫りになりました。第一に、透析患者数は減少傾向にありながら新規導入患者の平均年齢は71.6歳と高齢化が進み、日本では諸外国に比べて血液透析患者の割合が高い状況が続いています。第二に、災害対策の取組状況にばらつきがあり、災害時情報ネットワークへの登録や自治体等との連携体制を確保している医療機関は76.1%にとどまっています。第三に、シャント閉塞等への対応として事前に連携していない医療機関に紹介している医療機関が5.9%存在し、患者への不利益が懸念されます。第四に、腹膜透析の導入や診療を実施している医療機関は19.5%にとどまり、全ての患者に腎代替療法の3つの選択肢を提示している医療機関は51.2%です。第五に、緩和ケアを実施している医療機関は17.6%にとどまり、患者の意思決定支援も十分とはいえない状況です。
透析患者の動向と治療選択の現状
慢性維持透析患者数は343,508人で、2021年まで緩徐に増加していましたが2022年から減少傾向に転じています。この患者数減少の背景には、新規導入患者数が年間約3.9万人で推移する一方、高齢化の進展により透析中止や死亡が増加していることがあります。新規導入患者の平均年齢は71.6歳、慢性透析患者全体の平均年齢は70.1歳となっており、透析患者の高齢化が顕著です。
この高齢化は治療選択にも影響を及ぼしています。腹膜透析患者数は10,585人で2021年より増加傾向ですが、新規導入患者数は2,350人で2019年のピーク(2,657人)から減少しています。腹膜透析は在宅で実施できる利点がありますが、導入には患者本人や家族の協力が必要なため、高齢化により導入が難しくなっている可能性があります。
日本の透析医療は諸外国と比較して特徴的な状況にあります。腎代替療法のうち血液透析患者の割合が諸外国に比べて高く、腹膜透析や腎移植の割合が低い状況が続いています。この状況は医療提供体制の課題とも関連しており、患者の治療選択肢を広げる取組が求められています。
医療提供体制における3つの課題
血液透析の提供体制には3つの重要な課題があります。第一に災害対策、第二にシャントトラブルへの対応、第三に腹膜透析の導入です。
災害対策については、国や地方自治体と日本透析医会が連携して取組を進めています。しかし各医療機関の災害対策の取組状況にはばらつきがみられ、災害時情報ネットワークへの登録や自治体等との連携体制を確保していると回答した医療機関は76.1%にとどまっています。透析患者は定期的な透析治療を必要とするため、災害時でも治療を継続できる体制整備が不可欠です。
シャントトラブルへの対応には連携体制の課題があります。シャント閉塞等は発生頻度が高く、透析患者の入院理由としても最も多い疾患です。自院で治療している医療機関が23.4%、事前に連携している医療機関に紹介している医療機関が70.2%である一方、事前に連携していない医療機関に紹介している医療機関が5.9%存在します。事前連携がない場合、患者は迅速な治療を受けられず大きな不利益を被る可能性があります。
腹膜透析の導入には大きな課題があります。血液透析を実施する医療機関のうち、腹膜透析の導入や診療を実施している医療機関は19.5%にとどまり、77.1%の医療機関は腹膜透析を自院で実施していません。実施していない理由として、対象となる患者がいないが59.5%と最も多く、次いで対応できる器具設備を備えていないためが38.6%でした。また、緊急時や入院時のバックアップ体制に不安があるという意見もあり、医療機関間の連携体制整備が必要です。
患者支援の充実に向けて
患者への情報提供と意思決定支援には改善の余地があります。全ての患者に対し、血液透析、腹膜透析、腎移植の3つの選択肢を提示している医療機関は51.2%にとどまり、情報提供の取組をしていない医療機関が35.6%存在します。患者が自身の状況に応じた最適な治療法を選択するには、十分な情報提供が不可欠です。
通院困難な患者への対応も課題です。対応方法として、透析医療を提供する療養病床への案内が77.1%、介護施設への案内が63.9%である一方、腹膜透析の導入を含めた在宅医療への案内は5.4%にとどまっています。腹膜透析は通院負担を軽減できる治療法ですが、十分に活用されていない状況です。
緩和ケアの実施も十分とはいえません。医療用麻薬を用いた疼痛緩和を実施している医療機関は32.2%、緩和ケアを実施している医療機関は17.6%にとどまっています。透析患者の高齢化が進む中、終末期や透析医療中止に関する意思決定支援を含めた緩和ケアの充実が求められます。
評価方法の見直しと今後の方向性
分科会では、患者のQOLを考慮した質の高い透析医療を推進する観点から、人工腎臓の評価方法を見直すべきという意見が示されました。慢性維持透析を行った場合2及び3の算定回数は減少傾向で、人工腎臓全体の2.1%であることから、透析用監視装置の台数や透析用監視装置一台当たりの患者数による評価方法の見直しが検討されています。
シャントトラブルへの対応では、治療施設と事前に連携していないと患者への不利益が大きいことから、事前に連携することを促す評価方法の検討が提案されました。この評価により、医療機関間の連携体制が強化され、患者が迅速に適切な治療を受けられる環境整備が期待されます。
腹膜透析を増やしていくためには、導入期だけでなく血液透析からの切り換えも促していくことが考えられます。腹膜透析は在宅で実施でき、通院負担を軽減できる利点があります。医療機関が腹膜透析を導入しやすい環境を整備し、患者に十分な情報提供を行うことで、患者の治療選択肢を広げることができます。
通院困難な患者への対応として、療養病床や介護施設を案内すると回答した割合が高い一方、地域によってはこのような対応が難しい地域もあります。分科会では、医療機関へのアクセス確保の対応も検討すべきという意見が示されており、地域の実情に応じた対応が求められています。
まとめ
透析医療は患者数減少と高齢化という転換期を迎えており、質の高い医療提供体制の確立が急務です。分科会では、災害対策の強化、シャントトラブルへの連携促進、腹膜透析の推進、情報提供の充実、緩和ケアの実施という5つの課題が明らかになりました。患者のQOLを考慮した質の高い透析医療を推進するため、人工腎臓の評価方法を見直し、医療機関の取組を促す仕組みづくりが進められる見込みです。