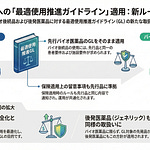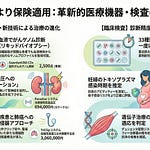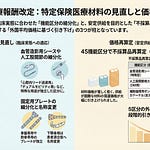令和7年度第11回診療報酬調査専門組織入院・外来医療等の調査・評価分科会の報告により、包括期入院医療の実態と課題が明らかになりました。高齢化社会における救急医療と在宅医療の連携強化が求められる中、地域包括医療病棟と地域包括ケア病棟の機能評価に関する新たな指標が検討されています。本報告書では、医療資源投入量のばらつきと高額薬剤による受入困難事例の実態を詳細に分析し、2026年度診療報酬改定に向けた重要な論点を提示しています。
調査結果は、包括期病院の救急受入と後方支援機能の評価指標に大きな課題があることを示しています。在宅患者緊急入院診療加算や協力対象施設入所者入院加算の算定状況は施設により二極化しており、地域医療の実態に即した評価体系の構築が急務となっています。また、包括内の出来高実績点数には診断群分類や入院経路により440点もの差が生じており、現行の包括算定方式の見直しが必要です。さらに、生物学的製剤や分子標的治療薬などの高額薬剤が受入困難の要因となっており、除外薬剤の設定についても再検討が求められています。
包括期病院の機能評価指標の現状と課題
包括期の入院医療を担う病院の機能評価において、救急搬送の受入と在宅・施設等の後方支援という2つの観点が重要な指標として位置づけられています。診療情報・指標等作業グループ(指標等WG)の検討により、評価指標の候補として救急搬送受入件数、下り搬送等受入件数、当該病棟への直接緊急入院、在宅患者緊急入院診療加算、協力対象施設入所者入院加算、介護保険施設等連携往診加算の算定回数が挙げられました。これらの指標は、地域医療における包括期病院の役割を定量的に評価するための重要な尺度となります。
現状の調査結果では、各指標の実績に大きなばらつきが確認されています。在宅患者緊急入院診療加算と協力対象施設入所者入院加算の病床あたり算定回数は、いずれも0件の施設が最多である一方、算定している施設では月に5件を超える施設も存在し、二極化が顕著です。地域包括医療病棟では比較的算定割合が高く、地域包括ケア病棟においては入院料1・3で2・4より多い傾向が見られました。この二極化は、各医療機関の地域における役割や連携体制の違いを反映していると考えられます。
救急搬送からの入院や自宅・施設からの緊急入院についても、施設により大きな差が生じています。地域包括医療病棟では月50床あたり20件を超える緊急入院を受け入れている施設がある一方、地域包括ケア病棟では0件の施設が多数を占めています。救急搬送からの入院が15%を超える地域包括ケア病棟では、在宅復帰率が80%を超え、平均在院日数は16日以下という良好なアウトカムを示していますが、重症度、医療・看護必要度は低い傾向にあり、現行の施設基準との整合性に課題があります。
協力医療機関の状況についても、重要な知見が得られています。地域包括医療病棟や地域包括ケア病棟を有する医療機関では、他の病棟を主とする病院と比較して多くの施設の協力医療機関を担っており、特別養護老人ホームや介護老人保健施設との連携が進んでいます。高齢者施設等の調査では、要件を満たす協力医療機関を定めている施設の方が救急車による搬送が少ないという結果が示され、平時からの連携体制の重要性が裏付けられました。
医療資源投入量の実態と包括算定の課題
地域包括医療病棟における包括内の出来高実績点数の分析により、医療資源投入量に大きなばらつきがあることが明らかになりました。診断群分類ごとの分析では、緊急入院が多い疾患や手術を行うことが少ない疾患において、包括内の出来高実績点数が高い傾向が確認されています。特に誤嚥性肺炎、肺炎等、腎臓又は尿路の感染症などの内科系疾患では、外科系疾患と比較して相対的に高い医療資源投入が必要となっています。
患者ごとの包括内出来高実績点数を詳細に分析すると、予定入院と緊急入院、手術の有無により大きな差が生じています。手術を行わない緊急入院群では1日あたり926点(中央値724点)であるのに対し、手術目的の予定入院群では490点(中央値369点)と、約440点もの差が生じています。この差は、緊急入院患者に対する集中的な医療提供の必要性を反映していますが、現行の包括算定方式では適切に評価されていない可能性があります。
地域包括ケア病棟における医療資源投入量は、地域包括医療病棟と比較してばらつきが少ない傾向にあります。1日あたり包括内出来高実績点数の平均値は594点(中央値565点)で、入棟経路による差は比較的小さくなっています。ただし、自宅や施設からの直接緊急入院では、他の入棟経路と比較して医療資源投入量が高い傾向が見られ、地域における救急医療の最前線としての役割を反映しています。
診断群分類による医療資源投入量の違いも重要な論点です。地域包括医療病棟では、股関節・大腿近位の骨折、胸椎・腰椎以下圧迫骨折などの整形外科系疾患で「請求点数/包括される点数の出来高換算点数」の比が10を超える一方、肺炎等の内科系疾患では比が小さい傾向にあります。この差は、手術や処置に係る技術料の違いを反映していますが、包括算定における公平性の観点から検討が必要です。
高額薬剤による受入困難事例と今後の対応
入院受入が困難となる理由として、高額薬剤の使用が大きな課題となっています。調査結果では、回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟、療養病棟のいずれにおいても、「高額薬剤を使用している」ことが受入困難理由の上位に挙げられています。具体的には、4割を超える施設がトルバプタン(心不全治療薬)、パーキンソン病治療薬、血友病以外の出血傾向抑制薬を困難事例として挙げています。
自由記載による詳細分析では、骨粗鬆症治療薬(イベニティ、プラリア等)や生物学的製剤を含む分子標的治療薬が多く挙げられました。特に回復期リハビリテーション病棟では、27.3%の施設が抗がん剤を受入困難薬剤として回答しており、他に医療用麻薬、間質性肺炎治療薬、腎性貧血治療薬も特有に挙げられています。これらの薬剤は現行の除外薬剤に指定されていないため、包括算定により医療機関の負担が大きくなっています。
現行の除外薬剤の設定には、病棟種別により差があることも課題です。地域包括医療病棟と地域包括ケア病棟では抗悪性腫瘍剤や疼痛コントロールのための医療用麻薬が除外薬剤となっている一方、回復期リハビリテーション病棟では包括算定の対象となっています。また、受入困難事例として多く挙げられた生物学的製剤を含む分子標的治療薬は、いずれの入院料においても除外薬剤になっておらず、高額薬剤使用患者の受入を阻害する要因となっています。
療養病棟では、薬価そのものに言及した回答が多く、「月3万円以上」「1日2千円以上」「薬価が500円/1000円以上不可」といった具体的な金額基準を設けている施設もあります。これは、包括算定における採算性の観点から、やむを得ず受入制限を行っている実態を示しており、地域医療における患者の受入体制に影響を与えている可能性があります。
まとめ
令和7年度第11回診療報酬調査専門組織入院・外来医療等の調査・評価分科会の報告から、包括期入院医療の機能評価と医療資源投入量の分析により、現行制度の課題と今後の検討方向が明確になりました。救急受入と後方支援機能の評価指標については、施設間のばらつきを踏まえた適切な基準設定が必要であり、地域の実情に応じた柔軟な評価体系の構築が求められます。医療資源投入量のばらつきに対しては、緊急入院や手術の有無を考慮した包括算定方式の見直しが必要であり、高額薬剤については除外薬剤の拡大を含めた対応策の検討が急務となっています。2026年度診療報酬改定においては、これらの課題に対する具体的な解決策の実装が期待されます。