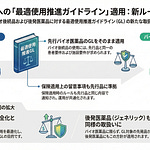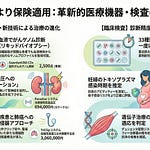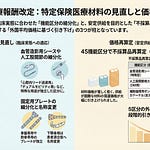令和7年9月11日に開催された第11回診療報酬調査専門組織の入院・外来医療等の調査・評価分科会において、診療情報・指標等作業グループから最終報告が提出されました。この報告では、20万人未満の二次医療圏における急性期医療の評価方法と、高齢者の入院医療における内科系疾患の適切な評価指標について、新たな方向性が示されています。特に注目すべきは、地域シェア率という新しい概念の導入と、地域包括医療病棟における医療資源投入量の詳細な分析です。
本報告の要点は3つあります。第一に、人口規模の小さい医療圏では救急搬送受入件数の絶対数ではなく地域シェア率による評価が必要であることが明らかになりました。第二に、内科系疾患は包括内の出来高点数が高く、現行の評価体系では適切に評価されていない実態が判明しました。第三に、重症度、医療・看護必要度のB項目について、測定負担の軽減と評価の適正化に向けた具体的な提案がなされました。これらの知見は、令和8年度診療報酬改定に向けた重要な検討材料となります。
急性期医療の地域特性を踏まえた新たな評価指標
急性期医療の評価において、二次医療圏の人口規模による格差が大きな課題として浮き彫りになりました。20万人未満の医療圏では、救急搬送受入件数の絶対数は少ないものの、地域医療における役割は極めて重要です。作業グループの分析により、こうした医療圏において地域シェア率が高い病院が、現行の総合入院体制加算等では評価されていない実態が明らかになりました。
地域シェア率は、当該医療機関の年間救急搬送受入件数を所属二次医療圏内の全医療機関の合計受入件数で除した値として定義されます。この指標により、人口規模に関わらず、地域における医療機関の相対的な貢献度を評価することが可能になります。ただし、二次医療圏の再編による影響を受けやすいという課題も指摘されており、慎重な制度設計が求められています。
総合入院体制加算と急性期充実体制加算の整理統合についても議論が進展しました。両加算で異なる実績要件を統一し、人口が少ない地域における要件緩和を検討することで、地域の実情に応じた評価体系の構築を目指しています。特に、圏域設定における人口規模の線引きについては、今後の重要な検討課題として位置づけられています。
地域包括医療病棟における内科系疾患の医療資源投入量分析
地域包括医療病棟の新設に伴い、高齢者の救急入院における医療資源投入量の詳細な分析が実施されました。内科系疾患は、包括される包括内の出来高点数が相対的に高く、請求点数には反映されにくい傾向が明確になりました。特に、救急搬送からの入院や緊急入院の割合が高く、手術を行わない緊急入院では医療資源投入量が他の入院形態と比較して顕著に高いことが判明しています。
疾患別の分析では、誤嚥性肺炎、肺炎、その他の感染症が上位を占めており、これらの疾患では緊急入院率が90%を超えています。85歳以上の高齢者では、内科系症例の約9割が緊急入院であり、外科系症例と比較して救急搬送や緊急入院の割合が著しく高い実態が明らかになりました。この結果は、高齢者医療における内科系疾患の重要性と、現行評価体系の見直しの必要性を示唆しています。
在院日数の分析からは、高齢であること、転院転棟を除く直接入院であること、入院初日のADLが低いこと、入院初日のB項目点数が高いことが、在院日数の長期化と強く関連することが示されました。これらの要因は相互に関連しており、高齢者の入院医療における複雑な患者像を反映しています。アウトカム指標としての在院日数評価には、これらの要因を考慮した多角的な検討が必要です。
重症度、医療・看護必要度の測定負担軽減と評価の適正化
重症度、医療・看護必要度のB項目について、測定負担と評価の適正化に関する具体的な提案がなされました。B項目は、入院や手術から4~7日後には点数の変化が少なくなる傾向が確認されており、この知見に基づいて測定間隔の緩和が検討されています。特に、術後7日目以降や内科系症例の入院4日目以降については、測定頻度を減らすことで現場の負担軽減が可能との見解が示されました。
内科系症例における評価の課題も明確になりました。A・C項目が一定点数以上である割合が外科系疾患と比較して低く、特に抗菌薬がA項目で評価されないため、感染症患者の重症度が適切に反映されていません。この問題に対し、緊急入院の評価日数を5日間に延長する案や、病床あたり緊急入院受入件数を直接評価する案など、複数の改善策が提示されています。
測定の簡略化と評価の質の両立に向けて、B項目の役割の再定義も議論されました。B項目は、急性期看護や高齢者ケアの手間を反映する指標として、人員配置や入退院支援、転倒・転落リスク判断等の病棟マネジメントに活用されている実態があります。今後は、A・B・C項目全体で患者像を表現し、必要なケアを評価するリアルワールドデータとしての活用が期待されています。
今後の診療報酬改定に向けた展望
診療情報・指標等作業グループの最終報告は、令和8年度診療報酬改定に向けた重要な方向性を示しています。地域医療圏の人口規模に応じた評価体系の構築、高齢者の入院医療における内科系疾患の適切な評価、重症度評価の測定負担軽減という3つの柱は、いずれも医療現場の実態を踏まえた実践的な提案です。特に、地域シェア率の導入と内科系疾患の医療資源投入量分析は、これまでの診療報酬体系では十分に評価されてこなかった領域に光を当てるものです。今後は、これらの提案を具体的な制度設計に落とし込み、地域医療の持続可能性と医療の質の向上を両立させる改定が求められます。