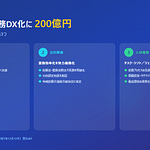令和7年7月16日に開催された中央社会保険医療協議会総会(第612回)で、外来医療をとりまく環境について議論されました。日本の外来医療は2025年をピークに患者数が減少局面に入り、既に224の医療圏では2020年までにピークを迎えています。この現状に対応するため、令和7年4月から「かかりつけ医機能報告制度」が施行されます。医療機関は都道府県知事にかかりつけ医機能を報告し、地域の協議の場で不足する機能を確保する方策を検討します。
本記事では、外来医療改革の3つの柱を説明します。第一は、かかりつけ医機能報告制度の創設です。第二は、医師偏在対策の強化です。第三は、医療資源の少ない地域への配慮です。各医療機関が自らの機能を報告し、地域で連携しながら必要な医療を提供する体制が構築されます。
かかりつけ医機能報告制度が構築する新たな外来医療体制
かかりつけ医機能報告制度は、令和7年4月から施行される外来医療改革の中核となる制度です。慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、医療機関から都道府県知事に報告を求めます。報告を受けた都道府県知事は、医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに公表します。
報告を求めるかかりつけ医機能の内容は、大きく3つに分類されます。第一は「日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能」です。継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療を総合的に実施します。第二は「通常の診療時間外の診療、入退院時の支援、在宅医療の提供、介護等と連携した医療提供」です。時間外診療や入退院支援などの機能を担います。第三は「健診、予防接種、地域活動、教育活動、今後担う意向等」です。地域全体での医療提供体制の充実に貢献します。
都道府県知事による確認を受けた医療機関は、慢性疾患を有する高齢者に在宅医療を提供する場合など外来医療で説明が特に必要な場合であって、患者が希望する場合に、かかりつけ医機能として提供する医療の内容について電磁的方法又は書面交付により説明するよう努めます。説明内容は、疾患名や治療計画、当該医療機関の連絡先等に加えて、当該患者に対する機能の内容、連携医療機関等を含みます。患者は自らのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるようになります。
医師偏在対策が推進する地域医療の最適化
医師偏在対策は、地域偏在と診療科偏在の両面から総合的に実施されます。令和6年12月25日に厚生労働省が公表した「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」では、医師養成過程を通じた取組、医師確保計画の実効性の確保、地域偏在対策における経済的インセンティブ等、診療科偏在の是正に向けた取組が示されています。
重点医師偏在対策支援区域の設定により、優先的・重点的に対策を進めます。今後も定住人口が見込まれるが人口減少より医療機関の減少スピードが速い地域等を「重点医師偏在対策支援区域」と設定します。重点区域は、厚生労働省の示す候補区域を参考としつつ、都道府県が可住地面積あたり医師数、アクセス、人口動態等を考慮し、地域医療対策協議会・保険者協議会で協議の上で選定します。医師確保計画の中で「医師偏在是正プラン」を策定し、重点区域、支援対象医療機関、必要な医師数、取組等を定めます。
経済的インセンティブの導入も検討されています。令和8年度予算編成過程で重点区域における支援について検討し、診療所の承継・開業・地域定着支援、派遣医師・従事医師への手当増額、医師の勤務・生活環境改善、派遣元医療機関へ支援などが含まれます。診療科偏在の是正に向けては、必要とされる分野が若手医師から選ばれるための環境づくり等、処遇改善に向けた必要な支援を実施します。外科医師が比較的長時間の労働に従事している等の業務負担への配慮・支援等の観点での手厚い評価について必要な議論を行います。
医療資源の少ない地域における診療報酬上の配慮
医療資源の少ない地域に配慮した診療報酬上の評価は、平成24年度改定から段階的に拡充されてきました。平成28年度改定では、対象地域に関する要件を見直し、患者の流出率についての要件を緩和するとともに、医療従事者が少ないこと自体を要件化しました。令和2年度改定では、医師に係る要件を緩和し、「人口当たり医師数が下位3分の1」から「人口当たり医師数が下位2分の1」に変更しました。
令和6年度改定では、回復期リハビリテーション病棟に相当する機能を有する病室について、届出を病室単位で可能な区分を新設しました。地域包括ケア病棟入院料2及び4の施設基準における、「自院の一般病棟からの転棟患者の割合」に関する要件を緩和しました。在宅療養支援病院・診療所に係る24時間の往診体制の要件について、D to P with N(医師と看護師が連携して患者に対応する体制)の実施体制を整備することで要件を満たすこととする緩和を実施しました。
二次医療圏の人口規模は多様であり、中央値は約22万人です。人口規模が20万人未満の二次医療圏は157、100万人以上の二次医療圏は25あります。2040年には、人口規模が20万人未満の二次医療圏は182、10万人未満の二次医療圏は109となると推計されます。人口の少ない二次医療圏では、総合入院体制加算や急性期充実体制加算の件数要件の達成が困難な場合があるため、地域の実情を踏まえた基準緩和や代替的な評価の検討が必要です。
まとめ
令和7年4月施行のかかりつけ医機能報告制度は、外来医療改革の中核となる制度です。医師偏在対策の強化により、重点医師偏在対策支援区域への優先的な支援が実施されます。医療資源の少ない地域への診療報酬上の配慮は、段階的に拡充されてきました。各医療機関が自らの機能を報告し、地域で連携しながら必要な医療を提供する体制が構築され、複数の慢性疾患や医療・介護の複合ニーズを有する高齢者が増加する中で、地域の医療機関等や多職種が機能や専門性に応じて連携して、効率的に質の高い医療を提供する体制が確保されます。