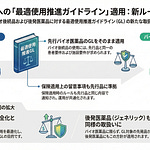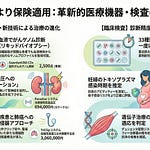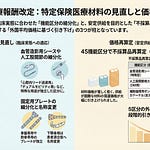令和7年度第11回診療報酬調査専門組織入院・外来医療等の調査・評価分科会において、重症度、医療・看護必要度の評価体系に関する重要な議論が展開されました。現行制度では、B項目(ADL評価)の測定負担が医療現場の大きな課題となっています。内科系症例が外科系症例と比較して基準該当割合が低く、適切な評価を受けにくい状況も明らかになりました。今回の分科会では、これらの課題解決に向けた具体的な改革案が検討されています。
改革の焦点は、B項目の測定頻度の見直しと内科系症例への評価強化の2点に集約されます。B項目については、入院4日目以降や術後7日目以降の変化が少ないことから、測定間隔の緩和が提案されました。内科系症例については、救急搬送件数や協力対象施設入所者入院加算の算定数を重症度評価に反映させる新たな指標の導入が検討されています。これらの改革により、医療現場の負担軽減と適正な患者評価の両立を目指します。
B項目評価の現状と測定負担の実態
B項目の評価は、患者の状態と介助の実施を組み合わせた指標として機能しています。入院初日のB得点3点以上の割合は、特定機能病院で約10%、急性期一般入院料1で約30%と低く、地域包括医療病棟では66%と高い値を示しています。この差は、病棟の機能と患者像の違いを反映しています。
測定負担について、病棟看護管理者の約半数が「看護職員による記録忘れが多い」と回答しています。「看護必要度に関する職員研修に手間がかかる」という課題も、必要度Ⅰでは35.5%、必要度Ⅱでは31.8%が指摘しています。これらの負担は、日々の看護業務に影響を与えている実態が明らかになりました。
要介護度とB得点の相関関係も重要な知見として確認されています。要介護4-5の患者では、入院時と退院時でB得点の分布にほとんど変化がみられません。これは、元々の介護必要度が高い患者では、疾病による身体機能の変化よりも、既存の介護ニーズが評価に大きく影響することを示唆しています。
経時的変化から見るB項目測定の最適化
B得点の経時的変化の分析から、測定頻度を最適化できる可能性が示されました。手術非実施症例では入院4日目以降、手術実施症例では術後7日目以降、前日から変化しない患者の割合が約7割に達します。この安定期における毎日の測定は、必ずしも必要ではない可能性があります。
A項目との連動性も明らかになっています。A項目が変化しない場合、B項目も変化しない患者の割合が高く、特に安定期では75%に達します。一方、A項目が3点以上変化した場合は、B項目も同方向に変化する傾向が観察されました。この関係性を活用した効率的な測定方法の開発が期待されます。
予定入院と緊急入院の比較では、異なるパターンが観察されています。予定入院では入院3-7日目にB得点が改善する傾向がある一方、緊急入院では初期から変化が少ない傾向があります。これらの特性を踏まえた、入院形態別の測定プロトコルの検討も有効と考えられます。
内科系症例の評価課題と新たな指標の提案
内科系症例は外科系症例と比較して、A項目2点以上の該当割合が約15ポイント低い状況にあります。C項目(手術等)では、内科系症例の該当割合はわずか1.3%に留まっています。この評価格差は、内科系患者を多く受け入れる医療機関にとって深刻な課題となっています。
救急搬送や緊急入院の約8割を内科系症例が占めているという事実も重要です。内科系症例で割合が高いA項目の下位項目は、呼吸ケア、免疫抑制剤の使用、緊急入院等に限定されています。現行の評価体系では、内科系診療の負荷が十分に反映されていない構造的な問題が存在します。
新たな評価指標として、病床あたりの救急搬送件数と協力対象施設入所者入院加算算定数の活用が提案されています。これらの指標を重症度該当割合に加算することで、内科系症例を多く受け入れる医療機関の負荷を適切に評価できます。例えば、1床あたり年間20件の救急搬送等がある場合、該当患者割合に4%程度の加算を行うという具体的な計算例も示されました。
今後の改革に向けた具体的方向性
日本病院会からは、B項目評価を不要とする要件緩和の要望が提出されています。施設基準の要件でない入院料等については、B項目評価を不要とすることで、看護職員の負担を大幅に軽減できるという提案です。この要望は、現場の切実な声を反映したものといえます。
内科学会からは、A・C項目への追加候補リストが提示されました。中心静脈注射用カテーテル挿入、脳脊髄腔注射、吸着式血液浄化法など、内科系診療で頻回に実施される処置の追加が提案されています。これらの追加により、内科系症例の該当患者割合が約3.5ポイント改善するというシミュレーション結果も示されています。
測定間隔の緩和については、段階的な実施が検討されています。まず安定期(入院4日目以降、術後7日目以降)での測定頻度の削減を検討し、その効果を検証した上で、さらなる緩和を検討するという慎重なアプローチが提案されています。
まとめ
重症度、医療・看護必要度の改革は、医療現場の負担軽減と適正な患者評価の両立を目指す重要な取組みです。B項目の測定頻度の最適化により、看護職員の業務負担を軽減しながら、必要な評価精度を維持することが可能となります。内科系症例への新たな評価指標の導入により、急性期医療における公平な評価体系の構築が期待されます。