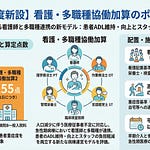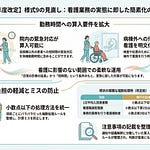令和7年7月16日に開催された中央社会保険医療協議会(中医協)総会第612回において、外来診療の診療内容と医療費に関する重要なデータが報告されました。この報告は、外来医療の実態を把握し、今後の診療報酬改定の基礎資料とする目的で作成されました。社会医療診療行為別統計と医療費の動向調査を基に、病院と診療所における外来診療の診療報酬構成の変化、診療科別の医療費動向、令和6年度診療報酬改定後の影響が明らかになりました。
報告の要点は3つあります。第一に、病院の外来診療では診療報酬点数が平成30年の1,516点から令和6年には1,891点へと大きく増加した一方、診療所では898点から932点へとわずかな増加にとどまり、ほぼ横ばいで推移しています。第二に、診療科別では整形外科の1施設あたり月額医療費が約1,000万円と最も高く、令和6年度改定後にさらに増加しました。第三に、診療報酬構成では病院で注射が約225点増加するなど大幅に増加し、診療所では検査と在宅医療が増加する一方で注射は大きく減少しています。
外来診療における診療報酬点数の推移と病院・診療所の違い
外来診療の診療報酬点数は、病院と診療所で異なる推移を示しています。病院の入院外1日あたりの診療報酬点数は、平成30年の1,516点から令和6年には1,891点へと約375点増加しました。この増加は、主に注射が291点から516点へと約225点増加、在宅医療が103点から141点へ約38点増加、検査が293点から349点へ約56点増加したことによります。
診療所の診療報酬点数は、平成30年の898点から令和6年には932点へと約34点増加し、ほぼ横ばいで推移しています。診療所では、検査が116点から142点へ約26点増加、在宅医療が46点から66点へ約20点増加、医学管理等が80点から98点へ約18点増加した一方で、投薬が210点から182点へ約28点減少、注射が72点から31点へ約41点減少しました。
この違いは、病院と診療所の機能分化を反映しています。病院では高度な医療技術を要する注射や在宅医療が大きく増加し、診療所では日常的な検査と在宅医療の提供が強化される一方、投薬や注射は減少しています。
診療科別にみる1施設あたり月額医療費の動向
診療科別の1施設あたり月額医療費では、整形外科が最も高い水準を示しました。令和6年6月から令和7年2月までのデータによると、整形外科は約1,000万円、内科は約500万円、眼科は約500万円でした。
令和6年度診療報酬改定後の変化では、診療科による違いが明確になりました。整形外科、皮膚科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科では医療費が増加し、内科、小児科、外科、その他では減少しました。
整形外科の医療費が高い理由は、1施設あたり月間受診延日数が約2,500日と最も多く、リハビリテーションや処置などの診療報酬点数が高いためです。内科は受診延日数が約1,000日と整形外科の半分以下ですが、投薬や検査が診療報酬の主要な構成要素となっています。
診療所における診療科別の診療報酬構成の特徴
診療所の診療科別診療報酬構成は、各診療科の特性を反映した特徴的なパターンを示しています。令和6年のデータでは、内科の1日あたり診療報酬は約730点で、投薬が約180点、検査が約140点、医学管理等が約100点を占めました。
精神科は約880点と診療所全体の平均より高く、精神科専門療法が約280点、投薬が約180点と特徴的な構成です。小児科は約610点で、医学管理等が約170点と他の診療科より高い割合を占め、小児かかりつけ診療料などが含まれています。
泌尿器科は約1,050点と高い水準で、処置が約420点と診療報酬の約4割を占めます。この処置には人工腎臓及び特定保険医療材料等が含まれており、透析医療を反映した特徴的な構成となっています。整形外科は約940点で、リハビリテーションが約270点、処置が約140点と、機能回復を重視した診療内容が示されています。
診療所の入院外受診延日数の診療科別分布
診療所の入院外受診延日数を診療科別に分析すると、外来医療需要の構造が明らかになります。令和5年度のデータでは、総受診延日数約12億日のうち、内科が38%、整形外科が17%、眼科が8%、皮膚科と耳鼻咽喉科がそれぞれ7%、小児科が6%でした。
内科の受診延日数が最も多い理由は、高血圧症や糖尿病などの慢性疾患患者が継続的に受診するためです。整形外科は腰部脊柱管狭窄症や変形性膝関節症などの患者が定期的なリハビリテーションや処置のために受診します。
令和6年度診療報酬改定後、小児科、産婦人科、耳鼻咽喉科では受診延日数が増加し、その他の診療科では横ばいから微減となりました。この変化は、改定による評価の見直しが診療行動に影響を与えたことを示唆しています。
まとめ
中医協第612回総会で報告された外来診療の診療内容と医療費のデータから、3つの重要な動向が明らかになりました。病院では診療報酬点数が平成30年の1,516点から令和6年には1,891点へと約375点増加し、特に注射が約225点増加するなど大幅な伸びを示しました。診療所では898点から932点へとわずか34点の増加にとどまり、ほぼ横ばいで推移しています。診療科別では整形外科の1施設あたり月額医療費が約1,000万円と最も高く、令和6年度改定後も増加を続けました。診療報酬構成では病院で注射と在宅医療が大きく増加し、診療所では検査と在宅医療が増加する一方で注射は大幅に減少しています。これらのデータは、外来医療における病院と診療所の機能分化の進展と、各診療科の特性に応じた診療内容の変化を示しており、今後の診療報酬改定における重要な基礎資料となります。