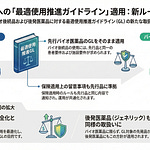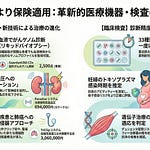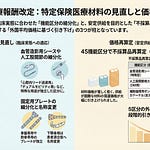令和6年度診療報酬改定で創設されたリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算は、急性期医療における多職種連携の新たなモデルを示しています。令和7年度第11回入院・外来医療等の調査・評価分科会では、この加算の効果検証と病棟における多職種ケアの実態が明らかになりました。本稿では、加算導入から1年余りが経過した現在の成果と課題について、最新のデータに基づき解説します。
調査結果から、連携体制加算を算定した患者群では、ADL(日常生活動作)が大きく改善した割合が高く、早期リハビリテーション介入率が約9割に達することが判明しました。休日のリハビリテーション提供量は平日の86.5%を維持し、継続的なケアが実現しています。さらに、管理栄養士や臨床検査技師の病棟配置により、栄養管理の充実と検査業務の効率化が進んでいます。一方で、退院時のADL低下率や歯科受診率の改善、専門職間の業務分担の最適化など、今後検討すべき課題も浮き彫りになりました。
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の導入効果
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算は、急性期病棟において多職種が連携し、患者のADL維持・向上を図る取り組みを評価するものです。加算の算定要件として、専従の理学療法士等2名以上、専任の管理栄養士1名以上の配置が必要となります。また、入棟後48時間以内の評価・計画作成、土日祝日のリハビリテーション提供量が平日の8割以上、ADL低下患者割合3%未満など、厳格な施設基準が設定されています。
DPCデータの分析結果によると、加算算定ありの患者では、退院時にADLが10以上改善した割合が25.7%と、算定なしの14.1%を大きく上回りました。特筆すべきは、入院3日目までのリハビリテーション開始率が89.2%に達し、算定なしの68.5%と比較して早期介入が顕著に進んでいる点です。患者1人当たりの1日平均リハビリテーション単位数も、算定ありで3.1単位と、算定なしの2.3単位を上回る結果となりました。
加算算定施設における休日のリハビリテーション提供体制も充実しており、土曜日94.1%、日曜日87.8%、祝日65.1%と高い水準を維持しています。これは、算定なし施設の休日全体34.1%と比較して、約2.5倍の提供量となっており、切れ目ないリハビリテーションの実施が患者のADL改善に寄与していることが示唆されます。
地域包括医療病棟における多職種連携の実態
令和6年度改定で新設された地域包括医療病棟入院料では、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算が設定されています。この病棟では、救急患者の受け入れとともに、早期からのリハビリテーション、栄養管理、口腔管理を包括的に提供することが求められています。
地域包括医療病棟における連携加算算定患者のADL改善率は42.9%と高く、入院3日目までのリハビリテーション開始率は92.9%に達しています。急性期一般病棟と比較しても、リハビリテーション介入の早期化と高頻度化が実現されています。休日のリハビリテーション提供量も平日の86.0%を維持し、継続的なケアが担保されています。
療法士の病棟業務への関与状況を見ると、生活機能の回復に向けた支援において、食事で46.0%、排泄で71.9%、離床の促しで76.6%の病棟で療法士が関与しています。これは地域包括ケア病棟と比較して高い割合となっており、専門職の積極的な関与が患者の生活機能回復に寄与していることが分かります。
管理栄養士と臨床検査技師の病棟配置がもたらす変化
管理栄養士の病棟配置は、栄養管理の質向上に大きく貢献しています。就業時間の5割以上を病棟で従事している管理栄養士は全体の38.1%にとどまりますが、病棟配置された管理栄養士は、GLIM基準による栄養評価、ミールラウンド、食事変更の調整など、専門性の高い業務を展開しています。
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算算定患者では、低栄養(GLIM基準)の入力割合が74.4%と、算定なしの58.8%を上回り、栄養状態の把握が進んでいます。また、入院栄養食事指導料の算定率も25.1%と、算定なしの16.7%より高く、栄養介入の充実が図られています。入院時に低栄養であった患者に対しても、積極的な栄養管理が実施されています。
臨床検査技師の病棟配置は、約3割の病棟で検査の準備や実施への関与が見られます。早朝採血、心電図測定、POCT検査の実施、検査結果の確認と医師への報告など、病棟に常駐することで迅速な検査実施と結果報告が可能となり、医師・看護師の負担軽減に寄与しています。検体再採取率の減少やインシデントの減少など、医療安全面での効果も報告されています。
看護業務のタスクシェアと専門職の役割分担
病棟における看護業務のタイムスタディ調査では、「診察・治療」と「患者のケア」に費やす時間が全体の約半分を占めることが明らかになりました。これらの業務において、多職種によるタスクシェアが進展しています。
診察・治療に係る業務では、栄養状態のスクリーニングは管理栄養士が87.0%の病棟で主として実施し、ADLのスクリーニングは理学療法士が23.1%の病棟で主として担当しています。薬剤の準備・セットは薬剤師が31.4%の病棟で主として実施しており、専門性に基づいた業務分担が進んでいます。一方、薬剤の投与やバイタルサイン測定、吸引などの直接的な医療行為は、依然として看護師が主として実施している状況です。
患者のケアに係る業務では、食事の配膳、排泄介助、見守り・付き添い、体位交換などで看護補助者が10~20%程度主として実施しています。環境整備については看護補助者が47.3%の病棟で主として担当しており、看護師の負担軽減に寄与しています。生活機能の回復支援では、排泄で理学療法士が3.9%、食事で作業療法士が2.3%、離床で理学療法士が15.2%の病棟で主として実施しており、専門性を活かした介入が行われています。
まとめ
病棟における多職種連携は、診療報酬改定を契機に大きく前進しました。リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の創設により、早期介入と継続的なケアが実現し、患者のADL改善に寄与しています。管理栄養士や臨床検査技師の病棟配置も進み、専門性を活かした質の高いケアが提供されています。今後は、退院時ADL低下率のさらなる改善、口腔管理と歯科受診の連携強化、専門職間の業務分担の最適化などの課題に取り組み、より効果的な多職種連携モデルの構築が期待されます。