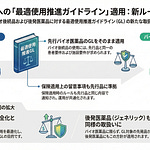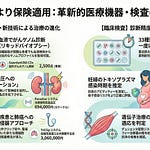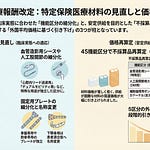令和7年9月11日に公表された全国医学部長病院長会議による調査は、大学病院における逆紹介の実態を明らかにした。全国82大学病院を対象に実施され、78病院から回答を得た本調査(回収率95.1%)は、令和7年6月の診療実績を分析している。調査結果は、診療報酬改定における外来機能分化の推進という政策目標に対し、大学病院が直面する構造的課題を浮き彫りにした。
本調査により、診療科別逆紹介割合の平均値は48.3‰となり、23診療科中4科が平均値で減算基準30‰を下回ることが判明した。形成外科系(8.7‰)、麻酔科系(6.4‰)、リハビリテーション系(8.7‰)、精神科系(24.6‰)の4診療科は、いずれも専門性の高い継続的な医療管理を要する特性を持つ。再診患者の88%が月1~2日の受診にとどまる一方で、外来化学療法患者が2.2%、高額医薬品使用患者が4.2%、指定難病患者が6.7%を占めており、これらの患者群が大学病院での継続診療を必要としている実態が明らかになった。大学病院からの逆紹介が困難な理由として、希少疾患や複雑な合併症などの疾患要因、患者の不安感などの患者側要因、地域における専門医不在などの医療提供体制の問題が挙げられている。
診療科別逆紹介割合の実態と基準未達成の背景
診療科別の逆紹介割合は、診療科の特性により大きな格差が生じている。循環器系(97.2‰)や整形外科系(84.6‰)が高い逆紹介割合を示す一方、形成外科系、麻酔科系、リハビリテーション系、精神科系の4診療科は平均値で減算基準30‰を大きく下回った。さらに、中央値で見ると、これら4診療科に加えて血液内科系、放射線系、皮膚科、産婦人科系の4診療科も基準を下回っており、合計8診療科で逆紹介が困難な状況が明らかになった。
形成外科系の逆紹介割合が8.7‰にとどまる背景には、術後の長期フォローアップが必要な症例が多いことがある。乳癌術後の乳房再建や、皮膚潰瘍・リンパ浮腫などの慢性疾患は、専門的な管理技術を要し、地域医療機関への紹介が困難である。麻酔科系(6.4‰)においては、帯状疱疹後神経痛や癌性疼痛など、高度な疼痛管理を必要とする患者が集中している。
リハビリテーション系(8.7‰)は、運動器疾患や脳血管障害後のリハビリテーションなど、継続的かつ専門的な介入を要する。精神科系(24.6‰)では、うつ病や統合失調症などの重症例が多く、病状の不安定さから地域医療機関への紹介にリスクを伴うケースが少なくない。これら4診療科に共通するのは、高度な専門性と継続的な医療管理の必要性であり、地域医療機関での対応が困難な患者層を抱えているという構造的な問題である。
再診患者の受診パターンと高額医療の集中
再診患者の受診日数分析により、月1~2日の受診が全体の88%を占めることが明らかになった。月1日の受診が70%、月2日が18%となっており、多くの患者は月1回程度の定期受診で管理されている。一方で、月3日が6%、月4日が3%、月5日以上が3%となっており、頻回受診を要する患者は全体の一部にとどまるが、これらの患者群には特徴的な疾患構成が見られる。
外来化学療法患者(1大学病院平均507人)と高額医薬品使用患者(同978人)を合わせると、再診実患者数の6.4%を占める。外来化学療法は、肺癌、乳癌、大腸癌などの悪性腫瘍患者が中心であり、レジメンに応じた定期的な通院を必要とする。高額医薬品使用患者には、生物学的製剤を使用する関節リウマチや炎症性腸疾患、分子標的薬を使用する血液疾患などが含まれる。
指定難病患者(1大学病院平均1,519人)は再診実患者数の6.7%を占め、パーキンソン病、多発性硬化症、全身性エリテマトーデスなどの疾患が上位を占める。これらの疾患は、専門的な診断・治療技術を要し、病状の変化に応じた細やかな薬剤調整が必要となる。生物学的製剤使用患者(同537人、2.4%)、小児慢性特定疾病患者(同219人、1.0%)、治験患者(同73人、0.3%)も、大学病院での継続的な管理が不可欠な患者群である。
逆紹介を阻む3つの構造的要因
大学病院からの逆紹介が進まない要因は、疾患・医療内容の要因、患者側の要因、その他の要因の3つに大別される。
疾患・医療内容の要因として最も重要なのは、希少疾患や複雑な合併症例の存在である。血液疾患、神経難病(ALS、多系統萎縮症など)、移植後の患者、小児がん患者などは、高度な専門性を要し、地域医療機関での対応が困難である。外来化学療法中の患者や、高額薬剤・生物学的製剤使用患者も、薬剤の副作用管理や効果判定に専門的知識を要する。臨床試験・治験実施中の患者は、プロトコールの遵守と安全性確保の観点から、実施医療機関での継続診療が必須となる。
患者側の要因では、大学病院への安心感・信頼感から「見捨てられるのでは」という不安を抱く患者が多い。症状が安定しても再発・悪化への不安から継続通院を希望し、逆紹介の受け入れを拒否するケースが見られる。複数診療科に通院している患者では、通院先が増えることへの負担感から拒否される場合もある。医療費の観点からも、大学病院でまとめて受診した方が患者負担が少ないという経済的インセンティブが働いている。
その他の要因として、地域における専門医や診療科の不在という医療提供体制の問題が大きい。身寄りがない、後見人がいない、経済的困窮などの社会的要因も逆紹介を困難にしている。受診態度に問題がある患者(クレーマー等)については、地域医療機関が受け入れを躊躇するケースもある。
政策的対応と今後の方向性
本調査結果は、診療報酬による誘導だけでは解決困難な構造的課題の存在を示している。平均値で減算基準を下回る4診療科、さらに中央値で基準を下回る8診療科については、疾患特性や専門性を考慮した基準の見直しが必要である。高額医薬品使用患者や外来化学療法患者については、地域医療機関との連携体制構築に向けた診療報酬上のインセンティブ設計が求められる。
患者の不安解消に向けては、逆紹介後も大学病院がバックアップする体制の明確化が重要である。地域医療機関の専門性向上に向けた教育・研修プログラムの充実、遠隔診療を活用した専門医によるサポート体制の構築など、医療提供体制の強化が不可欠である。社会的要因を抱える患者に対しては、医療ソーシャルワーカーの活用や地域包括ケアシステムとの連携強化が必要となる。
大学病院の外来機能を真に高度急性期医療に特化させるためには、診療報酬による経済的誘導に加え、地域医療提供体制の整備、患者の意識改革、医療機関間の連携強化という多面的なアプローチが必要である。本調査結果を踏まえ、令和8年度診療報酬改定において、より実効性の高い制度設計が行われることが期待される。
まとめ
全国78大学病院を対象とした逆紹介割合調査により、平均値で4診療科、中央値で8診療科が減算基準を下回り、高額医療を要する患者が大学病院に集中している実態が明らかになった。逆紹介が進まない背景には、疾患の専門性、患者の不安、地域医療体制の不備という3つの構造的要因が存在する。今後の診療報酬改定においては、診療科特性を考慮した基準設定、地域連携体制の強化、患者の不安解消に向けた制度設計が求められる。