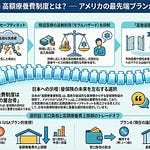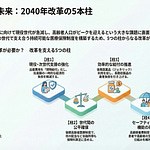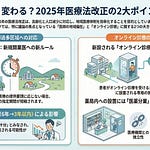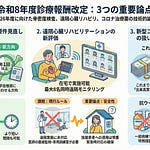令和7年度第13回入院・外来医療等の調査・評価分科会では、療養病棟入院基本料等の現状について検討結果がまとまりました。令和6年度末に介護療養病床が廃止されることに伴い、看護配置25対1の経過措置が令和6年5月末で終了したことを受け、慢性期医療提供体制の構築が求められています。新たな地域医療構想では、在宅医療需要への対応を見据え、療養病床だけでなく在宅医療や介護施設等とあわせた体制整備が重要とされました。
分科会では療養病棟における医療区分の充足状況、栄養管理体制、在宅復帰の取組、障害者施設等入院基本料の4つの観点から現状を分析しました。医療区分2・3の施設基準を満たさない医療機関が入院料1で12.8%、入院料2で3.8%存在する一方、DPCデータでは入院料2の95.5%が医療区分2・3を6割以上受け入れていました。身体的拘束は認知症患者で25.7%、認知症のない患者でも13.6%実施され、病棟間でばらつきがありました。経腸栄養管理加算は届出910施設のうち約9割が算定実績なしで、栄養サポート体制の構築が課題です。在宅復帰機能強化加算は709施設が届出し、加算届出施設では在宅退院割合が高い傾向でしたが、加算ありでも死亡退院50%超の病棟が存在しました。
医療区分の充足状況と身体的拘束の実態
療養病棟における医療区分の充足状況は施設間で差がみられ、改善の余地があります。令和6年度診療報酬改定で中心静脈栄養の医療区分が病態と実施期間に応じて見直され、令和6年10月時点で入院料1の12.8%、入院料2の3.8%が施設基準(入院料1で医療区分2・3が8割、入院料2で5割)を満たしていませんでした。一方、DPCデータでは入院料2の95.5%が医療区分2・3を6割以上受け入れていることから、入院料2の施設基準を検討する余地があるとの意見が出されました。
医療区分2・3の疾患・状態、処置等に該当する患者割合は入院料1・2ともに増加しており、特に「医師及び看護師の常時の管理」に該当する患者が増えていました。分科会では、療養病棟の看護職員配置が20対1であることから、医療区分の高い患者を受け入れられる医療体制の検討が必要との意見がありました。また、褥瘡と肺炎を併発するなど同じ処置区分に複数該当する場合の医療資源投入量についても評価すべきとの指摘がありました。
身体的拘束の実施状況は認知症の有無で大きく異なり、課題が浮き彫りになりました。認知症のある患者では25.7%、認知症のない患者では13.6%に身体的拘束が実施されていました。病棟ごとの分析では、挿入デバイスのある認知症患者でも約3割の病棟が身体的拘束を全く実施していない一方、挿入デバイスのない認知症でない患者にも20%以上身体的拘束を実施している病棟が約2割存在しました。分科会では、デバイスや認知症以外の要素で患者像に違いがあるのか、病棟の見守り体制や夜間を含めた人員配置等まで踏まえて現状を評価し、検討を進めるべきとの意見が出されました。
経腸栄養管理と摂食嚥下機能回復の課題
療養病棟における栄養管理の現状は、中心静脈栄養への依存度が高く、経腸栄養への移行が進んでいません。医療行為・処置等の実施状況は令和4年度調査と同様の傾向で、中心静脈栄養が16.3%、胃ろう・腸ろうによる栄養管理が13.0%、経鼻経管栄養が26.7%でした。1か月に中心静脈栄養を実施した人数は11-20人の病棟が最多で半数弱を占め、中心静脈栄養を実施した患者のうち身体的拘束を行った患者の割合が高い病棟もみられました。
摂食嚥下機能回復の取組に係る診療報酬上の評価として複数の加算が設けられていますが、算定実績は低調です。中心静脈栄養を実施している患者の摂食・嚥下機能回復に必要な体制は、入院料1で約3割、入院料2で約4割が整備していました。しかし、体制を整備できていない医療機関のうち9割が今後も整備予定なしと回答し、その理由として内視鏡下嚥下機能検査または嚥下造影の実施体制確保が困難という回答が約8割に達しました。分科会では、日常的な嚥下訓練では反復唾液嚥下テストや水飲みテストのような簡易な評価法でもタイムリーに実施可能であり、全ての施設で検査体制が必要かは検討の余地があるとの意見が出されました。
経腸栄養管理加算の算定率は極めて低く、制度設計の見直しが求められています。令和6年8月から10月の3か月で経腸栄養管理加算を1回以上算定した施設は9.3%にとどまり、届出施設910のうち約9割が算定回数0回でした。届出が困難な理由として「栄養サポートチーム加算を届け出ていないため」が80%以上を占め、研修を受けた医師・看護師等の配置が難しいことが調査で示されました。分科会では、施設基準について検討を深めるべきとの意見がありました。また、認知症がないのに身体的拘束を受けながら中心静脈栄養を続けている患者の栄養管理のあり方は、さらなる議論が必要との指摘もありました。
在宅復帰に向けた取組と評価
療養病棟における在宅復帰の取組は一定の成果を上げていますが、機能の明確化が求められています。在宅への退院を評価する在宅復帰機能強化加算は令和6年8月時点で709施設が届け出ていました。加算では退院後1か月以内に患者が在宅生活を継続していることを、患者居宅への訪問または在宅医療を担当する医療機関等からの情報提供により確認することとされています。
在宅復帰機能強化加算の届出施設では在宅退院の成果が高い傾向がみられました。療養病棟における在宅への退院割合や死亡退院割合は施設ごとにばらつきがありましたが、在宅復帰機能強化加算を届け出ている施設では在宅へ退院する患者の割合が高く、死亡退院の割合は低い傾向でした。ただし、在宅へ退院する患者の割合が比較的高くても加算を届け出ていない施設が存在しました。
在宅復帰機能強化加算の要件については見直しの余地があるとの意見が出されました。加算ありでも死亡退院が50%を超える病棟があることが明らかになり、分科会では医療保険の療養病棟として望ましい姿とは言えず、加算の要件として死亡退院を含めた在宅復帰率を見ることもあり得るとの意見がありました。療養病棟は在宅医療とともに整備され、メリハリある体制となるべきであり、身体的拘束の実施状況も踏まえつつ、経腸栄養に切り替えるための工夫についても検討すべきとの指摘がありました。
障害者施設等入院基本料と特殊疾患病棟入院料の状況
障害者施設等入院基本料における患者要件の充足状況は看護配置により差がみられます。障害者施設等入院基本料の病棟における該当患者7割の基準は、7対1病棟では概ね満たされていましたが、10対1以下の病棟では7割に満たない施設が17.3%ありました。障害者施設等入院基本料・特殊疾患病棟入院料2においては重度の肢体不自由児(者)の該当割合が高く、対象疾患に該当する割合は全体で8割を超えていました。特殊疾患病棟入院料1においては難病患者等の割合が高い傾向でした。
障害者施設等入院基本料の病棟では廃用症候群が主傷病である患者の割合が多いことが明らかになりました。この背景として、レセプトやDPCにおいては元々の患者要件に係る傷病名ではなく、入院契機となった病名が記録されるため、入棟要件のいずれに該当するのかを把握することが難しいという課題があります。
まとめ
療養病棟入院基本料等の現状分析から、医療区分の充足率向上、身体的拘束の最小化、経腸栄養管理体制の整備、在宅復帰機能の強化という4つの課題が明確になりました。慢性期医療提供体制は在宅医療需要の増加に対応するため、限りある資源を活用し、地域の実情に応じた体制構築が求められています。今後の診療報酬改定では、これらの課題に対する施設基準の見直しや評価方法の改善が検討されることが期待されます。