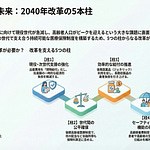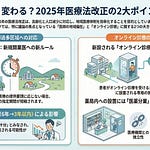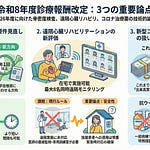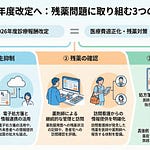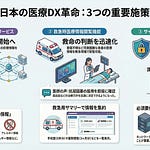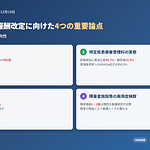令和7年11月6日に開催された第202回社会保障審議会医療保険部会では、高額療養費制度の在り方について重要な議論が行われました。高齢化の進展と医療の高度化により医療費が増大する中、制度を将来にわたって維持するための改革が求められています。医療保険部会では、高額療養費制度の在り方に関する専門委員会での議論を踏まえ、自己負担限度額の見直し、70歳以上の外来特例の在り方、所得区分の細分化という3つの論点を中心に検討を進めています。
議論の焦点は、制度の持続可能性と現役世代の保険料負担軽減の必要性、年齢によらない負担能力に応じた負担の実現、長期療養患者や低所得者への配慮というセーフティネット機能の維持という3点にあります。専門委員会では患者団体や保険者からのヒアリングを丁寧に実施し、具体的な患者の医療費負担の実態を踏まえた検討が行われました。本制度の見直しは、全世代型社会保障の構築に向けた医療保険制度改革全体の中で位置づけられており、今後の改革の方向性が注目されています。
高齢化と医療高度化により増大する医療費への対応
医療費は高齢化の進展と医療の高度化により今後も増大が見込まれます。専門委員会では、人口構造の変化や医療費の高騰という状況を踏まえると、高額療養費制度を現行のままで維持していくことは困難という認識が示されました。医療の高度化や高額薬剤の普及により高額療養費制度の重要性が増している一方で、制度を支える加入者の保険料負担も増加しています。
専門委員会での議論では、現役世代の保険料負担を軽減していくことが非常に重要という意見が出されました。この観点から、医療保険制度全体の改革を進めていくことが不可欠であり、高額療養費制度についても改革項目の一つとして一定程度の見直しを行うべきとされています。ただし、見直しに当たっては、利用者の家計の破綻につながらないよう十分配慮することが求められています。
一方で、患者団体からは切実な声も寄せられています。患者やその家族、医療者からは、自己負担限度額を上げられたらもう治療を受けられなくなるという意見が出されました。特に希少疾患患者にとって、病気の責任は自身になく必要に迫られて医療を利用しているのであり、過度な負担は公的保険制度の公平性を損なうおそれがあるという指摘もありました。
現行制度においても医療費負担が極めて厳しい状況にある患者がいる一方で、制度を将来にわたって維持する必要性も認識されています。制度を見直す際は、仮のモデルを設定した負担のイメージやデータを踏まえる必要があるという意見が出されており、丁寧な検討が求められています。具体的には、年収約200万円未満の乳がん患者の事例では、総医療費約658.2万円に対して高額療養費制度により自己負担は約44.7万円となっていますが、年間収入に占める割合は決して軽くない負担となっています。
年齢によらない負担能力に応じた負担の実現
全世代型社会保障を目指す中で、年齢ではなく負担能力に応じた負担という考え方が重要視されています。専門委員会では、70歳以上の高齢者のみに設けられている外来特例の在り方が主要な論点となりました。外来特例は、高齢者の外来受診時の自己負担限度額を引き下げる仕組みですが、世代間の公平性の観点から見直しが必要という意見が出されています。
外来特例の見直しについては、複数の視点から議論されています。医療者からは、抗がん剤治療において高齢者は外来特例により一定の負担で治療を受けられる一方で、現役世代、特に子育て世代は厳しい経済環境の中でその治療を受けることができないという公平性の問題が指摘されました。年齢階級別のデータでは、一人当たり医療費が年齢とともに増えている一方で、一人当たり自己負担額は70歳を境に大きく減っており、この点について世代間の公平性の議論が求められています。
一方で、外来特例の必要性を主張する意見もあります。一定の年齢になると疾病数が増え医療機関にかかる回数が多くなるという高齢者の特性を踏まえた仕組みは必要ではないかという指摘です。高齢者は若い世代と違って失った所得を回復させることが難しく、また病気になる確率が高いという事情があり、これらを考慮する必要があるとされています。
所得区分の在り方も重要な論点となっています。負担能力に応じたきめ細かい制度設計をしていく観点から、現行制度において大括りとなっている所得区分について、低所得者に配慮した自己負担の設定を前提としながらも細分化が必要ではないかという意見が出されました。所得区分を細分化する方向は合理的と考えられていますが、細分化しすぎたり複雑なものにしすぎると国民にも分かりにくく、市町村窓口などの現場で混乱が生じることにもなりかねないため、制度設計に当たっては留意が必要とされています。
他方で、一定の所得を有する方は応分の保険料を負担している中において、給付面の応能負担をこれ以上強めることは制度への納得性を損なうのではないかという意見もありました。負担能力という観点では、所得のみならず資産も勘案する必要があるという指摘もなされています。
セーフティネット機能を維持した制度設計の在り方
高額療養費制度はセーフティネット機能として患者にとってなくてはならない制度であり、今後もこの制度を堅持していく必要性については認識が一致しています。専門委員会では、制度を将来にわたり維持していく観点から、仮に自己負担限度額の見直しを行っていく場合であっても、特に長期にわたって継続して治療を受けられる方や所得が低い方の負担が過重なものとならないよう配慮すべきという意見が多く出されました。
長期療養患者への配慮は特に重要視されています。難病やがんなどの慢性疾患を有する方で長期間療養を必要とする方への配慮が、現行の多数回該当制度だけでは弱いのではないかという指摘がなされました。多数回該当制度は、直近12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合に4回目から自己負担限度額が引き下げられる仕組みですが、年間上限を設けてはどうかといった追加的な配慮の必要性が議論されています。
既に現行制度においてもWHOが定義する「破滅的医療支出」を大きく超えている患者が存在するという実態も示されました。今後の持続可能性の観点だけではなく、患者の過重な負担にならないという観点からは、こうした患者が既に存在していることに十分配慮しながら制度の検討を行う必要があるとされています。具体的な事例として、年収約200万円未満の20歳代女性の白血病患者では、多数回該当により自己負担は約14.5万円となっていますが、年間収入に占める割合は依然として重い負担となっています。
制度設計に当たっては、医療の質を落とさずに患者が治療を継続できることが前提となります。これまでのヒアリングや提示されたモデルも参考に、実態を踏まえて丁寧に検討することが求められています。悪性腫瘍や難病の患者のような長期療養の方々の医療へのアクセスが妨げられないような制度設計とすべきという意見が出されており、セーフティネット機能の維持と制度の持続可能性の両立が課題となっています。
現役世代においても高額療養費制度が活用されており、制度変更により家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないようにすることが重要とされています。年収約410万円の30歳代男性が超高額医薬品(薬価約3,265万円)を使用した事例では、高額療養費制度により自己負担は約40.4万円に抑えられていますが、家計調査によれば年間の税・社会保険料が約66.7万円であることを考えると、決して軽い負担ではありません。
まとめ
高額療養費制度の見直し議論は、制度の持続可能性の確保、全世代型社会保障の実現、セーフティネット機能の維持という3つの要請のバランスを取ることが求められています。医療保険部会では、高齢化の進展や医療の高度化等により増大する医療費への対応、年齢によらない負担能力に応じた負担の実現、患者の経済的負担に配慮したセーフティネット機能の在り方という3つの論点を中心に、今後さらに議論を深めていくことが必要とされています。制度改革は医療保険制度全体の中で検討されており、患者団体や保険者、医療関係者の意見を踏まえた丁寧な制度設計が期待されています。