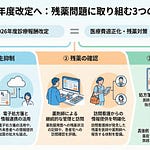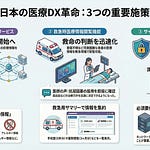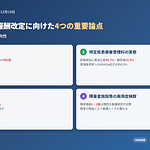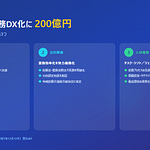令和7年11月7日に開催された中央社会保険医療協議会総会第625回では、入院時の食費・光熱水費について議論されました。令和7年4月に実施された食費基準額の引き上げを振り返るとともに、令和8年度診療報酬改定に向けた検討が行われています。食材費の高騰が続く中、医療機関が提供する食事の質を確保する観点から、1食あたり20円の引き上げが実施され、基準額は690円となりました。
入院時の食費は医療の一環として提供されるものです。令和7年4月改定により、一般所得者の患者負担は1食510円、住民税非課税世帯は240円、低所得高齢者は110円に据え置かれました。医療機関は入院時食事療養(Ⅰ)または(Ⅱ)を選択でき、(Ⅰ)を届け出た場合は特別食加算や食堂加算を算定できます。特別食加算は1食76円で腎臓食や糖尿食などの疾病治療に必要な食事に適用され、現在32.5%の算定率となっています。
入院時の食費制度の基本的な仕組み
入院時に必要な食費は国が定めた仕組みで運用されています。この仕組みは、1食あたりの総額を「食事療養基準額」として設定し、患者が負担する「標準負担額」との差額を保険給付として支給するものです。入院時食事療養費は、保険給付額が食事療養基準額から標準負担額を差し引いた金額として計算されます。
この制度は入院患者の年齢と病床の種類により区分されています。一般病床、精神病床、療養病床に入院する65歳未満の患者には入院時食事療養費が適用されます。一方、療養病床に入院する65歳以上の患者には、入院時生活療養費の食費部分として評価されます。療養病床の入院患者は食費に加えて居住費も負担することが特徴です。
入院患者に提供される食事は医療の一環として位置づけられています。各患者の病状に応じて必要な栄養量が提供され、食事の質の向上と患者サービスの改善が求められます。管理栄養士や栄養士による専門的な栄養管理のもとで、医師との連携により個別的な医学的・栄養学的管理が行われています。
令和7年4月に実施された食費基準額引き上げの内容
食材費の継続的な高騰を受けて、令和7年4月に入院時の食費基準額が1食あたり20円引き上げられました。この引き上げは、令和6年6月に実施された30円の引き上げに続くもので、医療機関が質の高い食事を提供し続けるための措置です。基準額は670円から690円へと引き上げられ、医療機関の経営安定化が図られました。
患者負担額は所得区分に応じて異なる設定となりました。一般所得者の自己負担は490円から510円へと20円引き上げられました。住民税非課税世帯の患者負担は230円から240円へと10円の引き上げにとどめられ、所得への配慮がなされました。住民税非課税世帯かつ所得が一定基準に満たない70歳以上の患者については、110円に据え置かれ、低所得高齢者への負担増加が回避されました。
保険給付額は基準額と患者負担額の差額として自動的に調整されます。一般所得者の保険給付は180円、住民税非課税世帯では450円、低所得高齢者では580円となります。この仕組みにより、所得が低い患者ほど保険給付の割合が高くなり、医療へのアクセスが確保されています。
入院時食事療養(Ⅰ)と(Ⅱ)の評価体系
入院時食事療養には(Ⅰ)と(Ⅱ)の2つの区分があります。入院時食事療養(Ⅰ)は1食690円で評価され、届出を行った医療機関が算定できます。この区分では流動食のみを提供する場合は625円となります。入院時食事療養(Ⅱ)は届出が不要で、1食556円で算定されます。流動食のみの場合は510円です。
入院時食事療養(Ⅰ)を届け出るには一定の要件を満たす必要があります。常勤の管理栄養士または栄養士が食事療養の責任者となることが求められます。医師、管理栄養士または栄養士による検食が毎食行われることも必須要件です。食事療養関係の各種帳簿の整備、病状により特別食を必要とする患者への特別食の提供、適時の食事提供、保温食器等を用いた適温の食事提供などが義務づけられています。
令和6年時点で7,761施設が入院時食事療養(Ⅰ)を届け出ています。これらの医療機関では、質の高い食事療養を提供する体制が整備されています。多くの病院がこの基準を満たすことで、入院患者に適切な栄養管理と食事サービスが提供されています。
特別食加算と食堂加算の算定要件
特別食加算は疾病治療の直接手段として提供される食事に対する評価です。この加算は1食につき76円で、1日3食を限度として算定できます。医師が発行する食事箋に基づき、腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食などの特別食が提供された場合に適用されます。令和6年の社会医療診療行為別統計では、入院時食事療養(Ⅰ)において32.5%の算定率となっています。
特別食加算が適用される食事は厚生労働大臣が定めた基準を満たす必要があります。てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食、特別な場合の検査食も対象です。単なる流動食や軟食は対象外となります。流動食のみを提供する患者には特別食加算を算定できません。
食堂加算は入院患者の食事環境を評価する加算です。一定基準を満たす食堂を備えた病棟または診療所において、入院患者に食事が提供された場合に1日につき50円を算定できます。この加算は療養病棟に入院している患者を除くすべての入院患者が対象となります。食堂の設置や食器への配慮など、食事の提供を行う環境の整備が求められています。
特別メニューの食事提供と患者負担
入院患者に提供される食事に関する多様なニーズに対応するため、特別メニューの食事を提供することができます。患者から特別の料金の支払を受ける特別メニューの食事を別に用意し、一定の要件を満たした場合に妥当な範囲内の患者負担を求めることが認められています。複数メニューの選択では、1食あたり17円を標準とした社会的に妥当な額の支払を受けることができます。
特別メニューの食事提供では患者への十分な情報提供が必須です。患者の自由な選択と同意に基づいて提供する必要があり、患者の意に反した提供は禁止されています。患者の同意がない場合は標準食を提供しなければなりません。各病棟内等の見やすい場所に特別メニューの食事のメニューおよび料金を掲示し、文書を交付してわかりやすく説明することが求められます。
特別メニューの食事は通常の入院時食事療養の費用では提供が困難な内容でなければなりません。高価な材料を使用し特別な調理を行う場合や、標準食の材料と同程度の価格でも異なる材料を用いるため別途費用がかかる場合が該当します。当該患者の療養上支障がないことについて、診療を担う保険医の確認を得る必要があります。医療機関は特別メニューの食事を提供することにより、それ以外の食事の内容および質を損なうことがないように配慮しなければなりません。
まとめ
入院時の食費制度は食材費の高騰に対応しながら、医療の質を維持し、低所得者への配慮を両立させる仕組みです。令和7年4月に実施された基準額引き上げにより、一般所得者の患者負担は1食510円、住民税非課税世帯は240円、低所得高齢者は110円に据え置かれ、所得区分に応じた負担設定となりました。医療機関は入院時食事療養(Ⅰ)を届け出ることで、特別食加算や食堂加算を算定でき、質の高い食事療養を提供する体制が評価されています。中医協では令和8年度診療報酬改定に向けて、この制度の効果検証と今後の方向性について議論が続けられています。