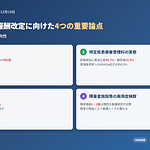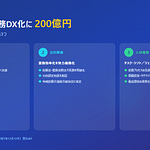令和7年7月16日に開催された中央社会保険医療協議会総会第612回では、外来診療に係る診療報酬上の評価について重要な議論が行われました。高齢化の進展と生産年齢人口の減少を背景に、外来医療提供体制の再構築が急務となっています。
今回の議論では5つの重点テーマが設定されました。初・再診料等の基本診療料の評価、令和7年4月施行のかかりつけ医機能報告制度を踏まえた評価体系、令和6年度改定で大幅に見直された生活習慣病管理の評価、特定機能病院等における外来機能分化の推進、そして情報通信機器を用いた診療の適切な推進です。本稿では、これら5つのテーマについて診療報酬上の評価の現状と今後の方向性を詳しく解説します。
初・再診料等の評価:病診機能分化を促進する基本診療料体系
初・再診料は外来診療の基本となる診療報酬であり、医療機関の機能分化を促進する重要な役割を担っています。
令和6年度現在、初診料は診療所291点、病院216点と設定されています。この評価は、診療所が地域における日常的な医療を担い、病院が専門的・入院医療を担うという機能分化を反映したものです。平成24年度改定以降、病院と診療所で異なる評価体系が維持され、外来医療における役割分担が明確化されてきました。
再診料と外来管理加算の評価体系も同様の考え方に基づいています。再診料は診療所75点、病院76点となっており、外来管理加算は73点です。外来管理加算は、処置やリハビリテーションを行わずに計画的な医学管理を行った場合に算定できる評価です。
特定機能病院や大規模病院においては、紹介割合・逆紹介割合による減算規定が設けられています。令和4年度改定では紹介受診重点医療機関が追加され、一般病床200床以上の医療機関が対象となりました。この仕組みにより、高度専門医療を担う医療機関への患者集中を防ぎ、地域の診療所との連携を促進しています。令和6年度の調査では、対象病院における紹介割合・逆紹介割合は令和5年度と比較して不変またはやや増加しており、制度が一定の効果を上げていることが確認されています。
かかりつけ医機能の評価:報告制度施行を見据えた体制整備の推進
かかりつけ医機能の評価は、地域包括ケアシステムの構築において中核的な役割を果たしています。
令和7年4月から医療法に基づく「かかりつけ医機能報告制度」が施行されます。この制度は、各医療機関が担うかかりつけ医機能の内容を都道府県に報告し、国民・患者への情報提供を強化するものです。診療報酬においても、この制度整備を踏まえた評価体系の見直しが議論されています。
現行の診療報酬では、機能強化加算と地域包括診療料・加算がかかりつけ医機能を評価する中心的な項目です。機能強化加算は初診時に80点を算定でき、地域包括診療料・加算、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料等の届出を要件としています。この加算は、服薬管理、専門医療機関への紹介、健康管理に係る相談、時間外診療に関する情報提供等を評価するものです。令和3年までは届出医療機関数が増加傾向でしたが、近年は横ばいとなっています。
地域包括診療料・加算は、複数の慢性疾患を有する患者に対して継続的かつ全人的な医療を提供することを評価します。対象疾患は高血圧症、糖尿病、脂質異常症、慢性心不全、慢性腎臓病、認知症の6疾病のうち2つ以上です。地域包括診療料1は1,660点、地域包括診療料2は1,600点で月1回算定できます。地域包括診療加算1は28点、加算2は21点で1回につき算定可能です。これらの評価には、24時間対応体制の整備、在宅医療の提供、介護保険制度との連携など、包括的な要件が設定されています。
小児かかりつけ診療料は、継続的に受診する未就学児に対して包括的な小児医療を提供する体制を評価するものです。処方箋を交付する場合の初診時652点、再診時458点など、小児の特性に配慮した評価体系が設けられています。
生活習慣病管理の評価:検査包括型と非包括型の二本立て体系
令和6年度診療報酬改定では、生活習慣病管理の評価が大幅に見直されました。
最も重要な変更は、生活習慣病管理料が生活習慣病管理料(Ⅰ)と生活習慣病管理料(Ⅱ)の二本立てとなったことです。生活習慣病管理料(Ⅰ)は検査等を包括する従来型の評価で、脂質異常症610点、高血圧症660点、糖尿病760点となっています。新設された生活習慣病管理料(Ⅱ)は検査等を包括せず333点で、医療機関が患者の状態に応じて柔軟に選択できる仕組みです。
この改定に伴い、特定疾患療養管理料の対象疾患から糖尿病、脂質異常症、高血圧が除外されました。その結果、特定疾患療養管理料の算定回数は令和4年の約2,632万回から令和6年には約1,021万回へと大幅に減少しました。一方、生活習慣病管理料の算定回数は約31万回から約1,392万回へと大幅に増加しています。算定医療機関数も、生活習慣病管理料では約3,550施設から約6万351施設へと大幅に増加しました。
主傷病名が糖尿病、高血圧症、脂質異常症である外来患者の算定状況を見ると、令和4年では外来管理加算が最も多く算定されていましたが、令和6年では生活習慣病管理料(Ⅱ)が最多となっています。この変化は、新たな評価体系が医療現場に浸透していることを示しています。
生活習慣病管理料の要件も簡素化されました。療養計画書の記載項目が整理され、令和7年から運用開始される電子カルテ情報共有サービスを活用する場合は血液検査項目の記載が不要となりました。また、月1回以上の総合的な治療管理を行う要件が廃止され、医療機関の負担軽減が図られています。一方で、多職種との連携が望ましい要件として追加され、糖尿病患者への歯科受診推奨が明確化されるなど、包括的な疾病管理の重要性が強調されています。
外来機能分化の推進:紹介・逆紹介による医療連携の強化
外来機能の分化は、医療資源の効率的配分と患者の適切な医療機関選択を実現するための重要な政策です。
病院の1日平均外来患者数は長期的に減少傾向にあります。紹介なしで外来受診した患者の割合も減少しており、令和5年は特定機能病院で34.1%、地域医療支援病院で58.5%となっています。これらのデータは、医療機関間の機能分化と連携が徐々に進展していることを示しています。
紹介割合・逆紹介割合による初診料・外来診療料の減算規定は、外来機能分化を推進する主要な仕組みです。対象となる医療機関は、特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床200床以上)、紹介受診重点医療機関(一般病床200床以上)、許可病床400床以上の病院(一般病床200床以上)です。令和6年度の調査では、これらの医療機関における紹介割合・逆紹介割合は令和5年度と比較して不変またはやや増加していました。
減算規定の対象病院における再診患者の約6割以上は2年以内に初診料の算定がない患者であり、平均して8割程度の患者が直近6か月以内に再診を受けています。外来診療料を算定した患者の主傷病名を見ると、特定機能病院では悪性腫瘍が約18%、指定難病が約4%、小児慢性特定疾病が約16%を占めています。これらのデータは、継続的な専門医療を必要とする患者が一定数存在することを示しています。
医療機関間の連携を促進する評価として、診療情報提供料(Ⅰ)、診療情報提供料(Ⅱ)、連携強化診療情報提供料が設けられています。診療情報提供料の算定回数は令和2年に低下しましたが、令和3年以降は増加しています。特に連携強化診療情報提供料は令和6年に算定回数が大きく増加しており、医療機関間の情報連携が強化されていることがうかがえます。
逆紹介を行う上での課題として、治療管理上の不安を持つ患者の理解を得ることの困難さや、複数科を受診している患者の診療科間調整の難しさが挙げられています。いわゆる「2人主治医制」など、病院の専門医師と地域のかかりつけ医師が連携しながら共同で継続的に治療管理を行う取組も一部で実施されており、今後の展開が注目されます。
情報通信機器を用いた診療の評価:オンライン診療の適切な推進
令和4年度診療報酬改定では、オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しを踏まえ、情報通信機器を用いた診療の評価が大幅に見直されました。
情報通信機器を用いた初診料は251点、再診料は73点、外来診療料は73点と設定されています。初診料の点数水準は、対面診療の初診料288点と新型コロナウイルス感染症の時限的・特例的対応の214点の中間程度に設定されました。この水準設定は、オンライン診療では触診・打診・聴診等が実施できない一方で、オンライン診療のみで診療を終え得ることや、国民にオンラインでも適切に診療を届けていくことの重要性を勘案したものです。
情報通信機器を用いた診療の届出医療機関数は増加傾向にあり、初・再診料等の算定回数も令和5年4月以降増加しています。令和5年における情報通信機器を用いた初診料等の算定回数は初・再診料等全体の0.063%を占めています。年齢階級別では、対面診療と比較して若年者の算定割合が高く、再診料・外来診療料では年齢構成に地域差が見られます。
オンライン診療の算定要件では、オンライン診療の適切な実施に関する指針に沿った診療の実施が求められています。保険医療機関においては対面診療を提供できる体制を有すること、患者の状況によって対応が困難な場合には他の医療機関と連携して対応できる体制を有することが要件となっています。医療機関と患者との間の時間・距離要件や、オンライン診療の実施割合の上限については要件として設定されていません。
遠隔連携診療料(D to P with D)は令和2年度に新設されましたが、算定回数は限られています。過去1年間にD to P with Dによるオンライン診療を実施した医療機関は1.0%にとどまっています。しかし、医療的ケア児に対する診療や訪問診療における眼科・皮膚科・耳鼻科等の専門医との連携など、遠隔連携診療料を算定できる状況以外でも連携事例が見られます。
令和6年度診療報酬改定では看護師等遠隔診療補助加算(D to P with N)が新設されました。届出医療機関数は令和7年4月1日時点で78施設、研修受講者は合計約4,000名程度となっています。規制改革実行計画では、D to P with Nにおける診療報酬の算定方法に不明確な部分があるとの指摘があり、今後の明確化が期待されています。
まとめ:外来医療提供体制の再構築に向けて
中医協総会第612回で議論された外来診療に係る診療報酬上の評価は、今後の外来医療提供体制の方向性を示す重要な内容でした。初・再診料等による医療機関の機能分化、かかりつけ医機能報告制度を踏まえた評価体系の整備、生活習慣病管理の効率化と充実、特定機能病院等における外来機能分化の推進、オンライン診療の適切な推進という5つのテーマは、いずれも高齢化の進展と生産年齢人口の減少という社会構造の変化に対応するための重要な施策です。令和6年度診療報酬改定の影響を検証しつつ、次期改定に向けた継続的な議論が求められています。