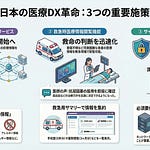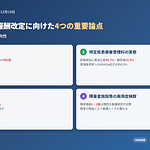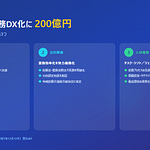令和7年11月7日に開催された中央社会保険医療協議会総会第625回において、情報通信機器を用いた診療についての議論が行われました。本議論では、オンライン診療の適正な推進と評価拡大を目的として、3つの診療形態における現状課題と今後の方向性が示されました。
今回の議論の要点は、第一にD to P(医師対患者)における適正推進のための評価のあり方、第二にD to P with D(患者が医師といる場合)の対象拡大と評価見直し、第三にD to P with N(患者が看護師等といる場合)の評価明確化、第四に外来栄養食事指導料等の個別事項についての制度改善です。
D to P:オンライン診療の適正推進に向けた課題と対応
D to Pは医師と患者が情報通信機器を用いて直接診療を行う形態です。この形態では、患者側に医療従事者が同席せず、医師が初診料・再診料・外来診療料、各種医学管理料を算定できます。
情報通信機器を用いた診療に係る報告書によると、「自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合」として他の医療機関へ紹介を実施した割合は、患者の所在が医療機関と同一の場合で0.49%、患者の所在が医療機関と異なる場合で0.59%でした。この結果から、緊急時や対応困難な症例における他医療機関との連携体制に課題があることが明らかになりました。具体的には、事前合意なく患者に他医療機関への受診を指示していた事例や、医師が国外から診療を実施した事例が報告されています。
オンライン診療の適切な実施に関する指針や医療広告ガイドラインを遵守していない事例も確認されました。これらの課題を踏まえ、中医協では直接の対面診療を行える体制の整備状況について、施設基準の更なる明確化を検討する方針が示されました。
D to P with D:遠隔連携診療の対象拡大と評価見直し
D to P with Dは患者が医師といる場合にオンライン診療を行う形態です。現在の診療報酬では、遠隔連携診療料として、難病患者及びてんかん患者に対する専門医との連携が評価されています。
遠隔連携診療料は令和2年度に新設されて以降、算定回数は限られています。令和6年度入院・外来医療等における実態調査によると、過去1年間にD to P with Dによるオンライン診療を実施した医療機関は1.0%(3,546施設中37施設)でした。遠隔連携診療料を算定できる状況以外でも、医療的ケア児との連携が26.9%、訪問診療における眼科・皮膚科・耳鼻科等の専門医との連携が15.4%の施設で実施されていました。
D to P with D型やD to D型の遠隔医療については、緊急性が高い状況や専門の医師による対面診療が困難な状況下において、有用性が高いことが考えられます。オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針における遠隔医療に期待される役割を踏まえ、中医協ではD to P with D型及びD to D型の遠隔医療の診療報酬上の評価を一定の考え方を踏まえて検討する方針が示されました。
皮膚科領域における活用事例として、日本臨床皮膚科医会及び日本看護協会が実施した調査結果が示されました。この調査では、訪問看護を利用する566名の在宅療養者のうち399名(70.5%)が何らかの皮膚疾患を有していました。そのうち114名(28.1%)が未治療であり、理由として「近くに往診する皮膚科医がいない」「皮膚科は往診しないと思っていた」等が挙げられています。このような地域における皮膚科医療へのニーズに対応するため、オンライン診療の活用により皮膚科の専門的医療へのアクセスを改善することが有益であると考えられます。
D to P with N:看護師等遠隔診療補助の評価明確化
D to P with Nは患者が看護師等といる場合にオンライン診療を行う形態です。令和6年度診療報酬改定では、へき地診療所及びへき地医療拠点病院において、適切な研修を修了した医師がD to P with Nを実施できる体制を確保している場合の評価として、看護師等遠隔診療補助加算(50点)が新設されました。
規制改革実行計画(令和7年6月13日閣議決定)において、D to P with Nにおける診療報酬の算定方法に不明確な部分があるとの指摘がありました。D to P with Nとして想定される診療形態には、看護師等の所属や定期的な訪問の有無等の違いがあります。訪問看護については介護保険との整理に留意が必要です。
令和7年度厚生労働科学特別研究事業の調査によると、D to P with Nで実際に実施している診療の補助行為として、検査では採血、咽頭拭い液を用いた検査、尿検査、心電図等が挙げられました。処置・注射としては点滴注射、創傷処置、皮膚科軟膏処置等が挙げられました。中医協では、看護師等の所属や定期的な訪問時に行われるか等の看護の提供形態の違いを踏まえて、看護師の訪問に係る評価を明確化する方針が示されました。
個別事項:外来栄養食事指導料の評価明確化
外来栄養食事指導料については、令和2年度から初回の情報通信機器等の活用が評価され、令和4年度からは2回目以降も算定可能となっています。しかし、算定回数は極めて少なく、規制改革実施計画において、オンライン診療の特性を十分に活かした活用が進まない算定要件となっていると指摘されています。
外来栄養食事指導料は、管理栄養士が医師の指示に基づき、初回は概ね30分以上、2回目以降は概ね20分以上の栄養指導を行った場合に算定できます。情報通信機器等を用いる場合の要件として、事前に対面による指導と情報通信機器等による指導を組み合わせた指導計画を作成することが求められています。
中医協では、情報通信機器を活用した外来栄養食事指導料の推進の観点から、オンラインのみでの実施も可能であることの明確化や、電話と情報通信機器を同様としている取扱いについて検討する方針が示されました。この見直しにより、栄養指導におけるオンライン診療の活用が進むことが期待されます。
まとめ:遠隔医療の推進に向けた評価見直しの方向性
中医協第625回総会では、情報通信機器を用いた診療について、D to P、D to P with D、D to P with Nの3つの診療形態と個別事項における現状課題と今後の方向性が議論されました。今後の診療報酬改定では、オンライン診療の適正推進と評価拡大により、地域医療における専門医へのアクセス改善や、へき地医療における医療提供体制の充実が期待されます。