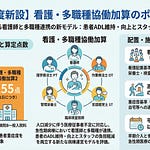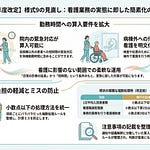令和7年11月6日に開催された第202回社会保障審議会医療保険部会において、薬剤給付の在り方に関する重要な議論が行われました。医療保険制度の持続可能性を確保するため、長期収載品の選定療養の更なる活用、先行バイオ医薬品の保険給付の在り方、OTC類似薬の保険給付範囲の見直しという3つの重要なテーマが検討されています。
今回の議論では、令和6年10月から施行された長期収載品の選定療養制度の効果検証が示されました。後発医薬品の使用割合は数量ベースで90%以上に上昇し、一定の効果が確認されています。この成果を踏まえ、患者負担額の引き上げや対象範囲の拡大が論点となりました。先行バイオ医薬品については、バイオ後続品への置き換え率が金額ベースで33.7%と低いことから、使用促進に向けた選定療養の導入が検討されています。OTC類似薬については、医療機関における必要な受診の確保、子どもや慢性疾患を抱える方への配慮、低所得者の負担増加への対応という3つの重要な配慮事項が示されました。
長期収載品の選定療養制度の効果と今後の方向性
長期収載品の選定療養制度は、令和6年10月に施行されました。この制度は、患者が後発医薬品ではなく長期収載品を希望する場合に、両者の価格差の4分の1を患者が追加負担する仕組みです。施行後約5ヶ月が経過した令和7年3月時点で、後発医薬品の使用割合は数量ベースで90.6%に達しており、後発医薬品の使用促進に一定の効果を示しています。
制度の運用状況を見ると、長期収載品の銘柄名で処方された医薬品のうち73.6%が後発医薬品へ変更されています。残りの25.4%で長期収載品が調剤された理由は、医療上の必要性による変更不可が23.3%、患者希望が17.8%、後発医薬品の在庫不足が43.9%でした。この結果から、供給不安が依然として医療現場の課題となっていることがわかります。
一方で、薬局からは患者への説明負担が大きいという指摘があります。長期収載品の選定療養制度導入による影響を尋ねた調査では、78.9%の薬局が患者への説明や質問対応に係る負担が大きいと回答しました。制度そのものや特別料金の計算がわかりづらいという意見も寄せられており、現場への配慮が求められます。
医療保険部会では、後発医薬品使用促進をさらに進めるため、選定療養の更なる活用が議論されました。具体的には、現在の価格差4分の1という患者負担を、2分の1、4分の3、全額へと段階的に引き上げる案が示されています。複数の委員から価格差全額を患者負担とすべきという意見が出された一方、後発医薬品の供給不安定が解消されていない現状への配慮を求める意見もありました。
先行バイオ医薬品への選定療養導入に向けた課題
先行バイオ医薬品のバイオ後続品への置き換えは、低分子医薬品の後発医薬品への置き換えと比較して大幅に遅れています。令和6年の薬価調査によると、バイオ後続品への置き換え率は金額ベースで33.7%にとどまります。政府目標では、2029年度までにバイオ後続品が80%以上を占める成分数を全体の60%以上とすることを掲げていますが、現状では22.2%と大きく乖離しています。
バイオ医薬品が後発医薬品と異なる特性を持つことが、置き換えの障壁となっています。バイオ医薬品は製造工程が複雑で、細胞株由来のばらつきが生じる可能性があります。先行品と後続品は同質・同等性が確認されていますが、完全な同一性は認められていません。このため、低分子医薬品のように処方変更や変更調剤で対応することが困難です。
さらに、バイオ医薬品には先行品と後続品に共通の一般名が存在せず、一般名処方加算の仕組みが適用できません。後発医薬品調剤体制加算に相当する評価も存在しないため、医療機関や薬局がバイオ後続品を積極的に使用するインセンティブが限られています。保存や運搬にも特別な配慮が必要で、安定供給の確保が課題です。
医療保険部会では、バイオ後続品への置き換えが一定程度進んでいる先行バイオ医薬品について選定療養の対象とすべきという意見が複数示されました。高額療養費制度の持続可能性確保の観点からも検討が必要という指摘があります。ただし、急性期で一時的に使用する薬と、自己注射のように患者が継続使用する薬では対応が異なるため、デバイスの使用方法の違いなども考慮した丁寧な制度設計が求められます。
OTC類似薬の保険給付見直しにおける3つの配慮事項
OTC類似薬の保険給付の在り方見直しは、骨太方針2025および三党合意で示された重要課題です。医療保険制度の持続可能性確保と現役世代の保険料負担軽減を実現するため、令和7年末までに十分な検討を行い、令和8年度からの実施を目指しています。検討に当たっては、医療機関における必要な受診の確保、子どもや慢性疾患を抱える方・低所得者の患者負担への配慮、成分や用量がOTC医薬品と同等のOTC類似薬の扱いという3つの視点が示されました。
医療機関における必要な受診の確保については、複数の懸念が指摘されています。OTC類似薬を保険適用から外した場合、受診遅延による健康被害が生じる可能性があります。医療の基本は早期発見・早期治療であり、軽症段階での対応を困難にすれば、結果として重症化により多額の医療費を要することになりかねません。薬の過剰摂取や飲み合わせリスクも考慮が必要です。
へき地では医療機関にアクセスできても薬局がない地域があり、OTC医薬品の入手自体が困難な場合があります。スイッチOTC化された医薬品についても、単に保険給付の対象から外すだけではセルフメディケーションの適切な実施は難しく、かかりつけ医やかかりつけ薬剤師と相談しながら薬歴管理を行う体制が望ましいという意見が出されました。
子どもや慢性疾患を抱える方、低所得者への配慮も重要な論点です。過度な負担や急激な変化が生じないよう十分な配慮が必要です。難病や心身障害のある方にとっては、一般用医薬品が医療用医薬品の10倍以上の価格になることもあり、負担が非常に重くなる可能性があります。医療保険部会では、こうした方々への配慮が必須という認識が共有されました。
OTC医薬品と医療用医薬品の違いにも留意が必要です。有効成分が一致していても、用法・用量、効能・効果、対象年齢、投与経路・剤形などに違いがあります。配合剤で包装単位が決まっている大多数のOTC医薬品は、医療用医薬品のように患者個々の量に対応して提供できません。OTC医薬品の安定供給も十分ではなく、全薬局で一律な対応ができない状況も指摘されています。
まとめ:医療保険制度の持続可能性確保に向けた取組の方向性
薬剤給付の在り方見直しは、医療保険制度の持続可能性確保と現役世代の負担軽減という重要な政策目標を実現するための取組です。長期収載品については選定療養制度が一定の効果を示しており、更なる活用が検討されています。先行バイオ医薬品についてはバイオ後続品への置き換えを促進するための環境整備が課題です。OTC類似薬については、必要な受診の確保と患者への配慮を前提とした慎重な検討が求められます。いずれの課題についても、医療の質の維持とアクセスの確保を図りながら、効率的で持続可能な制度設計を進めることが重要です。