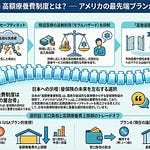福井商工会議所デジタル活用ビジネス支援センターは、2025年6月24日(火)に「生成AIとAPI連携で創る業務効率化ワークショップ」の第1回を開催しました。本ワークショップは、生成AIを活用して自ら業務課題を解決するデジタルツールを制作する全5回シリーズです。初回講義では、会話型AI構築プラットフォーム「miibo」を中心に、ChatGPTの基礎から応用まで体系的に学習し、参加者全員がオリジナルのLINE Bot開発に成功しました。
本記事では、プロトタイピング専門家による実践的な指導のもと、4時間という短時間で達成された成果をご報告します。参加者は、miiboを使った会話型AIの構築、ナレッジデータストアによる精度向上、LINEとのAPI連携、そしてGPTsの作成まで、幅広い技術を習得しました。「AIをぐっと身近に感じられるようになった」という参加者の声が示すように、実践を通じて生成AIの可能性を体感する機会となりました。今後のシリーズを通じて、各参加者が業務課題に即したオリジナルツールを開発し、地域のDX推進に貢献することが期待されます。
プロトタイピング専門家による充実した指導体制
第1回ワークショップの講師陣は、プロトタイピング教育の第一人者として活躍する2名の専門家が担当しました。メイン講師を務めたdotstudio株式会社代表取締役・菅原のびすけ氏は、プロトタイピング専門スクール「プロトタイピングスクール」のプロデューサーとして、実践的な技術教育を推進しています。日本最大級のIoTコミュニティ「IoTLT」の主催者でもあり、デジタルハリウッド大学大学院の非常勤講師として、次世代の技術者育成にも尽力しています。
サブ講師のプロトアウトスタジオ講師・りゆ氏は、幼稚園教諭の経験を活かした実践的なアプローチが特徴です。保育現場で役立つアプリを多数開発し、位置情報を使った待ち合わせ専用人形「ときメーター」のクラウドファンディングでは多くの支援を獲得しました。両講師ともに、技術の実用化と社会実装を重視する姿勢が、今回のワークショップの成功につながりました。
講師陣の専門性は、Microsoft MVP Visual Studio and Development Technologiesの受賞や、世界で22名の第1期LINE API Expertsの認定など、国際的にも評価されています。このような高度な専門性と実践経験を持つ講師陣による指導により、参加者は理論と実践をバランスよく習得することができました。
miiboを活用した会話型AI開発の実践演習
ワークショップの前半では、ChatGPTの基本的な仕組みと活用方法から学習を開始しました。LLM(大規模言語モデル)の特性を理解した上で、実際の業務への応用可能性を検討する時間が設けられました。参加者は、自社の業務課題を振り返りながら、生成AIをどのように活用できるかを具体的にイメージすることができました。
実践演習の中心となったのは、会話型AI構築プラットフォーム「miibo」を使用した開発体験です。参加者は、福井の観光情報をテーマにした会話型AIの構築に取り組みました。エージェントの作成、プロンプトの設定、会話コンテンツの登録まで、miiboの直感的なインターフェースにより、プログラミング経験がない参加者でもスムーズに進めることができました。特に「AIにプロンプトを考えてもらう」機能を活用することで、効果的なプロンプト設計を体験的に学びました。
演習では、単なる会話型AIの作成にとどまらず、実用性を高めるための様々な機能を実装しました。クイックリプライの設定により、ユーザーが次に話しかけたくなる選択肢を提示する方法を学びました。また、福井の方言を使った応答など、地域性を活かしたカスタマイズも行い、より親しみやすい会話型AIの構築を実現しました。
RAG技術による回答精度の向上
ワークショップの重要な学習項目の一つが、RAG(Retrieval-augmented Generation)技術の活用でした。生成AIの課題であるハルシネーション(事実と異なる情報の生成)を防ぎ、正確な情報提供を実現するため、miiboのナレッジデータストア機能を活用しました。参加者は、福井商工会議所のホームページをデータソースとして登録し、実際の情報に基づいた応答を生成する仕組みを構築しました。
ナレッジデータストアへのデータ登録は、URLを指定するだけで簡単に実現できました。登録されたデータは自動的にEmbedding(ベクトル化)され、AIが効率的に検索・参照できる形式に変換されます。参加者は、この仕組みにより、特定の領域に強い専門知識を持った会話型AIを構築できることを実感しました。
実際の動作確認では、福井商工会議所に関する質問に対して、ホームページの情報を正確に引用した回答が生成されることを確認しました。この体験を通じて、参加者は自社の業務マニュアルやFAQ、製品情報などを活用した実用的な会話型AIの構築可能性を理解することができました。
LINE連携とGPTsによる応用展開
ワークショップの後半では、作成した会話型AIをLINEと連携させる実習を行いました。LINE Developersの設定から、miiboとのWebhook連携まで、実際の手順を一つずつ確認しながら進めました。参加者全員が、自分のスマートフォンで作成したLINE Botと会話できるようになり、開発の成果を即座に体験することができました。
さらに、OpenAIのGPTs機能についても学習しました。GPT Storeから既存のGPTsを探して使用する体験から始まり、ナレッジファイルを活用したオリジナルGPTsの作成まで実践しました。「福井のクマ情報GPT」を題材に、PDFファイルをそのままアップロードして専門的な情報を提供するGPTsを構築する過程で、データ加工なしに既存資料を活用できる利便性を体感しました。
GPT mentions機能を使った複数GPTsの連携も体験しました。福井観光情報GPTから取得した情報を基に、DALL-Eで画像を生成するという連携により、異なるAI機能を組み合わせた高度な活用方法を学びました。これらの体験を通じて、参加者は生成AI技術の可能性と実用性を深く理解することができました。
今後の展開とコミュニティ形成
第1回の成功を受けて、今後は全5回のシリーズを通じて、より実践的なスキルの習得を目指します。第2回(7月11日)では「Google Apps Scriptの活用」、第3回(7月22日)では「GASとChatGPTを活用したスクレイピング」、第4回(8月8日)では「プロトタイプの制作と共有」、そして最終回(8月25日)では「成果報告会」を予定しています。
特筆すべきは、参加者によるオンラインコミュニティの形成です。LINEオープンチャットやMetaLifeを活用した継続的な情報共有の場が設けられ、ワークショップ期間中だけでなく、終了後も相互学習を続ける環境が整備されました。参加者同士が制作物を共有し、フィードバックを交換することで、より実践的なスキル向上が期待されます。
福井商工会議所は、このような実践的な学習機会を通じて、地域企業のデジタル化推進を支援していきます。参加者それぞれが、学んだ技術を活用して業務課題に即したソリューションを開発し、実装することで、地域全体のDX推進につながることを期待しています。生成AIとAPI連携の技術は、今後ますます重要性を増していくことが予想され、今回のワークショップがその第一歩となることでしょう。
まとめ
第1回「生成AIとAPI連携で創る業務効率化ワークショップ」は、miiboを活用した実践的な演習により、参加者全員がオリジナルのLINE Bot開発に成功するという大きな成果を上げました。プロトタイピングの専門家による体系的な指導のもと、ChatGPTの基礎からRAG技術、API連携、GPTsの活用まで、幅広い技術を4時間で習得することができました。今後のシリーズを通じて、参加者が自社の業務課題を解決するオリジナルツールを開発し、地域のDX推進に貢献することが期待されます。