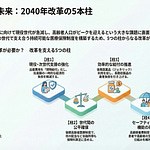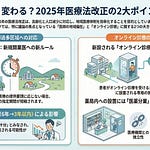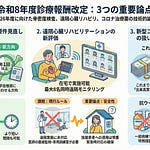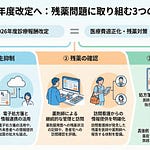京都芸術大学が会話型AI構築プラットフォーム「miibo」を活用して開発した学習特化AI「Neighbuddy(ネイバディ)」が、教育現場で大きな成果を上げています。2024年秋からのパイロット導入で、85.9%の学生が継続利用を希望するという驚異的な結果を達成しました。
このプロジェクトは、学生の「わからないことを聞けない」「学習が続かない」という課題に対し、miiboの会話型AI技術を活用して解決を図った画期的な事例です。授業ノートと連携し、個々の学生に最適化された学習支援を提供するNeighbuddyは、教育分野におけるmiiboの新たな可能性を示しています。本記事では、その開発背景と成果、そして教育現場での実際の声をご紹介します。
Neighbuddyが実現する個別最適化された学習体験
京都芸術大学デジタルキャンパス局(DCB)が開発したNeighbuddyは、単なる質問応答システムではありません。学生が書いた授業ノートや対話履歴をもとに、復習から探究、自己整理までを支援する"学びの相棒"として機能します。
このAIの最大の特徴は、学生一人ひとりの学習プロセスに寄り添う点にあります。雑談を糸口に学びを深めたり広げたりするきっかけを提供し、怠りがちな復習についても振り返りやクイズなど自然な流れでモチベーションを維持します。Active Recall、Spaced Learning、Metacognitionなど学習科学に基づく設計により、自己調整学習を促進する仕組みが組み込まれています。
特筆すべきは、「質問する」「話しかけてみる」といった初期行動の心理的ハードルを下げる工夫です。これにより、従来の学習支援ツールでは難しかった、学生の自発的な学習への取り組みを促すことに成功しています。
現場から寄せられる高い評価と具体的な成果
パイロット導入の成果は数字に明確に表れています。継続利用希望率85.9%という高い数値に加え、「使えなくなると困る」と回答した学生が56.2%に上ることは、Neighbuddyが学生の学習に欠かせない存在になりつつあることを示しています。
学生からは「ラフに話しかけられるため、"とりあえず聞くか"みたいな活用方法ができる」「他のAIと比べて寄り添ってくれる感が強い」「話した内容を整理してくれるので、自分の考えを客観視できた」といった声が寄せられています。これらのコメントは、Neighbuddyが技術的な優位性だけでなく、学生の心理的なニーズにも応えていることを物語っています。
教員の視点からも高い評価を得ています。吉田大作准教授は、「学生自身の関心や疑問をバディとの対話の中で学習を深めていく様子が見られた」と述べ、さらに「これまで定量化することが容易ではなかった授業外の事前・事後学習が、バディとの対話記録等を用いて可視化され、学習プロセスを評価できるようになったことは、教育界にとっても大きなインパクト」と、教育評価の新たな可能性にも言及しています。
miiboが切り拓く教育分野での会話型AIの可能性
京都芸術大学のNeighbuddyプロジェクトは、miiboを活用した会話型AIが教育分野でも大きな価値を創出できることを実証しました。創造性とテクノロジーが出会うことで、学びは"孤独"から"対話"へと変化し、より豊かな学習体験が生まれています。
現在約100名の協力学生と検証を継続中のこのプロジェクトは、今後さらに教育機関・教員・研究者との連携を深めながら発展していく予定です。miiboの会話型AI技術が、教育の個別最適化という大きな課題に対する有効なソリューションとなることが期待されます。
まとめ
京都芸術大学の学習特化AI「Neighbuddy」の成功は、miiboが教育分野においても強力なツールとなることを証明しました。85.9%という高い継続利用希望率は、適切に設計された会話型AIが学生の学習体験を大きく向上させる可能性を示しています。カスタマーサポートや社内ヘルプデスクだけでなく、教育という新たな領域でもmiiboの技術が活用され、社会に価値を提供していることは、会話型AIの可能性の広がりを感じさせます。
京都芸術大学の取り組み:企画×デザイン×テクノロジーで未来をつくる|京都芸術大学クロステックデザインコース(https://miibo.site/crosstech-design-kyoto-art-university/)