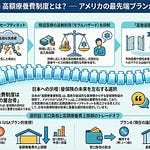令和7年11月13日に開催された第203回社会保障審議会医療保険部会において、医療機関の業務効率化・職場環境改善の推進に関する論点が議論されました。2040年に向けて高齢者人口がピークを迎える一方、15歳~64歳人口が減少する中、医療従事者の確保はますます困難となることが見込まれます。厚生労働省は2019年に「医療・福祉サービス改革プラン」をとりまとめており、2040年時点で単位時間当たりのサービス提供を5%(医師は7%)以上改善することとしています。この状況を踏まえ、医療界全体での実効ある取組を進めるための制度的枠組みが検討されています。
本稿では、業務のDX化推進、タスク・シフト/シェアの推進、医療従事者の養成体制確保、環境整備という4つの論点について、現状認識、具体的な取組、今後の方向性を説明します。DX化については、省力化投資促進プランに基づく先進的医療機関の事例と支援策の必要性を示します。タスク・シフト/シェアについては、看護師の特定行為研修制度とオンライン診療の活用を取り上げます。養成体制については、遠隔授業やサテライト化の活用を紹介します。環境整備については、医師の時間外労働削減目標と看護職員の超過勤務時間削減目標に基づく賃上げの実施と多様な働き方の推進を述べます。
業務のDX化推進:省力化投資促進プランに基づく取組
業務のDX化については、2025年6月に策定された「省力化投資促進プラン(医療分野)」に基づき、医療界全体での取組が求められています。現状では、物価や賃金の上昇等の影響で投資を行う余力がない医療機関がある一方、先進的な医療機関が成果を上げています。先進的医療機関では、ICT機器の導入や生成AIサービスの活用によって、文書や記録作成等の業務を効率化し、超過勤務時間の減少や職場満足度の向上といった結果につなげています。
省力化投資促進プランでは、看護業務の効率化に資する機器等の導入支援、医師の労働時間短縮に資する機器等の導入支援、医療DXの推進のための情報基盤の整備を多面的な促進策として掲げています。目標として、省力化機器を導入している医療機関数の増加、AMED事業による医療機器等の研究開発支援における採択課題数の増加、電子カルテ情報共有サービスの普及が設定されています。サポート体制の整備として、省力化投資を通じた看護業務効率化のためのサポート体制、看護師養成におけるDX促進のための支援、省力化投資を通じた勤務環境改善のためのサポート体制が用意されています。
先進的医療機関の取組をさらに加速化させるとともに、業務効率化に取り組む医療機関の裾野を広げるために、支援や制度的枠組みの整備が必要です。医療部会では、業務効率化を実現した場合の人員配置基準の緩和を検討すべきとの指摘がありました。人員配置基準が医療従事者確保の足かせになっているならば、見直しや緩和を検討すべきとの意見が示されています。医療機関が適正な価格でICT機器等を導入できるような環境整備も重要であり、医療機関の経営を圧迫することなく、現場で使いこなしていけるように、国や自治体による支援体制のさらなる構築が求められています。
タスク・シフト/シェアと人材確保:時間外労働削減の数値目標
タスク・シフト/シェアについては、医師の働き方改革に関する具体的な数値目標が設定されています。2024年4月から医師の時間外労働に関する上限規制が施行されており、地域医療確保暫定特例水準適用医師の時間外労働の目標時間数は、現状の上限1,860時間から2029年度までに上限1,410時間へと削減することが目標とされています。看護職員の月平均超過勤務時間については、現状5.1時間から2029年度までに2027年度比で月平均超過勤務時間の減少を目指すこととされています。
看護師の特定行為研修制度については、本年9月に「看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ」が設置され、見直しに向けた議論が開始されました。特定行為研修を修了した看護師の活躍促進に向けて、どのような取組が必要かが検討されています。医師の働き方改革の推進に伴い、タスク・シフト/シェアの取組を進めてきていますが、これまでの取組の定着化が必要です。医療職一人一人が専門性を十分に発揮できるよう、タスク・シフト/シェアやチーム医療に加えて、多職種連携も促進する必要があります。
医療の質や安全の確保を前提に、医療従事者の業務効率化という観点から、オンライン診療などを適切に普及・推進することも重要です。いわゆる「D to P with N」等によるオンライン診療を推進するためにどのような対応が考えられるかが議論されています。医療従事者でなければできない患者への直接的なケアやコミュニケーションに時間を割くためにも、AIやICTの活用、DXを積極的に進めるべきとの意見が示されています。限られた人材で安全かつ効率的な医療を提供するためには、タスク・シフト/シェア、ICTの活用、多職種連携等が不可欠です。
医療従事者の養成体制確保:地域の実情に応じた環境整備
地域における医療従事者の養成体制の確保については、養成校の定員充足率の低下傾向と18歳以下人口の減少が課題です。多くの医療関係職種の養成校の定員充足率は低下傾向にあり、今後、地域によっては18歳以下人口の減少が急激に進むところもあります。医療関係職を目指す若者が地域において必要な教育を受けられる体制を安定的に確保することが必要です。
養成体制の安定的確保のために、多様な学び手のニーズを踏まえた学習環境の整備が求められています。養成校における遠隔授業の活用、地域や養成校の実情に応じたサテライト化の活用など、柔軟な対応が必要です。実際に、沖縄県名護市の北部看護学校では、学校設置者変更により2026年4月に公立大学法人名桜大学附属北部看護学校として公立化される予定であり、学費の負担軽減、教育環境の充実、地域への貢献などが期待されています。
医療従事者の需給の状況を見通しつつ、都道府県等が養成体制の確保のために講ずることが考えられる施策のメニューを整理していくことも重要です。地域の実情に応じた多様な施策を用意することで、医療従事者の安定的な供給を図ることができます。看護師養成におけるDX促進のための支援など、時代に即した取組も進められており、省力化投資促進プランのサポート体制の一環として位置づけられています。
環境整備と支援体制:賃上げと多様な働き方の推進
医療従事者の確保に資する環境整備については、賃上げの継続実施と多様な働き方の推進が重要です。15~64歳人口の減少が急激に進む地域では、医療機関等における医療従事者の確保が難しくなるほか、医療から他産業への人材流出が進んでいるとの指摘があります。2017年から2019年当時と比べ、医療従事者の不足状況は悪化しているとともに、新型コロナウイルス感染症等による医療需要の動向の変化や、物価や賃金の上昇など、医療機関をとりまく状況はさらに変わってきています。現在の医療従事者が医療の現場に定着し、今後も就業者が安定的に医療分野に参入する環境の整備が必要です。
他産業と遜色ない賃上げを継続的に実施できるようにするとともに、医療水準を維持しつつ、より少ない人員でも必要な医療が提供できる環境整備を進める必要があります。省力化に伴う生産性の向上を、賃金の増加に的確に結びつけていくことも重要です。働き方改革については、時間外労働の上限規制だけでなく、多様な働き方の選択肢を導入して、担い手を増やす取組を進めていくべきとの意見が示されています。
医療勤務環境改善支援センターによる支援体制の活用も重要です。医療勤務環境改善支援センターは、医療従事者の勤務環境改善を促進するための拠点として、各都道府県が設置しています。医療労務管理アドバイザーや医業経営アドバイザーが配置され、医療機関からの相談に応じて、勤務環境改善や医師の働き方改革の取組を支援しています。医療機関に対するアンケート調査の実施、多職種による意見交換会の実施、タスク・シフト/シェアやICTの導入等に関する助言など、多様な支援が提供されています。医師に関する適切な労務管理に関する助言、副業・兼業、研鑽、宿日直許可取得後の適切な労務管理等の支援も行われています。
まとめ
第203回社会保障審議会医療保険部会では、医療機関の業務効率化・職場環境改善の推進に関する4つの論点が議論されました。業務のDX化については、2025年6月に策定された省力化投資促進プランに基づき、先進的医療機関の取組を医療界全体に広げるための支援や制度的枠組みが必要です。タスク・シフト/シェアについては、2024年4月から施行された医師の時間外労働上限規制に基づき、地域医療確保暫定特例水準適用医師の時間外労働を現状1,860時間から2029年度までに1,410時間へ削減すること、看護職員の月平均超過勤務時間を現状5.1時間から2029年度までに削減することが目標とされています。医療従事者の養成体制については、遠隔授業やサテライト化の活用など、多様な学び手のニーズを踏まえた環境整備が求められています。環境整備については、賃上げの継続実施と多様な働き方の推進、医療勤務環境改善支援センターの活用が重要とされています。