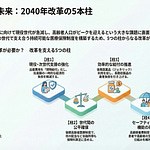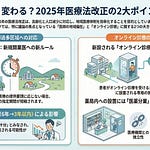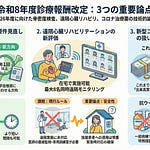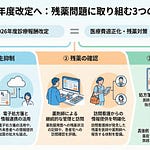「大学1年生の半数以上が、一度もAIを使ったことがない」という驚きの現実が、鹿児島大学の坂井美日准教授を行動に駆り立てました。教育現場では、AI技術を使わずに警戒するという課題が存在していたのです。本記事では、プログラミング知識のない文系教員がmiiboを活用して教育現場の課題解決に取り組んだ事例を紹介し、教育現場におけるAIの新たな可能性を示します。
鹿児島大学総合教育機構共通教育センターの坂井准教授は、コーディング経験なしでmiibo(ミーボ)を活用し、教育現場の課題解決に成功しています。坂井准教授は対話型クイズボットを開発し、学生の論理力向上を楽しく支援する環境を構築しました。また、レポート添削支援ボットを作成することで、3クラス90人分の添削業務の効率化を実現しています。さらに、AIとの会話に特定のキーワードを組み込むなどの工夫により、学生のAI適切活用を促進しています。
教育現場におけるAI活用の現状と課題
教育現場では、AIへの不理解と警戒感から活用が進んでいない現状があります。坂井准教授によると、「大学1年生の半数以上がAIを使ったことがない」という驚きの事実が明らかになりました。学生たちは「すごい」という漠然としたイメージと「怖い」という不安を抱え、新しい技術に踏み出せないでいたのです。
教員側にも同様の課題が存在していました。「警戒している先生が多いというより、使ったことすらない先生がいっぱいいるかもしれない」と坂井准教授は指摘します。AI技術を理解せずに警戒するという状況は、教育現場において良いパターンではないと准教授は感じていたのです。
未来の社会では、AIなしの仕事や生活は考えられないという認識が重要です。坂井准教授は「AIの使い方を正しく教える方が、むしろ重要なのではないか」という考えから、「miibo」を活用した解決策を模索し始めました。AIを適切に活用するスキルを培う教育環境の整備が、現代の教育現場に求められているのです。
文系教員によるmiiboを活用したノーコード開発
プログラミングの専門知識がなくても、miiboのノーコード環境で会話型AIの開発が可能です。「私は完全な文系人間です。コードは大学1年生と同じレベルの知識しかありません」と話す坂井准教授ですが、miiboの直感的な操作環境によって教育用AIアプリケーションの開発に成功しました。
文系の教員や学生がアイデアを形にできる新しいルートをmiiboは提供しています。坂井准教授は「文系の学生や教員は、実はアイデアをたくさん持っています。ただ、技術がないために実現できないでいました」と語ります。miiboは、技術的な障壁を取り除き、教育現場の創意工夫を実装可能にするプラットフォームとして機能したのです。
ゲーム感覚でAIを体験できる仕組みの構築が、学生のAI理解を促進しました。「1年生の『使ったことがない』『ほとんど使ったことがない』が半数で、一部の生徒はAIを怖いと感じている」状況を打開するため、坂井准教授はmiiboを活用した参加型の学習環境を設計したのです。この取り組みによって、学生たちはAIと自然に触れ合いながら、その可能性と限界を体験的に学ぶことができました。
論理力向上のための対話型クイズボットの開発と成果
学生が苦手とする「問いを立てる」という課題に対応するため、対話型クイズボットが開発されました。坂井准教授は、論理的思考の基盤となる「問いを立てる」能力の向上が、学生の学びにとって重要だと考えていたのです。miiboを活用することで、学生と対話しながら論理的思考を鍛える会話型AIの開発に成功しました。
AIとの対話形式の学習によって、学生は積極的に論理的思考のトレーニングに取り組めるようになりました。「問いを立てることが苦手な学生も、AIと会話しながら論拠を聞いたり、分析に反論したりすることで」学習への関心を高めたと坂井准教授は説明します。従来の一方向的な学習とは異なり、対話を通じた双方向の学びが実現したのです。
学生たちはAIからの肯定的なフィードバックにも良い反応を示しています。「AIが褒めてくれる」という特徴により、学生たちは失敗を恐れず挑戦できる環境の中で学習を進めることができました。坂井准教授によると、学生たちは想定以上に積極的にAIとの対話に参加し、論理的思考力の向上に取り組んでいるとのことです。
レポート添削支援ボットによる業務効率化
大量のレポート添削は教員にとって大きな負担となっていました。「1クラス30人、3クラス計100人近いレポートの添削」という課題に直面していた坂井准教授は、特に「初期段階のレポートに向き合うのが一番時間がかかる」と感じていたのです。この課題に対し、miiboを活用した解決策を模索しました。
AIによる事前チェックシステムの構築によって、効率的な指導プロセスが実現しました。坂井准教授は「AIに自身の知識を入れ込んで、AIによる事前チェックシステムを構築」し、「まずAIのチェックを通してから提出させる取り組み」を行っています。この仕組みにより、基本的な添削はAIが担当し、教員はより深い指導に集中できるようになりました。
レポート添削支援ボットの導入により、教員の負荷が大幅に軽減されています。坂井准教授によると、AIによる1次チェックを経たレポートは質が向上し、教員による最終チェックの効率が大幅に改善されたとのことです。この業務効率化により、教員はより創造的な教育活動に時間を割くことが可能になっています。
AIの適切な活用を促す教育的工夫
AIとの対話を適切に行ったかを確認するため、特定のキーワードを活用する工夫が施されています。「例えば、学生がAIとの対話を適切に行ったことを確認するため、特定のキーワード(『花子』や『もちまる』など)をAIが会話の中で発するよう設定」したと坂井准教授は説明します。このキーワードを課題の一部として記入させることで、学生が実際にAIと対話したことが確認できる仕組みになっています。
レポート添削支援ボットには適切な利用を促す指針が組み込まれています。「レポートの丸写しはダメですが、添削ならOK」といった利用指針をAIボット自体に組み込むことで、学生のAI活用が適切な範囲に収まるよう工夫されています。坂井准教授は、学生が「答えを教えて」と依頼しても、AIが明確に禁止事項として伝えるよう設定しているのです。
これらの工夫によって、AIを適切に活用する教育環境が整備されました。坂井准教授のアプローチは、AIを「使わせない」のではなく「正しく使わせる」ことに重点を置いています。AIとの付き合い方を学ぶ経験そのものが、学生たちの将来的なAI活用スキルの基盤となるのです。
教育現場におけるAI活用の今後の展望
AIの活用は教育現場の業務効率化に大きく貢献する可能性を秘めています。「学校の先生はみんな忙しくて大変です。AIで少しでも楽になってほしい」と語る坂井准教授は、現在の「よくわからないから使えない」という状況を変えるため、実践例の共有や活用方法の普及を目指しています。miiboの導入事例が広がることで、より多くの教育者がAIの恩恵を受けられるようになるでしょう。
「使わせない」から「正しく使わせる」への転換が教育のパラダイムシフトを促進します。坂井准教授の取り組みは、AIを禁止するのではなく、AIを適切に活用する能力を育てることの重要性を示しています。この転換により、学生たちは未来の技術環境に適応する力を身につけることができるのです。
教育現場の働き方改革とデジタル化の両立に向けた取り組みが始まっています。坂井准教授の実績は、miiboを活用することで文系教員でも気軽にAIアプリケーションの開発に挑戦できることを実証しています。この成功例をもとに、より多くの教育者がAIを活用した教育改革に取り組むことが期待されています。
まとめ:教育現場のDXを加速するmiibo活用
miiboの導入により、プログラミング知識のない教員でもAIを活用した教育改革が可能です。鹿児島大学の坂井准教授の事例は、文系教員がmiiboのノーコード環境を活用して、論理力向上ボットやレポート添削支援ボットを開発し、教育課題の解決に成功した実例を示しています。AIを教育現場で適切に活用することで、学生の学習体験の向上と教員の業務効率化の両立が実現できるのです。教育分野におけるAI活用はまだ始まったばかりですが、miiboのような直感的なプラットフォームの普及により、今後さらに多くの革新的な取り組みが生まれることが期待されます。