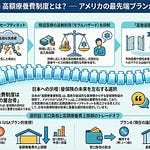令和7年度第13回入院・外来医療等の調査・評価分科会において、重症度、医療・看護必要度の評価体系に関する重要な検討結果が示されました。分科会では、特定集中治療室・ハイケアユニット用の評価項目の適正化と、一般病棟用のB項目測定における負担軽減という2つの重要テーマを扱いました。現行の評価体系には、活用されていない項目の存在、実態と乖離した基準設定、医療現場における記録負担という3つの課題が明らかになっています。
本稿では、集中治療室における致死性不整脈管理の評価のあり方、動脈圧測定・中心静脈圧測定の位置づけの見直し、一般病棟におけるB項目の特性分析と測定の合理化という3つの論点を詳述します。これらの検討結果は、次期診療報酬改定における重症度、医療・看護必要度の見直しに直接的な影響を与える重要な知見です。分科会が提示した課題と改善の方向性を理解することは、医療機関における今後の体制整備を考える上で不可欠です。
特定集中治療室・ハイケアユニット用評価項目の課題と見直しの方向性
特定集中治療室用とハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度には、評価項目の配点と実際の活用状況に大きな乖離があります。現行制度では、シリンジポンプの管理は1点という配点になっており、該当基準が2点以上であるため、この項目は実質的に基準該当の判定に活用されていません。一方、動脈圧測定と中心静脈圧測定はいずれも2点の配点となっており、これら単独の実施のみで基準を満たすことになります。
日本集中治療医学会のICU入退室指針では、人工臓器サポートや心血管作動薬などの薬剤持続投与を行わない動脈圧測定や中心静脈圧測定の患者については、中間ユニットでの管理を考慮するとされています。現行の評価体系は、この学会指針と整合性がとれていない状況です。特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者は全体の約92%に達しており、施設基準である7割または8割を大きく上回っています。該当患者割合が最も高い項目は動脈圧測定で約84%、最も低い項目は肺動脈圧測定で約6%でした。
ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度では、基準①を満たす患者は概ね3割であり、要件の1割5分を上回っています。基準②を満たす患者は概ね9割であり、要件の6割5分または8割を大きく上回っています。分科会では、現行基準が実態と乖離しているため、該当患者や施設の割合を踏まえた基準の見直しが必要であるとの意見が示されました。
集中治療室における致死性不整脈管理の評価強化
特定集中治療室とハイケアユニットの入室患者の傷病名では、急性心筋梗塞後の患者が上位を占めています。急性冠症候群ガイドラインでは、急性心筋梗塞発症直後は致死性不整脈の管理等を目的として、CCU(cardiac care unit)での管理が推奨されています。致死性不整脈が確認された場合には直ちに電気的除細動を行うこと、必要に応じて抗不整脈薬の投与を考慮することが推奨されています。また、病態に応じて一時的ペーシングが必要となる場合があります。
特定集中治療室管理料の算定患者のうち、蘇生術の施行(電気的除細動を含む)に該当する患者割合は約5%、抗不整脈剤の使用は約12%、一時的ペーシングは約1%でした。ハイケアユニット入院医療管理料の算定患者では、抗不整脈剤の使用に該当する患者割合は約4~6%、一時的ペーシングに該当する患者割合は約0.1~0.3%でした。現行の特定集中治療室用・ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度では、これらの処置を評価する項目がありません。
分科会では、急性冠症候群の治療後や心停止蘇生後の患者は、人工呼吸器の管理等を要さない場合であっても、ICUやHCUにおいて厳格な不整脈のモニタリングを要する場合があるとの意見が出されました。致死性不整脈等のリスクに備えた管理は、ICUやHCUの重要な役割の一つであることを踏まえ、蘇生術の施行、電気的除細動、抗不整脈薬の投与、一時的ペーシング等の処置について、特定集中治療室用とハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度での位置づけを検討してはどうかとの提案がなされました。
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度における必要度Ⅱの普及と課題
令和6年度診療報酬改定において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価項目が見直され、急性期一般入院料1では割合①と割合②が設定されました。令和6年11月1日時点で、必要度Ⅱを届け出ている施設は、急性期一般入院料1で99.0%、急性期一般入院料2-3で78.3%、急性期一般入院料4-6で41.0%となり、令和4年11月1日時点より増加しています。必要度Ⅱの普及により、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価が広がり、看護職員の記録負担の軽減が期待されています。
重症度、医療・看護必要度Ⅰの該当患者割合は、急性期一般入院料2-3においてのみ令和4年より令和6年の割合が高くなりましたが、その他の入院料については令和6年の割合は低下しています。重症度、医療・看護必要度の記録について、病棟看護管理者が課題に感じていることを調査したところ、「特になし」と回答した割合は必要度Ⅰが26.1%、必要度Ⅱが28.9%であり、必要度Ⅱの方が課題を感じていない割合が高くなっています。看護職員による記録忘れが多いとの回答は必要度Ⅰが51.7%、必要度Ⅱが47.4%、看護必要度に関する職員研修に手間がかかるとの回答は必要度Ⅰが35.5%、必要度Ⅱが31.8%と、いずれも必要度Ⅰの方が課題を感じている割合が高くなっています。
必要度の記録により時間外勤務が発生しているとの回答は、必要度Ⅰが19.7%、必要度Ⅱが21.0%でした。分科会では、看護師による重症度、医療・看護必要度の評価に係る負担が軽減されてきたと考えられる一方で、どこにどのような負担があるのかをもう少しデータとして調べていく必要があるのではないかとの意見が出されました。また、令和2年度診療報酬改定における記録簡素化について再度周知すべきとの意見もありました。
B項目の特性分析と測定の合理化に向けた検討
令和2年度診療報酬改定において、重症度、医療・看護必要度のB項目について、「患者の状態」と「介助の実施」に分けた評価とし、「評価の手引き」により求めている「根拠となる記録」を不要とする見直しが行われました。令和6年度診療報酬改定では、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価項目の見直しに伴い、急性期一般入院料1等では、B項目は基準から除外されましたが、当該評価票を用いて評価を行っていることが要件となっています。
急性期一般入院料1は、急性期一般入院料2~6と比較して、基準1~3に該当する割合およびA得点2点以上の割合が高く、B得点3点以上の割合は低くなっています。地域包括医療病棟は、急性期一般入院料と比較して、B得点3点以上に該当する割合が高く、70%を超えています。入院初日にB得点が3点以上である割合は、特定機能病院や急性期一般入院料1で低く、急性期一般入院料2~6や地域一般入院料1、地域包括医療病棟で高くなっています。地域包括医療病棟では入院初日にB得点が3点以上である割合が68%であり、令和6年では最も高い割合を占めています。
急性期一般入院料2~6、地域包括医療病棟における入院時と退院時のB得点は、要介護度との高い相関がみられました。特に要介護4~5においては、入院時から退院時にかけてB得点の変化がほとんどみられませんでした。患者全体の入院中のB項目の平均値は、入院後日数が経つにつれ、患者数の減少とともに緩やかに上昇しています。B項目の前日との差分の平均は、入院3日目頃からマイナス(改善)であり、7日目頃から変化がなくなっています。この時期には前日とB項目の変化がない患者が約7割程度となっています。
分科会の分析では、B項目は、疾患によって悪化した身体機能によるケアの必要性と、発症前からの身体機能によるケアの必要性の双方を反映した指標であると考えられました。入院4日目、術後7日目以降はB項目の変化が少ない患者の割合が約7割に収束すること、A項目が±2点以上変化した場合にB項目も同じ方向に変化する患者の割合が増えること、要介護度が高いとB点数が高いこと、要介護度の高い患者では退院時まで変化しないケースが多いことが明らかになりました。
内科系症例の重症度評価と救急搬送受入の評価案
急性期一般入院料1において、外科系症例(手術に係るKコード算定症例)と比較して、内科系症例(それ以外の症例)では、A得点2点以上、3点以上となる該当割合はいずれも低く、B得点3点以上の割合は高くなっています。救急搬送により入院した内科系症例の重症度、医療・看護必要度の該当割合は、救急搬送ではない外科系症例の重症度、医療・看護必要度の該当割合と比較して、いずれの入院料においても低くなっています。救急搬送からの入院や緊急入院の約8割を内科系症例が占めています。
日本内科学会提出資料によれば、現行のA・C項目に内科系の診療負荷が高い検査や処置を追加する案では、内科系症例と外科系症例の該当患者割合の差は、24.3%から22.8%に縮まりました。A・C項目を精緻化するのではなく、病棟や病院の負荷を直接的に医療・看護必要度の底上げに用いる方法として、救急医療や緊急入院を評価する案が検討されました。令和6年度改定でA項目の「救急に入院を要する状態」の評価日数が5日から2日に引き下げられており、単純に日数を戻すことによる入院延長の誘因となりうることが考慮されました。
分科会では、救急搬送応需件数を各病棟に按分した病床あたり件数や、協力対象施設入所者入院加算の病床あたり算定回数に一定の係数を乗じること等により連続的に評価し、当該病棟の基準該当割合に加算する案について議論されました。この方法に基づくと、基準該当割合への加算分が大きい施設は、概ね内科系症例の割合が多い施設となります。この評価案は、個々の症例の評価指標を精緻化するのではなく、病院・病棟全体の負荷を必要度の基準該当割合に反映する方法として提案されています。
まとめ
令和7年度第13回入院・外来医療等の調査・評価分科会における重症度、医療・看護必要度の検討では、特定集中治療室・ハイケアユニット用と一般病棟用の双方について、評価体系の適正化に向けた重要な課題が明らかになりました。集中治療室では、致死性不整脈管理の評価項目追加と、動脈圧測定・中心静脈圧測定の位置づけ見直しが論点です。一般病棟では、B項目の特性を踏まえた測定の合理化と、内科系症例を適切に評価する新たな指標の構築が課題です。これらの検討結果は、次期診療報酬改定における重症度、医療・看護必要度の見直しに直接的に反映されることが予想されます。