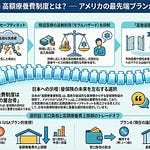2025年11月20日に開催された第204回社会保障審議会医療保険部会において、OTC類似薬の保険給付の在り方について患者団体からのヒアリングが実施されました。厚生労働省がOTC類似薬を保険給付の対象から外すことを検討している背景には、医療費の適正化があります。この提案に対し、患者の立場から具体的な懸念と問題点を提示する必要性が生じました。
3つの患者団体グループ(合計9団体)がOTC類似薬の保険給付除外に反対する意見を表明しました。全国がん患者団体連合会は、がんや難病患者がOTC類似薬を長期継続使用している実態と、保険適用除外による数十倍の負担増を指摘しました。7つのアレルギー関連団体(一般社団法人アレルギー及び呼吸器疾患患者の声を届ける会、認定NPO法人日本アレルギー友の会など)は連名で、難治・重症アレルギー患者への影響と国民皆保険制度の理念との矛盾を提起しました。ささえあい医療人権センターCOMLは、OTC類似薬の範囲設定の困難さと医療用医薬品とOTC医薬品の違いを明らかにしました。
全国がん患者団体連合会が指摘する4つの影響と代替案の提示
全国がん患者団体連合会は、OTC類似薬を保険給付の対象から外すことによる4つの重大な影響を指摘しました。同団体は、がんや難病患者がアセトアミノフェン、ロキソニンテープ、酸化マグネシウムなどのOTC類似薬を日常的に、あるいは長期にわたり継続して使用している実態を示しました。
第一の影響は、患者負担の大幅な増加です。保険給付から外れると、メーカー希望小売価格と比較した場合には数十倍の負担増となります。市場価格の最安値と比較した場合でも、過重な負担増となる可能性があります。
第二の影響は、各種医療費助成制度の対象外になることです。保険給付から外れると、高額療養費、指定難病患者への医療費助成、こども医療費助成、小児慢性特定疾病児童等への医療費助成など、各種の医療費助成の対象とならなくなります。
第三の影響は、医療機関への受診機会の喪失です。負担増により、医療機関への受診機会の喪失、あるいは遅延が生じ、健康被害が生じる可能性があります。
第四の影響は、処方シフトの問題です。患者負担割合はより安価であるが、薬価がより高い薬剤が処方されるようになる可能性があります。
代替案として、同団体は具体的な提案を行いました。どうしても見直しが必要な場合には、公的な保険給付の対象から外すのではなく、患者の自己負担割合を変更する対応を検討すべきであると提案しました。この方法であれば、公的な薬価が維持され、患者の負担増は一定程度抑えられ、高額療養費や各種の医療費助成の対象であることも維持され、医療機関への受診機会も確保される可能性があります。ただし、患者の自己負担割合の変更でも、患者の負担増となることは避けられず、処方シフトなどの問題が生じる可能性も依然として残ります。
7つのアレルギー関連団体が連名で懸念を表明
7つのアレルギー関連団体は連名で、OTC類似薬の保険適用除外が国民皆保険制度の理念に反する可能性を指摘しました。提出団体は、一般社団法人アレルギー及び呼吸器疾患患者の声を届ける会、認定NPO法人日本アレルギー友の会、NPO法人環境汚染等から呼吸器病患者を守る会、NPO法人アレルギーを考える母の会、NPOアレルギー児を支える全国ネット「アラジーポット」、NPO法人ピアサポートF.A.cafe、NPO法人アレルギーの正しい理解をサポートするみんなの会です。これらの団体は、国民皆保険制度は社会全体で医療費を分担する仕組みであり、経済的な理由で医療を受けられない人を減らすという理念のもとに成り立っていることを強調しました。
難治・重症アレルギー患者への深刻な影響が予想されます。喘息やアトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患は、標準治療のもとで多くの患者が症状をコントロールできるようになっています。しかし、一部の難治・重症患者は高額な生物学的製剤などを長期にわたって使う必要があり、医療費の増加は治療継続を困難にし、生活や就業に深刻な影響を及ぼします。
子どものアレルギー治療における家計負担の増加も重大な問題です。OTC類似薬の保険適用除外は、特に子どものアレルギー治療において家計に大きな負担を強いることになります。この負担増は、子どもの健全な成長や家庭生活に悪影響を及ぼす可能性があります。
具体的な懸念として、ステロイド外用薬の問題があります。アトピー性皮膚炎治療の標準治療であるステロイド外用薬は、効果の強度により5段階に分類されています。現在は医師が症状の重症度を判定し、適切な薬を処方していますが、薬局で購入する場合、強度を認識せずに使用して副作用が出たり、症状に対して弱すぎるために効果が出ず、炎症が持続して重症化してしまう可能性があります。
これらの団体は3つの要望を提出しました。高額療養費制度の自己負担限度額引き上げは、家計への影響を考慮し、治療継続が可能となるよう見直すことです。OTC類似薬の保険適用除外は、アレルギー疾患の標準治療に使われる薬剤・保湿剤には適用しないことです。制度改正にあたっては、患者の声を適切に反映することです。
ささえあい医療人権センターCOMLが提起する制度設計上の課題
ささえあい医療人権センターCOMLは、OTC類似薬の範囲を病名や病状で線引きすることの困難さを指摘しました。同団体は、医療用医薬品とOTC医薬品では効能・効果のみならず、成分や用量が異なるなかで「OTC類似薬」と一括りに判断できないこと、しかも患者にはその違いや判断ができないことを明らかにしました。
医師の診療上の判断への影響も懸念されます。他の疾患との関連で使用している医薬品の場合、一部が保険外になることで医師の診療上の判断が適切にできない場合も生じかねません。医師の管理下を離れることで、患者が自己判断で量や服用頻度などを変える可能性もあります。
配慮すべき対象の範囲の問題もあります。「こどもや慢性疾患、低所得者に配慮」すれば対象は激減し、特に慢性疾患患者が多いことから本来の目的を果たせない改革になる可能性があります。「近隣に薬局がない」「インターネットで購入できない高齢者」など、購入の利便性の地域差・個人差もあります。
同団体は、混在している議論を整理する提案をしました。医療用医薬品の代わりにOTCを患者に購入してもらう案では、患者が使用するのはOTCであり、医師の管理下を離れ、成分や用量が異なる、利便性の差があるなど問題が多いと指摘しました。OTCにもあるような医療用医薬品の保険負担を検討する案では、患者が使用するのは医療用医薬品であり、医師の管理下で安全は保たれますが、OTC類似薬を10割負担にすると患者負担が重くなりすぎるため、追加負担を求めるとしても患者負担が重くなりすぎないように配慮が必要であると提案しました。
医師の判断で医薬品を処方せず患者がOTC薬を購入することになると、費用が高くなるので購入しない患者が出て「治療」が成立しなくなり、症状悪化でさらに高い医療費が必要な治療が必要になる可能性があります。ほかに医薬品を使用している場合の飲み合わせや相互作用の判断ができない問題もあり、現在のドラッグストアの薬剤師や登録販売者の実態では対応不可能ではないかという懸念も示しました。
まとめ
3つの患者団体グループ(合計9団体)は、OTC類似薬の保険給付除外について、患者への重大な影響と制度設計上の課題を指摘しました。全国がん患者団体連合会は数十倍の負担増と医療費助成対象外になる問題を、7つのアレルギー関連団体は連名で国民皆保険制度の理念との矛盾と子どもへの影響を、ささえあい医療人権センターCOMLは範囲設定の困難さと医師の管理下を離れる問題を提起しました。今後の医療保険部会での議論において、これらの患者の声がどのように反映されるかが注目されます。