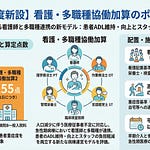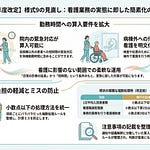生成AI技術の普及により、多くの企業や公共機関がAI活用を急速に進めていますが、データセキュリティやコンプライアンス面での懸念から導入を躊躇するケースも少なくありません。さくらインターネット株式会社は、こうした課題を解決するため、「さくらの生成AIプラットフォーム」を提供開始しました。この記事では、さくらの生成AIプラットフォームの特徴、技術基盤、連携パートナー、想定される活用シーンについて解説します。
さくらの生成AIプラットフォームは、国内データセンターでの運用を前提とした信頼性の高いAI基盤です。NVIDIA H100 Tensor コア GPU搭載の「高火力」クラウドサービスを基盤とし、複数の国産・海外モデルから選択可能な柔軟性を持ちます。サーバーレス環境での手軽な利用と、RAG向けベクトルデータベースの提供により、専門知識がなくても高度なAI活用が可能になります。またシンプルな料金体系と透明性の高い価格設定も特徴として挙げられています。
プラットフォームの技術的特徴
さくらの生成AIプラットフォームは、複数の技術要素を組み合わせた総合的なAI基盤です。このプラットフォームは、フルマネージドの生成AIアプリケーションと基盤モデル、高性能クラウドサービスを繋ぐAPIとベクトルデータベースから構成されています。
高性能なGPUインフラが、このプラットフォームのパフォーマンスを支えています。NVIDIA H100 Tensor コア GPUを搭載した「高火力」クラウドサービスにより、高速かつスケーラブルな処理環境を実現しています。これにより、大規模なデータ処理や複雑なAI応答も効率的に実行することができます。
多様な基盤モデルへのアクセスも提供されています。NEC開発の生成AI「cotomi」をはじめとする国産モデルと、オープンソースの主要モデルを取り揃え、用途に応じた最適なAIモデルの選択が可能です。特に国産モデルは日本語処理に強みを持っています。
使いやすさも重視した設計になっています。サーバーレス環境での提供により、インフラ管理の負担なく生成AIを活用できます。APIを通じた連携と、直感的なインターフェースにより、専門知識がなくてもAIアプリケーションの開発・運用を進めることができます。
データセキュリティと国内完結の仕組み
さくらの生成AIプラットフォームは、データセキュリティを重視した設計となっています。このプラットフォームは、日本国内のデータセンターで運用され、データの保管から処理まですべてを国内で完結させることができます。
国内完結型の運用により、データの越境移転に関するリスクを低減することができます。外国法の域外適用や海外企業によるデータアクセスの懸念が少なく、国内法規制に準拠した安全なAI環境を構築できます。特に行政機関や金融機関、医療機関など、高いセキュリティ要件が求められる組織にとって、この国内完結の仕組みは重要な選択肢となります。
多層的なセキュリティ対策も実装されています。データの暗号化やアクセス制御、セキュアな通信プロトコルの採用により、データの機密性と完全性を確保します。さらに、セキュリティ監査と脆弱性診断を実施し、セキュリティ標準に準拠した運用を維持する体制が整えられています。
ガバメントクラウド認定を取得していることも特徴の一つです。2025年度末までに技術要件をすべて満たすことを前提とした条件付きの認定により、公共機関での利用も視野に入れたセキュリティ基準を満たしています。
パートナー企業との連携
さくらの生成AIプラットフォームでは、さまざまなパートナー企業との連携が行われています。このパートナーシップにより、基盤モデルの提供からアプリケーション開発まで、AIのバリューチェーン全体をカバーすることを目指しています。
LLMパートナーとして、NECとPreferred Networksが参画しています。NECの「cotomi」は日本語理解に特化した対話モデルとして、Preferred Networksも国産の言語モデルを提供しています。
Appパートナーとしては、複数の企業が参加しています。株式会社miiboは、ノーコードで会話型AIを構築できるプラットフォームを提供しています。miiboのプラットフォームを通じて、プログラミング不要で会話型AIを開発することができます。
GitHouseは、データに関するサービスを提供する企業としてAppパートナーに名を連ねています。同社のウェブサイトでは「データで生産性を向上」というテーマが掲げられています。
ブレインズテクノロジー株式会社も重要なパートナーとなっており、企業内検索エンジン「Neuron ES+生成AI連携オプション」と生成AIナレッジチャット「Chat EI」をプラットフォームに提供することを発表しています。これらのサービスにより、企業内ドキュメントやFAQデータの効率的な活用が可能になります。
各パートナー企業はそれぞれの専門分野の知見を活かし、さくらの生成AIプラットフォームのエコシステム形成に参画しています。ユーザーはこれらのパートナーが提供するサービスを通じて、様々なAI活用の可能性を検討することができます。
想定される活用シーン
さくらの生成AIプラットフォームは、様々な業界や用途での活用が想定されています。企業の業務効率化から公共サービスの向上まで、幅広いニーズに対応する可能性を持っています。
企業の内部業務効率化は、主要な活用シーンの一つとして考えられます。社内文書を基にしたナレッジベースの構築により、業務マニュアルやFAQ、過去の事例などの情報を検索・活用できるようになります。営業資料の作成支援や社内問い合わせ対応の効率化など、日常業務の生産性向上に貢献することが期待されます。
カスタマーサポートの強化も、注目される活用シーンです。顧客からの問い合わせに対応するAIチャットボットを構築することで、サポート品質の向上とコスト削減を同時に実現できる可能性があります。特に定型的な質問への回答や初期対応をAIが担当することで、人的リソースをより複雑な問題解決に集中させることができます。
公共サービスでの活用も重要な用途として挙げられます。自治体の窓口業務効率化や住民向け情報提供など、公共サービスの質を向上させながら、行政コストを削減することができます。国内完結型のセキュアな環境は、個人情報を含む行政データを扱う上で適した選択肢となります。
教育分野での活用も考えられます。学習進捗の分析や教材の自動生成など、教育のパーソナライズ化を支援するAIアプリケーションの開発が可能です。教員の事務作業負担を軽減し、より質の高い教育活動に集中できる環境づくりに貢献することが期待されます。
これらの活用シーンは可能性の一例であり、実際の導入においては各組織の目的や状況に応じた検討が必要です。
まとめ
さくらの生成AIプラットフォームは、国内完結型の安全なAI基盤として、企業や公共機関のデジタル変革を支援する役割を担っています。高性能GPUインフラと複数の言語モデル選択肢、セキュリティ対策と使いやすさを兼ね備えたプラットフォームとして、日本のAI市場における選択肢の一つとなっています。さくらインターネットとLLMパートナー・Appパートナーの連携により、技術的な基盤と実用的なアプリケーションを組み合わせたAIエコシステムの構築が進められています。
生成AI技術の活用を検討する組織にとって、国内完結型のプラットフォームは、データセキュリティや法令遵守の観点から注目される選択肢となっています。さくらの生成AIプラットフォームの特徴と連携パートナーについて理解を深め、それぞれの組織に適したAI活用の形を検討する際の参考になれば幸いです。