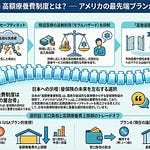令和7年度第13回入院・外来医療等の調査・評価分科会において、救急医療に関する検討結果がとりまとめられました。令和6年中の救急出動件数と搬送人員は過去最多を記録し、特に高齢者の搬送が増加しています。現場到着時間と病院収容時間はいずれも延伸しており、救急医療体制への負担が増大しています。現在の診療報酬制度では、救急患者連携搬送料の届出率が17%にとどまり、受入側医療機関への評価が不足しています。救急外来応需体制についても、24時間体制を構築する医療機関への適切な評価が課題となっています。
分科会では、救急医療需要の増加に対応するため、搬送連携と外来応需体制の両面で診療報酬評価の見直しが必要との認識が示されました。救急搬送の現状では、救急患者連携搬送料の届出が低調であり、搬送元医療機関のみが評価される一方で受入側医療機関への評価がないことが指摘されました。救急外来応需体制では、院内トリアージ実施料と夜間休日救急搬送医学管理料の算定状況が報告され、ウォークイン救急患者を多数受け入れる医療機関の実態が明らかになりました。分科会からは、受入側医療機関への評価の必要性、地域包括ケア病棟での受入評価の充実、患者等搬送事業者の活用検討、24時間診療体制への適切な評価という4つの改善提案が示されています。
救急搬送の現状と救急患者連携搬送料の課題
令和6年中の救急自動車による救急出動件数と搬送人員は、集計開始以来の過去最多を記録しました。年齢区分別の搬送人員をみると、高齢者が増加している傾向が顕著です。
搬送時間の延伸も深刻な課題となっています。令和5年中の救急自動車による現場到着所要時間は全国平均で約10.0分でした。病院収容所要時間は全国平均で約45.6分でした。新型コロナウイルス感染症の発生前の令和元年と比較すると、現場到着所要時間は約1.3分延伸し、病院収容所要時間は約6.1分延伸しています。
救急患者連携搬送料の届出状況は低調でした。高度救命救急センター、救命救急センター及び第二次救急医療機関において、救急患者連携搬送料を届け出ている医療機関は17%にとどまりました。救急患者連携搬送料の届出医療機関数は、令和6年7月時点で224施設でしたが、令和7年5月には387施設へ大幅に増加しました。
届出していない理由には複数の要因がありました。「救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる救急搬送件数が年間で2,000件未満であるため」という回答が多くありました。「搬送に同乗するスタッフが確保できないため」という人員配置の課題を挙げる医療機関もありました。「自院又は連携先医療機関が緊急自動車を保有していないため」という設備面の課題も指摘されました。「地域のメディカルコントロール協議会等と協議を行った上で、候補となる保険医療機関のリストを作成するという要件の達成が困難であるため」という体制整備の困難さも挙げられました。
算定実態をみると、令和6年10月1か月に救急患者連携搬送料を算定した患者数は、ほとんどの医療機関において少数でした。搬送理由としては、「処置・手術等を必要としないが、急性疾患に対する治療を必要とする状態であった患者」が最も多くなっていました。
転院搬送の実態も明らかになりました。第二次救急医療機関の一部には、入院した救急患者の25%以上が転院搬送で受け入れた患者である医療機関がありました。
救急外来応需体制の評価状況
救急外来医療に対する診療報酬評価として、院内トリアージ実施料と夜間休日救急搬送医学管理料があります。院内トリアージ実施料の算定医療機関数は、やや増加傾向を示しています。算定回数は、新型コロナウイルス感染症流行後に大幅に増加しましたが、令和6年には以前の水準まで減少しました。
夜間休日救急搬送医学管理料の算定回数は、令和2年以降増加傾向が続いています。第二次救急医療機関における年間救急搬送患者受入人数に占める夜間休日救急搬送医学管理料の年間算定回数の割合を医療機関ごとに算出すると、令和2年度の平均値は24.6%、令和4年度の平均値は21.9%でした。
ウォークイン救急患者の受入実態も注目されました。救急車等の救急受入患者数が少ない医療機関でも、相当数のウォークイン救急患者を受け入れている医療機関が多数存在することが明らかになりました。
救急医療管理加算の算定状況も報告されました。救急医療管理加算の算定回数は、令和2年に減少したものの、以降は増加傾向を示しています。届出医療機関数は、令和2年以降横ばいからやや増加傾向となっています。入院した救急患者のうち、ウォークイン救急受診患者を含めて平均54.4%の患者に救急医療管理加算が算定されていました。
分科会が示す改善の方向性
分科会では、救急患者連携搬送における評価の課題について意見が示されました。救急患者連携搬送料は搬送元医療機関で算定するものである一方、受入側医療機関の評価がないことが指摘されました。救急患者連携搬送は受入側医療機関の協力を前提とした制度であることから、受入側にも一定の評価を設けることが必要との意見がありました。
地域包括ケア病棟における受入評価についても提案がありました。地域包括ケア病棟において救急患者連携搬送料を算定した患者を受け入れた場合について、在宅患者支援病床初期支援加算の対象としたことには意義があるとされました。救急連携搬送における受入側医療機関への評価をさらに充実させることで、医療機関間の機能分担や連携の促進につながるのではないかとの意見がありました。
搬送手段の多様化についても検討の余地が示されました。救急患者連携搬送にあたっては、病院救急車だけでなく、患者等搬送事業者を活用することについても、今後検討の余地があるのではないかとの意見がありました。
救急外来応需体制に関しては、24時間診療体制への評価の必要性が提起されました。救急患者を多数受け入れる医療機関においては、医師・看護師等の人員配置に加え、24時間体制で検査・処方等が可能な診療体制の整備が不可欠であるとされました。こうした体制を構築し、地域の救急医療において重要な役割を果たしている医療機関については、適切な評価がなされるべきではないかとの意見がありました。
まとめ
救急医療需要の増加に対応するため、診療報酬評価の見直しが必要です。救急患者連携搬送では、搬送元だけでなく受入側医療機関への評価を設け、医療機関間の機能分担と連携を促進することが求められています。救急外来応需体制では、24時間診療体制を構築する医療機関への適切な評価が必要とされています。分科会が示した改善提案を踏まえ、救急医療提供体制の充実に向けた診療報酬制度の見直しが期待されます。