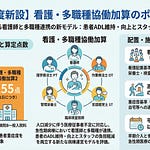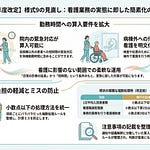令和7年11月20日に開催された第204回社会保障審議会医療保険部会において、医療保険制度における出産に対する支援強化の議論が本格化しました。この部会では、令和8年度を目途とした標準的な出産費用の自己負担無償化に向け、給付体系の骨格を令和7年冬頃までにとりまとめる方針が示されました。議論の焦点は、現在の出産育児一時金という現金給付から、妊婦の自己負担が発生しない給付方式への転換、そして地域差・施設差がある出産費用への対応という2つの論点です。
本稿では、部会で提示された給付体系見直しの方向性、産科医療機関の経営実態を踏まえた制度設計の課題、令和7年冬のとりまとめに向けた今後のスケジュールの3点を解説します。この制度改革は、妊婦の経済的負担軽減と周産期医療提供体制の維持という2つの政策目的を同時に実現する必要があり、特に経営困難に直面する一次施設への配慮が重要な検討事項となっています。制度設計では、出産費用の見える化を進め、妊婦が十分な情報に基づいて意思決定できる環境整備も求められています。
出産支援強化の背景と制度見直しの必要性
令和7年5月に公表された「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会」の議論の整理において、令和8年度を目途に標準的な出産費用の自己負担無償化に向けた具体的な制度設計を進めることが示されました。この方針を受けて、社会保障審議会医療保険部会で給付体系の見直しについての検討が開始されています。
制度見直しの背景には、現行の出産育児一時金制度に対する当事者からの指摘があります。部会の議論では、出産育児一時金の引き上げが行われるたびに、医療機関側も出産費用を値上げする傾向があり、結果として妊婦の負担軽減につながっていないという意見が示されました。この構造的な課題を解決するため、給付方式の抜本的な見直しが必要とされています。
見直しの目的は、妊婦が経済的負担を心配せずに安心して出産できる環境を整備することです。具体的には、標準的なケースで妊婦の自己負担が発生しない仕組みへの転換を目指しています。この転換により、出産費用の高額化に伴う不安を解消し、子供を産みたいと考える人々への支援を強化します。
給付体系見直しの2つの主要論点
部会では、給付体系見直しに関する2つの主要論点が提示されました。第一の論点は、給付方式の在り方についてです。現在の出産育児一時金は現金給付の仕組みですが、これを標準的なケースで妊婦の自己負担が発生しないような給付方式に転換することが検討されています。
給付方式の転換では、現物給付化が一つの選択肢として議論されています。部会での意見では、現金給付から現物給付への移行により、出産費用の直接的な支援が可能になるという指摘がありました。現物給付化により、医療機関への支払いを医療保険制度が直接行う仕組みとなり、妊婦の経済的負担が軽減されます。
第二の論点は、給付の内容についてです。出産費用には地域差や施設差が存在する現状があり、これらの差異に配慮した給付内容の設計が求められています。また、産科医療機関の経営状況も踏まえた検討が必要とされています。給付内容の検討では、標準的な出産費用の範囲をどう定めるか、その後の検証をどのように行うかという点も議論の対象となっています。
標準的な出産費用の範囲設定における課題
標準的な出産費用の範囲設定は、給付体系見直しにおける最も重要な検討課題の一つです。部会での議論では、負担とのバランスを考慮しながら、今後報告される出産費用に関するさらなるデータを踏まえて検討を進める必要性が指摘されました。
範囲設定では、妊婦が十分な情報に基づいて出産に関する自己決定を行える環境整備が前提となります。部会では、出産にかかる費用とサービスの関係が不明確であるという妊産婦からの声が紹介されました。この課題に対応するため、出産費用の見える化をより一層進めることが求められています。見える化により、妊婦は提供されるサービスの内容とその費用を明確に理解でき、納得感のある選択が可能になります。
標準的な出産費用には、地域差と施設間格差への対応という2つの論点があります。地域による医療資源の違いや、施設ごとの設備・人員体制の差異が出産費用に影響を与えています。また、無痛分娩などの妊婦のニーズが高いサービスを標準の範囲に含めるかどうかも議論の対象です。無痛分娩については、リスクやデメリットもあるため、まず安全に提供できる体制整備が必要であり、慎重な検討が求められるという意見が示されました。
産科医療機関の経営実態と周産期医療体制の維持
給付体系の見直しにおいて、産科医療機関の経営実態への配慮は極めて重要な検討事項です。日本医師会総合政策研究機構の調査によれば、2022年度の産科医療機関の経常利益では赤字施設が全体の41.9%を占め、2023年度には42.4%へと拡大しています。この経営悪化の背景には、少子化の進行と物価高騰があります。
地域の周産期医療を支えているのは一次施設です。一次施設は、正常分娩を取り扱う診療所や病院を指します。部会での議論では、一次施設が機能しなくなれば、お産難民が今以上に増加するという懸念が示されました。そのため、制度設計では一次施設を守るという観点が最優先されるべきとの意見が複数の委員から出されています。
現在、分娩を取り扱う一次施設の減少により、三次施設にローリスクの妊産婦が集中する状況が生じています。三次施設とは、ハイリスク妊娠や重症新生児に対応する総合周産期母子医療センターです。この集中により、三次施設では人員確保や病床確保が困難になっています。制度設計では、地域の一次施設を守り、拙速な集約化を招かないよう、特に丁寧な検討を進める必要があります。
妊産婦の多様なニーズへの対応と選択の保障
新たな給付体系では、妊産婦の多様なニーズに対応し、選択を制限しない仕組みが求められています。部会での議論では、出産に関しては医療的な安全確保とともに、助産師による助産ケアを通じて妊産婦の不安を軽減することが重要であるという指摘がありました。
妊産婦の選択を保障するためには、出産費用とサービス内容の関係を明確にする必要があります。検討会のヒアリングでは、何のために費用を払っているのか、なぜ病院ごとに費用が違うのかが当事者には分からないという声が上がっていました。この情報の非対称性を解消するため、出産費用の見える化を前提とした制度設計が求められています。
妊産婦の多様なニーズには、助産所における出産や無痛分娩など、様々な出産スタイルへの希望が含まれます。部会では、助産所における出産を含め、全ての出産の場が新たな枠組みの中に適切に位置づけられることへの期待が示されました。また、WHO(世界保健機関)が推奨するエビデンスに基づいた産痛緩和ケアを標準の範囲に含める方向での検討も提案されています。ただし、こうしたサービスの標準化にあたっては、安全性の確保と体制整備が前提条件となります。
税と保険料の役割分担と財源確保の課題
給付体系の見直しでは、税と保険料の性格の違いを踏まえた財源確保の議論も重要です。部会では、限りある保険医療財政を踏まえ、それぞれの目的に応じた施策を検討していくべきという意見が示されました。
財源確保の議論では、周産期医療提供体制の確保という課題をどう位置づけるかが論点となっています。一部の委員からは、周産期医療提供体制の確保は国としての体制整備の問題であり、出産に対する給付体系の見直しとは切り離して別途解決を図るべきという意見が出されました。この意見は、産科医療機関の経営支援と妊婦の負担軽減を別の政策として整理すべきという考え方を示しています。
保険料を負担する被保険者の納得感も重要な検討事項です。標準的な出産費用の範囲を設定する際には、保険診療の考え方や保険料負担者の理解が得られる内容とする必要があります。部会では、こうした観点も念頭に置いて議論を深めていくべきという指摘がありました。また、出産費用の自己負担無償化が子育て支援策なのか、出産費用の負担抑制策なのかについても整理が必要という意見が示されています。
今後のスケジュールと制度施行に向けた検討プロセス
医療保険部会における今後の議論の進め方は、段階的なアプローチが採用されています。令和7年冬頃までの議論では、給付体系の骨格の在り方について整理することを目指しています。この骨格には、給付方式と給付内容の基本的な枠組みが含まれます。
給付体系の骨格が固まった後、産科臨床現場で行われる個々の対応についての具体的な当てはめなど、個別具体的な内容については制度施行に向けてさらに議論を深める予定です。このように、まず大枠を決定し、その後に詳細を詰めていくという二段階のプロセスが採用されています。
検討プロセスでは、出産費用に関するさらなるデータの報告も予定されています。これらのデータは、標準的な出産費用の範囲設定や地域差・施設差への対応策を検討する際の基礎資料となります。データに基づいた議論により、実態を踏まえた制度設計が可能になります。最終的に令和8年度を目途として、産科医療機関等の経営実態等にも十分配慮しながら、標準的な出産費用の自己負担無償化に向けた具体的な制度設計が完成する見込みです。
まとめ
第204回社会保障審議会医療保険部会では、医療保険制度における出産支援強化の方向性が示されました。制度見直しの焦点は、給付方式の転換と給付内容の設定という2つの論点です。令和7年冬頃までに給付体系の骨格をとりまとめ、令和8年度を目途に標準的な出産費用の自己負担無償化を実現する方針です。制度設計では、妊婦の経済的負担軽減と産科医療機関の経営実態への配慮、特に一次施設の維持という課題の両立が求められています。