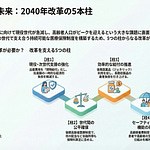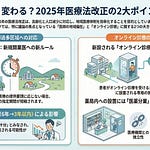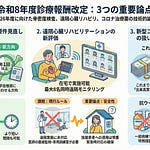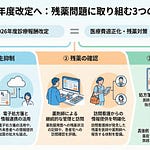京都芸術大学クロステックデザインコースでは、「スタートアップ思考1・2」の授業に会話型AI構築プラットフォーム「miibo」を活用した「AIバディ」を導入し、革新的な教育実践を行っています。教育現場でのAI活用が注目される中、実際の大学教育における具体的な活用事例として、この取り組みをご紹介します。
AIバディは学生一人ひとりに専用の会話型AIを提供し、授業内容の記録から対話による理解促進まで、学習を継続的にサポートする教育ツールです。株式会社miiboと共同開発されたこのシステムは、NotionやSlackと連携して授業内容を記録・学習し、学生の理解度向上を支援します。学生は授業中のノート作成から復習、最終課題作成までAIバディを活用し、共同学習を実践しています。さらに、学生が自分のAIに名前をつけるなど、対話を通じて成長するパートナーとして親しまれています。
AIバディとmiiboの関係
AIバディは、miiboを活用して京都芸術大学と株式会社miiboが共同開発した、学生一人ひとりの学習を支援するパーソナルAIです。miiboは「溶けこむAI」をコンセプトに、会話型AIを簡単に構築できるプラットフォームとして開発されました。この技術を教育現場に応用することで、学生の学習プロセスに自然に溶けこむAIが実現しています。
miiboの「知能」「知識」「共感」「個性」という4つの要素は、教育支援AIに必要な特性と合致します。特に「共感」と「個性」の要素により、AIバディは単なる情報検索ツールではなく、学生に寄り添い対話できるパートナーとして機能します。
クロステックデザインコースでは、学内初の取り組みとして2024年度より全学生にAIバディを導入しました。これにより、これからの社会で必須となるAIの特性理解と効果的活用を実践的に学ぶ環境が整いました。
AIバディの機能
AIバディは、Notionを活用したノート作成(ペアノート)機能を提供しています。学生は授業内容をNotionに記録し、AIバディがその情報を学習することで、復習時に的確な支援が可能になります。このシステムにより、授業に集中しながらも、後から振り返りがしやすい学習環境が実現しています。
Slackを通じた対話型フィードバック機能も重要な特徴です。AIバディは単に質問に答えるだけでなく、逆に学生に質問を投げかけることもあります。この双方向のコミュニケーションにより、「理解したつもり」から「本質的な理解」へと学生を導きます。他者(AIバディ)に説明することで理解が深まるという教育効果が生まれています。
AIバディは当初は知識のない状態からスタートし、Notionへの記録やSlackでの会話を通じて知識を蓄積します。学生が学べば学ぶほど、AIバディも成長するという相乗効果が生まれています。この成長プロセスにより、学生のAIバディに対する愛着が生まれ、学習モチベーションの向上にもつながっています。
学生からの要望に応じて、最初は「LB(ラーニングバディ)」と呼ばれていたAIに個別の名前をつける機能が追加されました。この迅速な対応は、株式会社miiboのアジャイル開発の強みを示しています。今後は音声による対話機能の追加も予定されており、さらなる進化が期待されています。
授業での活用方法
「スタートアップ思考1・2」は、経済学、地政学、歴史学など多角的な視点から未来社会を考える力を養成する1年生向けの専門科目です。小笠原先生(コース長)、吉田先生、牧田先生が担当し、ファクト(事実)をベースに社会を分析する力や、自身の夢を実現するための経済観を育てる内容となっています。
授業中、学生はNotionのペアノートに授業のポイントを随時メモしていきます。記録は主に3つの観点から整理されます。「今日の授業で教わったこと(事実)」「気づいたこと、学んだこと」「疑問に思ったこと、調べたいと思ったこと」です。スライドや配布資料はそのまま貼り付ければ良いため、学生は思考や疑問に集中できます。
この記録方法を大学4年間の全授業で継続することで、学びの質が変わることが期待されています。AIバディは画像も認識できるため、授業スライドの内容も学習対象となります。これにより、単なるメモ以上の、AIとの共同学習が実現しています。
最終課題では、自分と共に学習してきたAIバディにレポートを作成させるという革新的な取り組みが行われています。一般的にAIを使ったレポート作成は不正行為と見なされがちですが、このコースでは共に学んできたパートナーとしてAIを活用することが正式な課題となっています。この発想の転換は、AIの本質的な価値を教育に取り入れた先進的な事例といえるでしょう。
AIバディの教育的意義
AIバディは単なるツールではなく、共に学ぶパートナーとして位置づけられています。小笠原先生は「AIは言葉を計算できる計算機」と表現し、利用者の考えを計算に含められれば、それは自身の能力を拡張する道具になると説明しています。
今後、AIとの共生が当たり前になる時代において、AIを効果的に活用する力を養うことは重要です。AIバディを活用した学習は、その実践的なトレーニングの場となっています。学生は自分の考えを整理し、AIに伝えることで、自身の理解を深めています。
AIバディを通じた学習には、メタ認知能力(自分の思考プロセスを客観的に把握する能力)の向上も期待できます。学生は自分の理解度をAIとの対話を通じて確認し、足りない部分を補強する習慣が身につきます。
miiboが実現する教育の未来
miiboの「溶けこむAI」コンセプトは、教育現場でのAI活用に新たな可能性を開いています。京都芸術大学の事例は、AIが自然に学習環境に溶けこみ、教育効果を高める好例です。AIを敵視したり、過度に依存したりするのではなく、共に学び成長するパートナーとして位置づける視点は、これからのAI時代の教育モデルとして注目に値します。
株式会社miiboは学生からの要望に迅速に対応し、名前付け機能を実装するなど柔軟なサービス改善を行っています。このアジャイルな開発姿勢は、教育現場の多様なニーズに応える上で重要な強みとなっています。
AIバディのような学習支援システムは、個別最適化された教育の実現にも貢献します。学生一人ひとりの学習ペースや興味に合わせた支援が可能になり、多様な学習者に対応する柔軟な教育環境が構築できます。
今後も機能拡張が予定されており、教育分野でのmiiboの活用可能性は更に広がることが期待されます。音声対話機能の追加などにより、より自然なインターフェースでの学習支援が実現するでしょう。
AIと人間が共創する新しい教育モデル
京都芸術大学のAIバディ導入は、AIと人間が共に学び成長する新しい教育モデルの可能性を示しています。「溶けこむAI」としてのmiiboの特性が、教育現場でも効果的に活かされている事例といえるでしょう。
AIを単なるツールではなく、共に学ぶパートナーとして捉える視点は、これからのAI時代の教育において重要な示唆を与えています。miiboが実現する会話型AIの技術は、教育と技術の融合による新たな学びの形を創出していくでしょう。今後も教育分野におけるmiiboの活用事例から目が離せません。