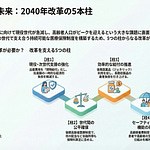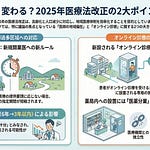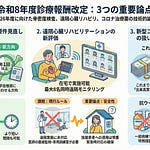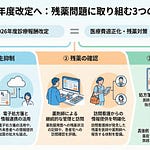令和7年度第13回入院・外来医療等の調査・評価分科会では、回復期リハビリテーション病棟入院料の評価体系について検討を行いました。この検討では、実績指数の除外基準に該当する患者が全体の86%に達している現状が明らかになりました。回復期リハビリテーション病棟の届出病床数は約9.5万床、届出機関数は1,620施設であり、直近10年で届出病床数が約1.4倍に増加しています。
分科会での議論では、実績指数の除外基準の見直し、重症患者割合と実績指数除外基準の重複問題、リハビリテーション単位数増加の効果の3点が主な論点となりました。実績指数の除外基準では「年齢が80歳以上」の該当割合が50%以上の施設が9割を超えている状況です。重症患者基準と実績指数除外基準の両方に該当する患者は、FIM運動項目では49.6%、FIM認知項目では85.9%でした。リハビリテーション単位数については、運動器リハビリテーション料と廃用症候群リハビリテーション料で7単位以上の提供ではFIM利得が比較的小さい結果が示されました。退院前訪問指導の実施率向上や高次脳機能障害患者への支援強化も課題として指摘されています。
実績指数の除外基準が抱える構造的問題
実績指数は回復期リハビリテーション病棟のアウトカム評価の指標です。この実績指数では、医療機関の判断で各月の入棟患者数の3割以下の範囲で除外できることとされています。除外が可能な要件には「年齢が80歳以上」「FIM運動項目20点以下」「FIM認知項目24点以下」などがあります。
除外基準の該当状況を見ると、「年齢が80歳以上」の該当割合が50%以上の施設が9割を超えています。いずれかの除外項目が該当する患者の割合が70%を超える施設は全体の86%に達しています。この状況について、分科会ではほぼ全ての患者が除外基準に該当している施設もあり、現行の基準で病棟の機能を正しく評価できているのか疑問であるとの意見が出されました。
「年齢が80歳以上」や「FIM認知項目24点以下」に該当する患者のFIM利得の分布は、患者全体と概ね同様でした。この結果から、これらの患者でもFIMが改善しないわけではないため、実績指数の計算対象から除外する必要性は乏しいのではないかとの意見がありました。一方で、FIM下位項目の得点が2点から3点に上がるのと5点から6点に上がるのでは自宅復帰への意味が異なる可能性があり、FIM利得には現れない効果を見落とさないよう評価を検討すべきとの指摘もありました。
重症患者割合と実績指数除外基準の重複が示す課題
回復期リハビリテーション病棟に入棟する患者の要件として、重症患者割合の要件が定められています。回復期リハビリテーション病棟1・2では重症患者割合が4割以上、3・4では3割以上とされています。令和6年5月から10月の実績では、回復期リハビリテーション病棟1・2における重症患者割合は約40から50%でした。
重症患者基準に該当する患者のうち、リハビリテーション実績指数の除外基準にも該当する患者の割合が高いことが明らかになりました。重症患者基準に該当する患者のうち、「FIM運動項目20点以下」にも該当する患者は49.6%、「FIM認知項目24点以下」にも該当する患者は85.9%でした。入棟時に「FIM運動項目20点以下」の患者は、脳血管疾患等リハビリテーション料と廃用症候群リハビリテーション料ではFIM利得が比較的小さい結果でした。
この重複について、分科会では重症患者と実績指数の除外基準両方に該当する患者が増えていることは理解できるものの、重複しないようにすると重症な患者も選別せずに入院を受け入れてほしいという当初の理念と食い違いが生じるため、慎重に検討すべきとの意見が出されました。
リハビリテーション単位数増加の効果検証
令和6年度改定では、回復期リハビリテーション病棟入院料または特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者で、運動器リハビリテーション料を算定するものについて、1日6単位までの算定とする見直しを行いました。この見直しは、運動器疾患に対する1日6単位を超えた実施単位数の増加に伴うADLの明らかな改善が見られなかったことを踏まえたものです。
運動器リハビリテーション料と廃用症候群リハビリテーション料において、7単位以上の提供ではFIM利得が比較的小さい結果でした。運動器リハビリテーション料については、改定前後で1日6単位を超えた算定は6割程度に減少しています。改定前に1日6単位を超えて実施した患者は、改定後に1日5から6単位実施した患者と比べ、FIM利得の上昇は少ない結果でした。
回復期リハビリテーション病棟における疾患別リハビリテーションの実施割合は、脳血管疾患等が54.3%、運動器が38.2%、廃用症候群が7.3%でした。廃用症候群リハビリテーションが実施された患者における医療資源を最も投入した傷病名としては、廃用症候群が55.0%で最も多い結果でした。分科会では、令和6年度改定後も運動器リハビリテーション料について6単位を超えて実施している患者が相当数いるが、単位数が増えてもFIM利得がほとんど変わっていないため、6単位を超えるリハビリを実施できる対象について分析を深めてはどうかとの意見が出されました。
質の高いリハビリテーション医療の推進に向けた取り組み
発症後の機能回復を図る上では、ベッド上等で行われる徒手でのアプローチのみでは不十分であり、他のアプローチと組み合わせた介入が重要です。入棟時のFIM運動項目が20点以下かつ要介護4、5の患者は、FIM21点以上や要介護4、5以外と比較し、患者1日当たりの平均リハビリテーション実施単位数は変わらないものの、運動項目のFIM利得が低い結果でした。
退院前訪問指導は回復期リハビリテーション病棟において包括されているものの、全入院患者の3から5%ほどに実施されており、その割合は他の病棟よりも高い状況です。各入院料を算定する施設において退院前訪問指導を実施している病院の割合は14から24%に留まっていました。退院前訪問指導はほとんどの施設で60分以上の実施時間を要しており、120分以上150分未満の割合が最も多い結果でした。具体的な実施内容として、家屋調査の他に外部との調整に係る項目も80%以上の病棟で行われていました。
高次脳機能障害者への支援に係る11の関係機関へのヒアリング調査では、入院医療機関における高次脳機能障害の診断や説明が不十分な場合があることや、支援に係る情報提供の不足、高齢者が多い病棟における障害福祉関連機関とのネットワークの希薄さ、退院時に相談窓口の情報を伝えることの重要性等について指摘がありました。令和6年診療報酬改定では、回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2について地域支援事業に参加していることが望ましいこととしており、令和6年11月1日時点で地域支援事業に参加している回復期リハビリテーション病棟は約70%でした。
生活機能の回復に資する診療報酬には排尿自立支援加算や摂食嚥下機能回復体制加算がありますが、回復期リハビリテーション病棟入院料の届出施設においては、これらの加算を届け出ている施設はそれぞれ24.2%、8.7%に留まっています。分科会では、退院前訪問指導は60分以上かけて行っている施設が9割を超えており、実施内容を踏まえた適切な評価方法について検討を進めるべきとの意見や、高次脳機能障害について特に就労支援に関してはかかりつけ医等との密な連携に対してより評価をすべきではないかとの意見が出されました。
まとめ
回復期リハビリテーション病棟入院料の評価体系には、実績指数の除外基準に該当する患者が全体の86%に達している課題、重症患者基準と実績指数除外基準が重複している課題、リハビリテーション単位数増加の効果が限定的である課題の3つの構造的問題があります。分科会では、これらの課題について除外基準の見直し、重症患者受け入れの理念との整合性の確保、リハビリテーション単位数上限の在り方の検討が必要との意見が出されました。退院前訪問指導の実施内容を踏まえた適切な評価方法の検討や高次脳機能障害患者への支援強化も今後の重要な論点となります。