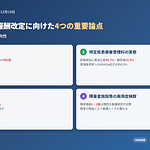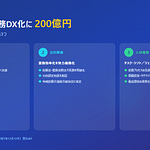外科系診療科における医師偏在と過重労働が深刻化する中、令和7年度第12回入院・外来医療等の調査・評価分科会は、診療科偏在対策の具体的な方向性を示しました。令和6・7年度入院・外来医療等における実態調査によると、心臓血管外科、消化器外科、脳神経外科では常勤医師1人あたりの時間外・休日労働時間が全診療科平均を大きく上回る実態が明らかになり、医師確保の困難さも内科43.7%、麻酔科32.8%、整形外科30.7%、外科27.1%と高い水準にあります。これらの課題に対し、山口大学の成功事例に代表される医療機関の機能分化による集約化と、手術の休日・時間外・深夜加算の施設基準見直しという2つのアプローチが注目されています。
本分科会の分析によれば、高度な手術の集約化により医療の質向上と医師の負担軽減を同時に実現できることが示されました。消化器外科領域では、年間50件未満の手術実施施設が大半を占める一方、大学病院本院の多くは200件以上を実施しており、すでに自然発生的な集約化が進んでいます。山口県の取り組みでは、医療機関を常勤消化器外科医師数に応じて3つのタイプに分類し、高度手術を基幹病院に集約する一方、術後の化学療法やフォローアップを地域の病院で実施する体制を構築しました。この機能分化により、基幹病院の医師の負担が軽減され、サテライト病院の経営改善も実現するという好循環が生まれています。
外科系診療科の労働実態と医師確保の現状
外科系診療科の時間外・休日労働時間は、全診療科平均を大きく上回る深刻な状況にあります。令和6・7年度入院・外来医療等における実態調査では、心臓血管外科、消化器外科、脳神経外科で特に常勤医師1人あたりの時間外・休日労働時間が長時間となっていることが明らかになりました。これらの診療科では、緊急手術や長時間手術が多く、オンコール体制による拘束時間も長いことが要因となっています。
医師確保の困難さも診療科によって大きな差があります。令和7年度の調査によると、内科では43.7%の施設が医師確保に困難を感じており、麻酔科32.8%、整形外科30.7%、外科27.1%と続きます。外科では大学医局からの派遣を受けている施設が38.2%あり、そのうち15.0%で派遣人員が減少していることが報告されています。有料の求人サービスを利用する施設も外科で7.9%、麻酔科で14.0%となっていますが、特に外科系診療科では効果が限定的です。
令和7年7月31日の中間とりまとめでは、若手医師の診療科選択にも偏りが生じていることが指摘されています。外科系診療科は専門性の習得に長期間を要し、身体的・精神的負担も大きいにもかかわらず、処遇が見合わないと感じる医師が増加しています。女性医師の増加に伴い、出産・育児との両立が困難な診療科は敬遠される傾向も強まっています。
手術加算の施設基準見直しによる働き方改革
手術の休日・時間外・深夜加算1の施設基準が令和6年度改定で強化されました。従来は交代勤務制、チーム制、手当支給のいずれかを満たせばよかったものが、交代勤務制またはチーム制の導入と手当支給の両方が必須となりました。この変更により、医師の休日確保と適切な処遇改善の両立が求められています。
新たな施設基準では、予定手術の術者・第一助手が前日に当直等を行った日数を年間4日以内に制限しています。交代勤務制では夜勤翌日を休日とし、チーム制では緊急呼び出し当番の翌日を原則休日とすることが義務付けられました。しかし、多くの施設でこれらの要件を満たすことが困難な状況です。
令和7年5月時点の調査では、手術の休日・時間外・深夜加算1を届け出ている192病院のうち、経過措置終了後に算定が困難となる要件として「緊急呼び出し当番翌日の休日対応」と「夜勤翌日の休日対応」を挙げる施設が最も多くなっています。オンコール体制の待機時間は労働時間に該当しない場合もありますが、施設基準では翌日の休日確保を求めており、医師確保が困難な施設では対応に苦慮しています。
山口モデルが示す機能分化と集約化の成功事例
山口大学医学部附属病院消化器外科が実践した機能分化モデルは、診療科偏在対策の有効な解決策を提示しています。このモデルでは、医療機関を常勤消化器外科医師数に応じて3つのタイプに分類し、それぞれの役割を明確化しました。Type1病院(常勤消化器外科医師1-2名)は基本的な手術のみ実施し、がん手術は大学病院に紹介する一方、術後の化学療法とフォローアップを担当します。
Type2病院(常勤消化器外科医師3-5名)は胃がん・大腸がんの標準的な手術を実施しますが、食道・肝胆膵の高難度手術は大学病院に集約します。Type3病院(常勤消化器外科医師6名以上)は従来通り独立してがん治療を完結できる体制を維持します。この機能分化により、各病院が強みを活かした診療体制を構築できました。
取り組みの結果、基幹病院では高度手術に専念できる環境が整い、医師の技術向上と負担軽減が実現しました。サテライト病院では、化学療法とフォローアップの症例数増加により経営が劇的に改善し、地域住民も近隣で継続的な治療を受けられるようになりました。この成功モデルは、他地域への展開可能性を示唆しています。
高度手術の集約化がもたらす医療の質向上
消化器外科領域の高度な手術(外保連試案の難易度D・Eかつ4時間以上)の実施状況分析から、自然発生的な集約化の実態が明らかになりました。令和4年度のNDBデータによると、全国2,017施設のうち年間50件未満の施設が過半数を占める一方、大学病院本院では200件以上実施する施設が大半となっています。この集約化により、手術成績の向上と若手医師の教育機会確保が両立されています。
集約化のメリットは手術の安全性向上だけではありません。症例数の増加により医療チームの技術が向上し、合併症率の低下や在院日数の短縮につながっています。また、高額な医療機器の効率的な活用や、専門スタッフの配置も可能となり、医療経済的にも合理的です。
中間とりまとめでは、過度な集約化による地域医療へのアクセス低下の懸念も指摘されました。分科会では、小規模な手術とのバランスを保ちながら、地域の実情に応じた集約化を進める必要性が強調されています。また、小規模施設から大規模施設への紹介・連携に対するインセンティブ強化も今後の検討課題となっています。
まとめ
外科系診療科の医師偏在と過重労働の解消には、医療機関の機能分化による集約化と、働き方改革を促進する診療報酬上の評価が不可欠です。山口モデルの成功は、地域全体で医療資源を最適配分することで、医療の質向上と医師の負担軽減を両立できることを実証しました。令和8年度診療報酬改定では、これらの取り組みを後押しする評価体系の構築が期待されます。