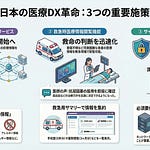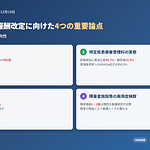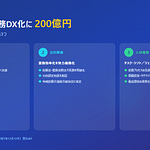入院・外来医療等の調査・評価分科会は、令和7年9月18日、透析医療の現状分析と課題検討を行いました。約34万人の慢性透析患者数が2022年から減少傾向に転じ、患者の平均年齢が70.1歳に達する中、透析医療の提供体制は大きな転換期を迎えています。血液透析に偏重した日本の腎代替療法の構造改革が求められています。
本報告書は、透析患者の高齢化と減少傾向、腎代替療法の選択肢提供の実態、災害対策と診療体制の課題という3つの重要な論点を提示しています。血液透析を実施する医療機関の19.5%しか腹膜透析を提供していない現状があります。全患者に腎代替療法の3つの選択肢を提示している施設は51.2%に留まります。災害時情報ネットワークへの登録率は76.1%となっています。これらの課題への対応が、今後の透析医療政策の重要な検討事項となります。
透析患者の現状と腎代替療法の選択肢
慢性透析患者数は343,508人(2023年末)で、2021年まで緩徐に増加していましたが、2022年から減少傾向に転じました。この減少傾向は、年間約3.9万人の新規導入があるものの、患者の高齢化による死亡数増加が背景にあります。患者の平均年齢は70.1歳、新規導入患者の平均年齢は71.6歳と、透析患者全体の高齢化が顕著です。
高齢化の進展は、腎代替療法の選択にも影響を与えています。日本では血液透析患者の割合が諸外国と比較して著しく高く、腹膜透析は10,585人、腎移植は年間2,001例に留まっています。腹膜透析は生活の制約や食事・飲水制限が血液透析より少なく、自由度が高いという利点があります。しかし、医療機関側の体制不備や経験不足が普及の障壁となっています。
腎代替療法に関する情報提供も不十分な状況です。全患者に血液透析、腹膜透析、腎移植の3つの選択肢を提示している医療機関は51.2%に過ぎません。35.6%の医療機関は情報提供の取組を行っていません。患者の自己決定権を保障し、最適な治療選択を支援する体制の構築が急務となっています。
診療体制の課題と災害対策の現状
血液透析の診療体制には、複数の課題が顕在化しています。シャント閉塞等のトラブルは透析患者の入院理由として最も多く、93.6%の医療機関が自院または事前連携先で対応しています。しかし、5.9%の医療機関は事前連携のない医療機関への紹介となっており、緊急時対応の体制整備が必要です。
災害対策については、各医療機関の取組にばらつきが見られます。災害対策マニュアルの策定は80.5%の施設で実施されていますが、電源車や給水車の受入体制は22.9%に留まります。日本透析医会災害時情報ネットワークへの登録または自治体等との連携体制を確保している医療機関は76.1%です。大規模災害時の透析医療継続には、より包括的な対策強化が求められます。
腹膜透析の提供体制も大きな課題です。血液透析実施医療機関の77.1%が腹膜透析を提供していません。その理由として、対象患者がいない(59.5%)、器具設備の不備(38.6%)、医師の経験不足(18.4%)が挙げられています。緊急時や入院時のバックアップ体制への不安も、腹膜透析導入の障壁となっています。
診療報酬による政策誘導と今後の方向性
診療報酬制度は、腎代替療法の適切な選択を促進する重要な政策ツールです。導入期加算は、腎代替療法に関する十分な説明と選択支援を評価し、200点から810点の3段階で設定されています。腎代替療法実績加算(100点)は、腹膜透析や腎移植の実績を評価する仕組みです。
慢性維持透析の施設基準は、透析用監視装置の台数と患者数の割合により3つに区分されています。慢性維持透析1の届出医療機関数は増加傾向(令和6年:2,358施設)にある一方、慢性維持透析2・3は減少しています。この変化は、医療機関の規模や効率性を反映した診療報酬体系への適応を示しています。
緩和ケアの取組も重要な検討事項です。医療用麻薬を用いた疼痛緩和を実施している医療機関は32.2%、終末期や透析医療中止に関する意思決定支援は35.1%に留まっています。超高齢社会における透析医療では、治療の継続と中止、緩和ケアへの移行を含めた包括的な医療提供体制の構築が不可欠となっています。
まとめ
透析医療は、患者数の減少と高齢化により大きな転換期を迎えており、血液透析偏重から腎代替療法の選択肢拡大への構造改革が必要です。診療体制の強化、災害対策の充実、腹膜透析の普及促進という3つの課題への対応が、今後の透析医療政策の重要な検討事項となります。診療報酬制度を通じた政策誘導と、医療機関の体制整備支援により、患者中心の透析医療への転換を推進することが求められています。