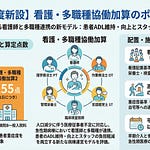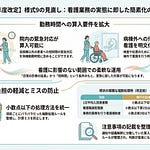令和7年11月20日、第204回社会保障審議会医療保険部会が開催されました。この部会では、食材費や光熱水費の継続的な高騰を受けて、入院時の食費と光熱水費の標準負担額の見直しについて議論されました。入院時の食費については、令和6年6月と令和7年4月に計50円の引上げを実施したにもかかわらず、令和7年4月以降も物価高騰が続いています。入院時の光熱水費については、平成18年の制度創設時から基準額(総額)が据え置かれており、昨今の光熱水費の大幅な高騰により病院経営に影響を及ぼしています。
この見直しは、患者の負担と病院経営の両立という観点から進められています。入院時の食費では、令和7年4月以降も食材費等の高騰が続いており、更なる標準負担額の見直しが検討されています。入院時の光熱水費では、令和6年度介護報酬改定で多床室の居住費が60円引き上げられたことにより、介護保険の居住費と医療保険の光熱水費の間で負担額に差が生じています。中央社会保険医療協議会でも、基準額(総額)の観点から並行して議論が進められており、患者負担への影響を慎重に検討する必要があります。
入院時の食費をめぐる現状と課題
入院時の食費は、令和6年6月に1食当たり30円、令和7年4月に1食当たり20円の計50円が引き上げられました。この見直しは、食材費等の高騰に対応するために実施されたものです。しかし、令和7年4月以降も食材費等の高騰は続いており、医療機関の経営を圧迫している状況が明らかになっています。
この見直しに伴い、医療機関は給食提供体制の変更を余儀なくされました。全面委託を行っている医療機関では、約5割が「給食委託費を増額した」と回答しています。一部委託や完全直営の医療機関では、約5割が「給食の内容を変えて経費の削減を行った(食材料を安価なものに変更等)」と回答しています。
さらに、令和6年6月以降、全面委託の約7割、一部委託の約5割の医療機関では、委託事業者から値上げの申し出がありました。これらの医療機関は、委託事業者との契約変更に対応しています。完全直営の医療機関では3.6%(22施設)が、給食運営を委託から完全直営に切り替える対応を取っています。
これらの状況を踏まえ、社会保障審議会医療保険部会では、更なる入院時の食費の標準負担額の見直しについて検討が進められています。中央社会保険医療協議会においても、食費の基準額(総額)の観点から並行して議論されています。
入院時の光熱水費をめぐる現状と課題
入院時の光熱水費は、平成18年に入院時生活療養費制度が創設されて以来、基準額(総額)が据え置かれています。この基準額は398円(1日当たり)で設定されており、18年以上変更されていません。一方で、昨今の光熱・水道費は特に足下で大きく高騰しており、病院経営に少なからず影響を及ぼしている状況です。
入院時の光熱水費は、療養病床に入院する65歳以上の者について入院時生活療養費の光熱水費として評価されています。一般所得者の場合、1日当たりの総額398円のうち、自己負担額は370円、保険給付額は28円です。一般病床、精神病床、療養病床に入院する65歳未満の者については、入院料の中で評価されています。
平成29年10月と平成30年4月には、介護保険の居住費に係る基準費用額を勘案して、自己負担額の段階的な引上げが行われました。この見直しでは、基準額(総額)を維持した上で、医療区分Ⅰの者の自己負担額を320円から370円に引き上げました。医療区分ⅡⅢの者の自己負担額も、0円から200円、その後370円へと段階的に引き上げられました。
しかし、これらの見直し後も光熱水費の高騰は続いており、基準額(総額)の据え置きが病院経営を圧迫する要因となっています。中央社会保険医療協議会においても、基準額(総額)の観点から議論が進められています。
介護保険との負担格差と均衡の必要性
介護保険では、令和6年度介護報酬改定において、多床室の居住費の基準費用額・負担限度額が60円引き上げられました。この見直しは、令和4年の家計調査によれば高齢者世帯の光熱・水道費が令和元年家計調査に比べて上昇していることを踏まえたものです。在宅で生活する者との負担の均衡を図る観点や、令和5年度介護経営実態調査の費用の状況等を総合的に勘案して実施されました。
この見直しにより、介護保険の居住費と医療保険の光熱水費の間で負担額に差が生じています。介護保険では、全ての居室類型で1日当たり60円分が増額されました。従来から補足給付の仕組みにおける負担限度額を0円としている利用者負担第1段階の多床室利用者については、負担限度額を据え置き、利用者負担が増えないように配慮されています。
健康保険法第85条の2では、入院時生活療養費の額を定める際、介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案することが規定されています。介護保険法第51条の3第3項では、厚生労働大臣は居住費の基準費用額を定めた後に、施設における居住等に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにそれらの額を改定しなければならないとされています。
こうした法的な枠組みを踏まえ、社会保障審議会医療保険部会では、近年の光熱・水道費の高騰を踏まえた対応を行う観点から、入院時の光熱水費の標準負担額の見直しについて議論が進められています。家計における光熱・水道支出を勘案して行われた令和6年度介護報酬改定による多床室の居住費の基準費用額の引上げを踏まえた対応が検討されています。
今後の議論の方向性と患者負担への影響
入院時の食費と光熱水費の見直しは、社会保障審議会医療保険部会と中央社会保険医療協議会の両方で並行して議論が進められています。社会保障審議会医療保険部会では、標準負担額(患者の自己負担額)の見直しが論点となっています。中央社会保険医療協議会では、基準額(総額)の観点から技術的な検討が行われています。
入院時の食費については、令和6年6月と令和7年4月の2回の見直し後も、引き続き食材費等の高騰が続いている状況を踏まえた更なる見直しが検討されています。医療機関では、委託事業者からの値上げ申し出への対応や、給食内容の変更による経費削減など、様々な対応が取られています。患者の栄養管理の質を維持しながら、持続可能な給食提供体制を構築することが課題となっています。
入院時の光熱水費については、近年の光熱・水道費の高騰を踏まえた対応が検討されています。家計における光熱・水道支出を勘案して行われた令和6年度介護報酬改定により、介護保険では居住費が60円引き上げられました。この引上げを踏まえ、医療保険における光熱水費についても見直しが論点となっています。病院経営の持続可能性を確保しながら、患者の負担増を最小限に抑える方策が求められています。
これらの見直しが実施される場合、入院患者の自己負担額が増加する可能性があります。特に、長期入院を要する患者や、住民税非課税世帯などの低所得者層への影響に配慮した制度設計が重要です。高額療養費制度や、指定難病患者への医療費助成、こども医療費助成などの各種医療費助成制度との整合性も考慮する必要があります。
まとめ
令和7年11月20日の第204回社会保障審議会医療保険部会では、入院時の食費と光熱水費の標準負担額の見直しについて議論されました。入院時の食費は、令和6年6月と令和7年4月に計50円の引上げを実施したにもかかわらず、物価高騰が続いており、更なる見直しが検討されています。入院時の光熱水費は、平成18年の制度創設時から基準額が据え置かれており、令和6年度に介護保険の居住費が60円引き上げられたことを踏まえた対応が論点となっています。今後、中央社会保険医療協議会での技術的な検討も踏まえながら、患者負担と病院経営の両立を目指した制度改革が進められていきます。