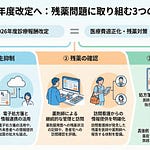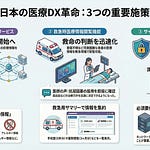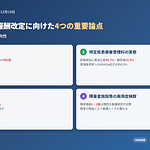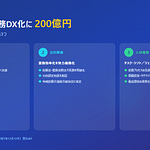令和7年9月18日に開催された中央社会保険医療協議会の入院・外来医療等の調査・評価分科会において、災害医療に関する包括的な調査結果が報告されました。日本の災害医療体制は783の災害拠点病院と1,840のDMATチームを中心に構築されていますが、能登半島地震での実際の派遣経験から、職員の配置基準維持や現地情報収集などの運用面での課題が浮き彫りになりました。
本報告では、災害拠点病院の整備状況とDMATの活動実態、能登半島地震における医療機関の対応状況、新型コロナウイルス感染症対応での施設基準の弾力的運用という3つの観点から、現在の災害医療体制の到達点と今後の改善方向を示します。特定機能病院の92.6%が能登半島地震への派遣を検討し、急性期一般入院料1算定病院の68.4%が検討したという結果は、高度急性期医療機関が災害医療の中核を担っている実態を明確に示しています。診療所における事業継続計画(BCP)策定率が約30%にとどまることや、派遣時の職員配置基準の課題など、医療提供体制全体として取り組むべき課題も明らかになりました。
災害拠点病院とDMAT体制の整備状況
日本の災害医療体制は、平成8年から整備が始まった災害拠点病院を中心に構築されています。災害拠点病院は、基幹災害拠点病院(都道府県に原則1箇所、全国63病院)と地域災害拠点病院(二次医療圏に原則1箇所、全国720病院)の2層構造で、令和7年4月1日までに計783病院が指定されています。
この災害拠点病院を支えるDMAT(災害派遣医療チーム)は、平成17年3月から養成が開始され、現在18,909名、1,840チームが研修を修了しています。DMATは医師1名、看護師2名、業務調整員1名の4名を基本として構成され、都道府県の派遣要請に基づいて活動します。令和4年2月には、新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、新興感染症等のまん延時における対応も活動内容に追加されました。
各入院料区分別の災害派遣医療チーム設置状況を見ると、特定機能病院が90.7%と最も高く、次いで急性期一般入院料1算定病院が59.1%となっています。高度急性期医療を担う医療機関ほど災害医療体制への参画率が高い傾向が明確に表れています。DPC/PDPS対象病院では、災害拠点病院の指定、DMATの指定、EMISへの参加、BCPの策定が体制評価指数として診療報酬上も評価される仕組みとなっています。
能登半島地震における医療機関の派遣実態と課題
令和6年能登半島地震への対応では、医療機関の規模や機能による派遣検討・実施の差が顕著に現れました。派遣を検討した医療機関の割合は、特定機能病院92.6%、急性期一般入院料1算定病院68.4%、専門病院50.0%の順となり、実際に派遣した割合も同様の傾向を示しました。
派遣検討時の主な困難要因として、「現地の状況把握と情報収集」「派遣にあたっての交通手段の確保」「派遣中の労務管理」「派遣中に自施設のスタッフ配置基準が満たせなくなること」が挙げられました。これらの課題は、災害発生時の初動体制や情報共有システム、労務管理体制の整備が急務であることを示しています。特に、職員配置基準の問題は、平時の医療提供体制維持と災害支援のバランスという構造的な課題を浮き彫りにしています。
実際に派遣された職種は、看護師が最も多く(急性期一般1で94.4%、特定機能病院で100%)、次いで医師(急性期一般1で81.5%、特定機能病院で94.2%)、事務職員、薬剤師の順でした。災害医療においても、看護師と医師を中心とした多職種チームによる支援体制が機能していることが確認されました。
新型コロナウイルス感染症対応と施設基準の弾力的運用
新型コロナウイルス感染症への対応においても、医療機関間の支援体制が重要な役割を果たしました。他の医療機関や福祉施設への職員派遣を検討した医療機関は、特定機能病院46.3%、急性期一般入院料1算定病院43.2%と、能登半島地震への対応と比較すると低い割合でしたが、長期間にわたる支援が継続されました。
派遣検討時の困難要因は、「派遣中に自施設のスタッフ配置基準が満たせなくなること」が最も多く、次いで「現地の状況把握と情報収集」「派遣中の労務管理」が挙げられました。能登半島地震と異なり、交通手段の問題は少なかった一方で、長期派遣による自施設の人員不足がより深刻な課題となりました。
これらの課題に対応するため、厚生労働省は施設基準の弾力的運用を認める事務連絡を発出しています。新型コロナウイルス感染症患者の受け入れや職員派遣により、月平均夜勤時間数や看護要員数に1割以上の変動があった場合でも、最初の月から3か月以内に限り施設基準の届出区分変更を不要とする特例措置が設けられました。この措置は当初令和6年5月31日までとされていましたが、活用状況を踏まえて令和8年5月31日まで延長されています。
まとめ
日本の災害医療体制は、783の災害拠点病院と1,840のDMATチームを中心に着実に整備が進んでいます。能登半島地震と新型コロナウイルス感染症対応の経験から、高度急性期医療機関が災害医療の中核を担う体制が機能していることが確認されました。一方で、職員派遣時の配置基準維持、現地情報収集、労務管理などの運用面での課題や、診療所のBCP策定率が約30%にとどまるなど、医療提供体制全体としての備えには改善の余地があります。今後は、施設基準の弾力的運用の恒久化や、情報共有システムの強化、中小医療機関のBCP策定支援など、実践的な課題への対応が求められています。