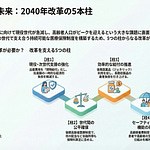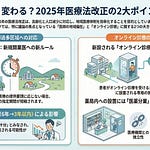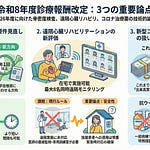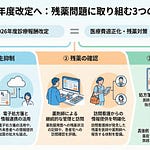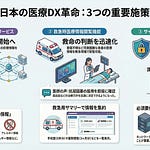令和6年度診療報酬改定後、地域包括医療病棟等への病棟再編によりDPC対象病院数は減少しています。DPC対象病院の構造は変化しており、全許可病床に占めるDPC算定病床の割合が50%未満の病院が増加傾向にあります。このような状況の中、DPC制度の適正化と急性期入院医療の評価見直しが求められています。
入院・外来医療等の調査・評価分科会は、DPC制度に関する5つの重要課題について検討結果をまとめました。複雑性係数については入院初期を重視した評価方法への見直しが提案されました。再入院・再転棟ルールと持参薬ルールについては、制度の趣旨を徹底するための厳格化が検討されました。点数設定方式については、平均在院日数から中央値への移行が提案されました。特別調査からは、DPC制度からの退出を検討する医療機関の実態や、制度参加のメリットが明らかになりました。
機能評価係数Ⅱの評価方法見直し|入院初期を重視した複雑性係数へ
複雑性係数の評価方法については、現行制度における課題が明らかになりました。診療対象とする診断群分類の種類が少ない病院で、誤嚥性肺炎等の平均在院日数が長く、1日当たり包括範囲出来高点数の小さい疾患に偏った症例構成の場合、急性期入院医療における評価として不適当な結果となっていました。
この課題に対し、DPC/PDPS等作業グループは重要な指摘を行いました。DPC制度における「急性期」は「患者の病態が不安定な状態から、治療によりある程度安定した状態に至るまで」と定義されています。機能評価係数は「急性期」を反映する係数として設計されています。複雑性係数についても、これらの価値を反映する指標とすべきです。
作業グループは、入院初期を特に重視する趣旨で、入院日数の25%tile値までの包括範囲出来高点数により評価すべきではないかと指摘しました。一入院当たりの包括範囲出来高点数が高い診断群分類の中には、平均的に入院初期の包括範囲出来高点数が高い診断群分類もあれば、1日当たりの包括範囲出来高点数が全診断群分類の平均値及び中央値よりも低い診断群分類もみられました。この実態を踏まえ、より適切な評価方法への見直しが求められています。
地域医療係数については、大学病院本院群における医師派遣の評価が検討されました。「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」において、特定機能病院が満たすべき「基礎的基準」として「地域に一定の医師派遣を行っていること」を設定することが議論されています。作業グループは、地域医療係数における派遣医師数の定義を、特定機能病院の基礎的基準における医師派遣の定義と整合的に検討すべきではないかと意見を述べました。
再入院・再転棟ルールの見直し|8日目の再転棟が突出する実態への対応
DPC制度は、入院初期を重点評価するため、入院期間Ⅰの1日当たりの点数を相対的に高く設定しています。この設定に対し、患者を短期間で退院・再入院させ、単価の高い入院期間Ⅰを繰り返し算定する事例への対応が課題となっていました。
現行制度では、一定の条件を満たす再入院及び再転棟については一連の入院とみなすこととし、累次の改定を行ってきました。DPC病棟からの転棟後、再転棟までの日数の分布を分析したところ、DPC制度において一連の入院と見なされなくなる8日目の再転棟の件数が突出して多いことが明らかになりました。
作業グループは、この実態に対する見解を示しました。DPC制度を構成する医療機関の内訳が変化しており、DPC算定病床以外の病床を有する医療機関の割合が増加しています。この構造変化により、「再転棟」が起こりやすい状況になっているのではないかという指摘がありました。
作業グループは、同一傷病による再転棟については、転棟後7日間を超える場合であっても原則として一連の入院として扱うこととすべきではないかとの意見を述べました。この提案は、制度の趣旨に沿った適正な運用を確保するための重要な見直しとなります。
持参薬ルールの周知徹底|算定ルール違反への対応強化
DPC制度では、患者の負担軽減やDPC制度下での公平な支払いの観点等を踏まえ、入院中の患者に対して使用する薬剤は入院する病院において入院中に処方することが原則です。「入院の契機となった傷病」に対する持参薬の使用は、特別な理由がある場合を除き認められていません。
実態調査の結果、制度の趣旨が十分に徹底されていない状況が明らかになりました。医療機関ごとの全症例数に占める持参薬を使用した症例数の割合を分析したところ、持参薬使用割合が5%未満の医療機関が最も多かったものの、55%以上60%未満の医療機関も一定数みられました。
入院の契機となった傷病に対する持参薬使用割合の分析では、算定ルール上認められていない入院の契機となった傷病に対する持参薬の使用割合が5%以上となる医療機関が一定数みられました。自院の外来で処方した医薬品を入院の契機となった傷病に対して使用した割合が5%以上となる医療機関も一定数存在していました。
作業グループは、現行ルールの更なる周知徹底を図るべきではないかと指摘しました。具体的には、DPC算定を行う場合は入院の契機となった傷病に対して使用する医薬品は院内で処方されるのが原則であること、DPC算定を行う場合の入院料の中には一般的に入院の契機となった傷病に対して使用する医薬品の薬剤料が含まれていることについて、患者への説明を求めるべきではないかとの意見がありました。
「入院の契機となった傷病」以外の傷病に対する持参薬の使用の可否については、令和10年度診療報酬改定に向けて引き続き議論する必要があります。検討に当たっては、まず持参薬を使用する理由や、使用される頻度が高い持参薬及び診断群分類等について調査を行う必要があるのではないかとの意見がありました。
点数設定方式の変更|平均在院日数から中央値への移行を検討
DPC制度は、入院初期を重点評価するため、在院日数に応じた3段階の定額報酬を設定しています。入院初期に要する医療資源投入量等に応じて、5種類の点数設定方式を設けています。点数設定方式D以外においては、第Ⅱ日は平均在院日数により規定されています。
診断群分類毎の平均在院日数について分析したところ、ばらつきが小さく標準化が進んでいる診断群分類がみられました。一方で、ばらつきが大きく十分に標準化が進んでいない診断群分類もみられました。特定の在院日数のみ患者数が顕著に多い診断群分類が存在していました。多くの診断群分類において、平均在院日数は在院日数の中央値を上回っていました。
作業グループは、多くの診断群分類で在院日数の分布は正の歪度を有していることから、在院日数の中心傾向の指標として平均在院日数は適切でないのではないかと指摘しました。特定の在院日数の患者数が顕著に多い診断群分類について、制度上、特定の日数までの在院を促すインセンティブが内在しているのではないかとの意見がありました。
この指摘に対し、1日当たり入院数の最大値に対する日ごとの入院数の割合の変動係数が著しく低い医療機関が一定数存在していることを踏まえた意見もありました。病床稼働率を過度に重視した病院経営を行うと、病床の活用が硬直的になり、柔軟な対応をできなくなります。必ずしも高い病床稼働率を維持しなくてもよい設計とすべきではないかとの意見です。
作業グループは、点数設定方式における入院期間Ⅱについて、在院日数の標準化が進んでいる診断群分類を中心として、原則として平均在院日数から在院日数の中央値に移行すべきではないかとの意見を述べました。一方で、入院期間Ⅱを在院日数の中央値に移行した場合、一部の診断群分類では入院期間Ⅱが著しく変化しうることから、激変緩和措置を設けるべきではないかとの意見もありました。
特別調査が明らかにしたDPC制度の実態|退出検討と参加意向
特別調査として、在院日数の短縮に向けた取り組みや課題等に関する調査、DPC制度の安定的な運用に関する調査、急性期医療の標準化の推進に関する調査を実施しました。DPC制度の安定的な運用に関する調査については、作業グループにおいてヒアリングを行いました。
在院日数の短縮に向けた取り組みや課題等に関する調査では、全DPC対象病院の約9割においてクリニカルパスが採用されていることが分かりました。クリニカルパスの入院期間の設定に際して主として参照しているものについては、約6割の医療機関が「診断群分類点数表上の第Ⅱ日」と回答しました。この結果は、点数設定方式が医療機関の診療行動に影響を与えていることを示しています。
DPC制度の安定的な運用に関する調査では、データ数が下位25%の439医療機関のうち、約2割の医療機関がDPC制度からの退出について「直ちに退出する予定である」または「直ちにではないが、今後退出を検討している」と回答しました。このうち約4割の医療機関が病床の転換を予定しており、転換先としては「地域包括医療病棟」及び「地域包括ケア病棟」が多い結果となりました。
DPC制度に参加したメリットとしては、医療の標準化や平均在院日数の短縮といった点が挙げられました。この結果は、DPC制度が医療の質向上に一定の効果をもたらしていることを示唆しています。
急性期医療の標準化の推進に関する調査では、DPC算定可能病床を有する出来高算定病院におけるDPC制度への参加意向を調査しました。調査対象となった404医療機関のうち、「現時点で参加は検討していない」と回答した医療機関は約86%でした。その理由としては、「DPC制度に参加する必要性を感じないため」が最も多く、次いで「診療報酬の算定上、DPC制度に参加しない利点が大きいため」が多い結果となりました。
まとめ
入院・外来医療等の調査・評価分科会は、DPC制度の5つの重要課題について検討結果をまとめました。複雑性係数は入院初期を重視した評価方法への見直しが提案されました。再入院・再転棟ルールと持参薬ルールについては、制度の趣旨を徹底するための厳格化が検討されました。点数設定方式は、平均在院日数から中央値への移行が提案されました。特別調査からは、DPC制度の実態と課題が明らかになりました。これらの検討結果は、令和8年度診療報酬改定に向けた議論の基礎となります。