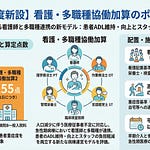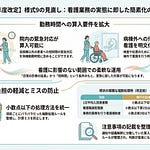企業が直面する深刻な課題として、ベテラン社員の退職・異動による経験知の喪失があります。人手不足で引き継ぎ時間が取れず、マニュアルに載らない暗黙知が失われ続けている現状を、AIによる知識継承システムで解決する方法があります。
本記事は、株式会社miiboと株式会社こころみが開催した「AIエージェント構築実践セミナー第18弾 ~ベテラン社員のノウハウを継承したAIを作る~」の内容をまとめたものです。会話型AI構築プラットフォーム「miibo」を活用し、ベテラン社員のノウハウを効果的にAIに継承する実践的な方法を、ディープリスニングによる暗黙知の引き出しから、AIフレンドリーなデータ構造化、RAGを活用した実装、そして社内展開まで、3つのステップで解説します。
なぜ今、ノウハウ継承AIが必要なのか
ベテラン社員が持つ知見を社内に引き継ぐことなく退職してしまうケースが増加しています。培われたノウハウがマニュアルやFAQとして形式知化されることは稀で、多くの暗黙知がそのまま失われ、企業にとって大きな損失となっています。
人に引き継ぐ場合でも、人手不足により引き継ぎの工数が確保できないという問題があります。さらに、人に引き継いでも再び属人化してしまうリスクが存在し、根本的な解決にはなりません。AIに学習させることで、いつでも利用可能で、何百人でも同時にアクセスできる知識資産として活用できるようになります。
従来のマニュアルやWebサイトにナレッジを蓄積する方法と比較して、会話型AIは質問すれば自然に回答を返してくれるため、多くの人にとって使いやすいシステムとなります。特にmiiboを活用することで、ノーコードで簡単に構築でき、様々なLLMを切り替えて利用できる柔軟性を持った継承型AIを実現できます。
ステップ1:ディープリスニングでノウハウを引き出す
ベテラン社員のノウハウを効果的に引き出すためには、単に質問するだけでなく、信頼関係を構築しながら話を聞き出すディープリスニングという手法が有効です。この手法では、相手との心理的安全性を保ち、何でも話せる状況を作ることを重視します。
社内の人間がインタビューする場合、利害関係や部署間の問題により全てを話してもらえない可能性があります。外部の専門インタビュアーが実施することで、より本音に近い情報を引き出すことができます。インタビュー設計では、ノウハウだけでなく、その方の略歴、思い、悩みなどの背景情報も含めて聞くことで、信頼関係を構築していきます。
特に重要なのは「どういう状況のときに、どういう行動をとって、どういう結果になったのか」という状況・行動・結果の流れで聞くことです。感情の部分(共感的理解)とロジカルな部分(論理的理解)の両方を引き出すことで、単なる手順だけでなく、判断の背景にある考え方まで抽出できます。株式会社こころみでは、このディープリスニング手法を用いて、ベテラン社員から「丁寧に聞いていただいて、組織文化や過去の経緯まで理解してもらえた」「内部スタッフでは聞けなかった内容まで話せた」という評価を得ています。
ステップ2:AIフレンドリーなデータ構造化
引き出したノウハウをAIが学習しやすいデータ構造に変換することが、継承型AI構築の要となります。ノウハウの種類によって適したまとめ方が異なり、AIが検索しやすく、理解しやすく、出力しやすい構造にする必要があります。
哲学や仕事観などの抽象度の高い内容は、Markdown形式の文章で記述します。見出しをシャープ記号(#)で階層化し、箇条書きをハイフン(-)で表現することで、情報の構造が明確になり、AIが理解しやすくなります。判断基準やルールについても同様に、構造的な文章として整理します。
手順や業務プロセスなどフローチャートで表現される内容は、YAMLやMermaid形式で記述します。これらの形式では、条件分岐や次のステップを明確に定義でき、「AのプロセスからBへ、Bで条件分岐してCかDへ」といった流れをテキストで表現できます。例えば経費精算プロセスのような複雑な業務フローも、AIが理解可能な形式に変換できます。
体の動きや作業の技など、テキスト化が困難なノウハウは動画として記録します。動画のURLと共に、内容の詳細な説明文を付加することで、AIが適切なタイミングで「この動画を参考にしてください」と提案できるようになります。Google AI Studioなどのツールを活用すれば、動画の内容を自動的にテキスト化することも可能です。
ステップ3:miiboでRAGを活用した実装
構造化されたデータは、miiboのナレッジデータストアに格納し、RAG(Retrieval-Augmented Generation)の仕組みを活用して実装します。RAGにより、ユーザーの質問に対して関連する知識を検索し、その結果を基にAIが適切な回答を生成できるようになります。
miiboでのRAG実装の流れは、まずユーザーが発話すると検索クエリーが生成され、設定した外部データに対して検索が実行されます。検索結果の上位が前提データプロンプトに追加され、その情報を基にAIが応答を生成します。この仕組みにより、正確な情報へのアクセスが可能になり、エビデンスを示しやすくなります。
ナレッジデータストアへのデータ登録は、自由入力、URL指定、ファイルインポート、CSV形式でのインポート、Notionページからの入稿、API経由での登録など、多様な方法が用意されています。登録されたデータはEmbedding(ベクトル化)され、類似度に基づいて検索されるため、ユーザーの質問に最も関連性の高い情報が抽出されます。
検索精度を高めるために、チャンクの制御、カスタムフィールドの活用、検索モードの設定などの工夫が可能です。全文検索モード、ミックス検索モード、ハイブリッド検索モードから、用途に応じて最適なモードを選択することで、より精度の高い情報検索を実現できます。
社内展開と活用シーンの設計
作成したAIを社内で効果的に活用するためには、使いやすい環境への実装が不可欠です。SlackやMicrosoft Teamsなどの社内チャットツールに統合することで、日常業務の中で自然にAIを利用できるようになります。
社内ポータルサイトへの組み込みや、miibo Agent Hubのような社内AIプラットフォームの活用も効果的です。miibo Agent Hubでは、複数のAIエージェントを集約し、必要に応じて組み合わせて利用することも可能です。これにより、ベテラン社員のノウハウAIだけでなく、人事部の問い合わせ対応AIやマーケティング担当AIなど、様々なAIを一元管理できます。
具体的な活用シーンとしては、ベテラン社員の退職時のノウハウ継承、優秀な社員のスキルの全社展開、一時的な不在時の業務引継ぎ、夜間・休日の判断支援、若手社員のOJTや社内研修での活用、マニュアルに載っていない裏技や例外処理の共有などがあります。これらの活用により、社内の知識資産を効率的に共有・活用できるようになります。
運用と継続的な改善
継承型AIの運用では、ログ分析とユーザーフィードバックの収集が重要になります。miiboの会話ログ機能を活用することで、どのような質問に対してどのような回答がされたか、使われた知識は何かを詳細に確認できます。
精度向上のためには、間違った回答の原因分析が必要です。検索クエリーの問題、必要な情報の不足、矛盾する情報の存在など、様々な要因を特定し、改善していきます。MCPという機能を使えば、ユーザーが「この回答はおかしい」とフィードバックした際に、その情報を自動的に収集し、改善に活用できます。
社内教育の観点では、AI活用のワークショップ開催、定期的な研修、社内推進役の育成などが効果的です。miiboはノーコードで操作できるため、プログラマーでなくても使いこなせる人材を育成し、継続的な改善サイクルを回すことが可能です。
まとめ
ベテラン社員のノウハウを継承したAIの構築は、聞く力(ディープリスニング)、構造化(AIフレンドリーなデータ形式)、実装(使いやすい環境の構築)の3つのステップで実現できます。本セミナーで紹介された手法を活用することで、miiboを使ったノーコードでの継承型AI構築が可能になり、企業の知識資産として活用できるようになります。暗黙知の形式知化により、属人化を防ぎ、組織全体の意思決定力を底上げすることで、持続可能な組織づくりに貢献できるのです。