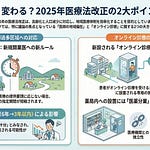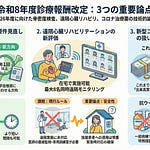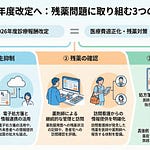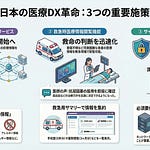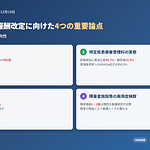医療現場では計画書作成やDPCデータ入力などの事務負担が深刻な問題となっており、令和7年度の調査では施設の44.2%が計画書作成の簡素化を、38.2%がDPCデータ作成の簡素化を求めています。これに対し、令和2年度から6年度にかけての累次の診療報酬改定により、ICT活用による会議の効率化、記録・届出事務の簡素化、レセプト業務の改善など、段階的に業務簡素化が進められてきました。さらに令和7年度に向けて、規制改革推進会議の答申に基づき、署名・押印要件の廃止など、より抜本的な改革が検討されています。
これまでの改定により実現した主な成果として、会議のオンライン化、研修の統合実施、添付資料の削減という3つの大きな改善があります。特に病棟においては61.8%が計画書作成の簡素化を、45.1%が患者・家族の署名・記名押印の簡素化を必要としており、これらの声を受けて更なる改革が進行中です。今後は施設基準届出の完全電子化、署名・押印の原則廃止、DPCデータ入力項目の更なる精査により、医療従事者が本来の診療業務により多くの時間を割けるようになることが期待されています。
令和2年度改定で実現した会議・研修の効率化
令和2年度診療報酬改定により、安全管理責任者等で構成される会議について、責任者が必ずしも対面でなくてもよいと判断した場合、ICTを活用した対面によらない方法での開催が可能となりました。この変更により、多忙な医師や管理者の時間調整が容易になり、会議の開催頻度や参加率の向上が実現しています。医療機関では、Web会議システムの導入により、場所や時間の制約から解放され、より柔軟な会議運営が行われています。
院内研修においても効率化が図られました。抗菌薬適正使用支援加算に係る院内研修を院内感染対策研修と併せて実施できることが明確化され、重複する内容の研修を統合することが可能となりました。急性期看護補助体制加算等の看護補助者に係る院内研修の要件も見直され、より実践的で効率的な研修体系が構築されています。
院外研修の指導者要件についても柔軟性が増しています。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の院内研修の指導者に係る要件が見直され、医療機関の実情に応じた研修体制の構築が可能となりました。これらの改革により、研修に係る時間的・人的負担が軽減され、医療従事者の働き方改革に貢献しています。
令和4年度改定における記録・届出事務の簡素化
令和4年度改定では、診療録への記載要件が大幅に見直されました。栄養サポートチーム加算注2等については、栄養治療実施計画の写しを診療録に添付すれば良いこととなり、従来求められていた詳細な記載を省略できるようになりました。在宅療養指導料等についても、医師が他の職種への指示内容を診療録に記載する必要がなくなり、チーム医療の効率化が図られています。
施設基準の届出においては、研修修了証の写し等の添付資料が削減されました。訪問看護ステーションの基準に係る届出については、適合性に影響がない場合の届出が不要となり、事務処理が効率化されています。小児科外来診療料等の施設基準については、令和4年度改定により届出自体が省略可能となりました。
レセプト摘要欄の記載方法も改善されました。薬剤等について選択式記載が導入され、従来の自由記載から簡素化が進みました。これにより記載ミスの削減と事務処理時間の短縮が実現し、医療事務職員の業務負担が軽減されています。
令和6年度改定で更に進んだ効率化
令和6年度改定では、施設基準の届出について更なる簡素化が実施されました。保守管理計画書や研修修了証の写し等の添付が不要となり、届出事務の負担が大幅に軽減されました。複数の届出様式の提出を求めていた施設基準についても、様式の統廃合が行われ、1つの施設基準につき複数の届出様式が必要だったものが統一されました。
レセプト業務については、画像診断の撮影部位や算定日等について選択式記載が拡大されました。必要以上の記載項目と考えられるものについて見直しが行われ、レセプトに記載されている情報から確認できるものは記載不要となりました。検査等の診療行為については、あらかじめ検査値の記載を求めることで、審査支払機関からのレセプト返戻を減少させる仕組みも導入されています。
施設基準の届出について、現在主に紙で届け出ることとされているものの電子的な届出を可能にする取組も開始されました。これにより、医療機関・薬局の届出業務の効率化が大きく前進することが期待されています。
令和7年度に向けた署名・押印要件の見直し検討
規制改革推進会議の令和6年5月の答申では、医療機関等又は医師等の負担軽減の観点から、診療報酬上の書面における署名・押印要件について「令和6年検討開始、令和7年度結論・措置」というスケジュールで見直しが求められています。入院診療計画書、リハビリテーション実施計画書、診療情報提供書など、多くの書類で現在求められている署名・押印について、不要とすることの可否が検討されています。
電磁的方法による作成や情報提供を行う場合の電子署名についても、不要とすることの可否が検討対象となっています。「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」遵守を前提に、電磁的方法による作成や情報提供が可能であることの明確化も進められる予定です。患者の同意についても、電磁的記録によるものでも良いことが更に明確化され、ペーパーレス化の促進が期待されています。
これらの検討により、令和7年度には署名・押印要件の大幅な見直しが実現する見込みです。医療機関においては、電子カルテシステムと連動した計画書作成システムの導入準備を進めることで、手書きによる転記作業が不要となり、書類作成に要する時間を大幅に削減できるようになるでしょう。
リハビリテーション関連書類の課題と改善の方向性
現状、リハビリテーション関連の計画書は複数の様式が存在し、重複する項目が多い状況です。リハビリテーション実施計画書(別紙様式21、21の6、23)、リハビリテーション総合実施計画書(別紙19、20)など、それぞれに署名欄が設けられており、説明者や患者・家族等の署名が必要となっています。これらの様式の統合・簡素化が今後の検討課題となっています。
現行制度でも、やむを得ない理由がある場合には、説明内容及び継続について同意を得た旨を診療録に記載することで、署名を省略できる運用が認められています。しかし、この運用の更なる拡大と明確化が求められており、令和7年度に向けた検討の中で整理される予定です。
医療機関からは、これらの計画書作成が大きな負担となっているとの声が上がっており、様式の統合と項目の整理により、作成負担の軽減が図られることが期待されています。
DPCデータ入力負荷の現状と改善の必要性
DPCデータの様式1において入力を求めているデータには、入力負荷が特に大きい項目が存在します。障害福祉サービス等事業所との面談回数、作業療法士による個別作業療法の実施回数など、入院全期間の評価が必要な項目は、医療機関にとって大きな負担となっています。検査値等の経時的データについても、継続的な入力が必要であり、負荷が高い状況です。
外来・在宅・リハビリデータにおいても同様の課題があります。LDLコレステロール値やHbA1c値などの検査値データ、ブリストルスケールなどの評価項目について、入力頻度や項目数の多さが指摘されています。診療報酬改定のために必要な情報収集と、医療の質評価のための情報収集を区別し、真に必要な項目に絞り込むことが求められています。
今後は、一般的な診療において収集される情報と、診療報酬改定のために特別に収集が必要な情報を明確に区別し、入力項目の精査と削減を進めることが検討されています。医療機関が戦略的にデータ管理を行える環境の整備も重要な課題となっています。
まとめ
令和2年度から6年度にかけての累次の診療報酬改定により、医療現場の事務負担軽減は着実に前進してきました。会議のICT活用、研修の統合、記録・届出事務の簡素化、レセプト業務の効率化など、既に多くの改善が実現しています。令和7年度に向けては、署名・押印要件の原則廃止、リハビリテーション関連書類の統合、DPCデータ入力項目の更なる精査など、より抜本的な改革が検討されています。医療機関においては、これまでの改定で実現した簡素化策を確実に活用しつつ、今後の改革に向けた準備を進めることが重要です。特に電子化への対応と業務プロセスの見直しを計画的に進めることで、医療従事者が本来の診療業務により専念できる環境を構築し、患者サービスの質向上につなげることができるでしょう。