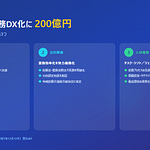令和7年9月11日、中央社会保険医療協議会の入院・外来医療等の調査・評価分科会は、令和8年度診療報酬改定に向けた重要な議論を行いました。本分科会では、診療情報活用の高度化やDPC制度の見直し、地域包括ケア病棟の機能評価など、今後の入院医療の方向性を決定づける7つの重要テーマが検討されました。医療機関は、これらの議論内容を理解し、早期に対応準備を進める必要があります。
今回の検討では、急性期医療の評価指標の再構築、高齢者医療への対応強化、重症度評価の適正化、医療従事者の働き方改革、多職種協働の推進など、医療提供体制の根幹に関わる内容が議論されました。特に注目すべきは、人口減少地域における医療機能の維持、内科系疾患の適切な評価、B項目測定の効率化など、現場の課題に即した具体的な改善策が示された点です。医療機関経営者は、これらの変化を的確に捉え、自院の機能と役割を再定義し、地域医療における位置づけを明確化する戦略的対応が求められます。
急性期医療の新たな評価軸:地域シェア率と人口規模への配慮
診療情報・指標等作業グループは、急性期医療の評価指標として、従来の救急搬送受入件数や全身麻酔手術件数に加え、地域シェア率という新たな視点を提示しました。地域シェア率とは、当該医療機関の年間救急搬送受入件数を所属二次医療圏内の全医療機関の合計で除した割合です。この指標により、20万人未満の二次医療圏において、救急搬送件数は少なくとも地域医療の中核を担う病院の存在が明らかになりました。
総合入院体制加算と急性期充実体制加算の要件統一についても議論が進展しました。両加算の心臓血管外科手術の対象Kコードと実績件数が異なる現状に対し、統一化の必要性が指摘されています。特に、人口が少ない地域での要件緩和が検討され、地域の実情に応じた柔軟な基準設定が求められています。こども病院や離島医療機関など、特殊な医療機関についても、その機能に応じた個別評価の必要性が認識されました。
DPC制度の精緻化:在院日数分布と点数設定方式の見直し
DPC/PDPS等作業グループは、現行制度の課題として、点数設定方式と実際の在院日数分布の乖離を指摘しました。多くの診断群分類において、平均在院日数が中央値を上回る正の歪度を有する分布となっており、現行の平均在院日数を基準とした第Ⅱ日設定の妥当性に疑問が投げかけられています。在院日数の中心傾向の指標として、平均値よりも中央値の採用が適切である可能性が示唆されました。
再転棟ルールについても、7日以内の再入院を一連の入院とみなす現行制度の運用実態が検証されました。持参薬使用による診療報酬上の二重負担問題も指摘され、適切なコスト評価の必要性が確認されています。地域医療係数における医師派遣機能の評価では、特定機能病院の基礎的基準との整合性を図る方向で検討が進められています。
包括期医療の機能分化:地域包括医療病棟と地域包括ケア病棟の役割明確化
地域包括医療病棟は、70歳以上の高齢者が多く、要介護度の高い患者、認知症を有する患者の割合が急性期一般入院料4〜6と比較して高い実態が明らかになりました。入院患者の上位疾患は、その他の感染症(真菌を除く。)、肺炎等、誤嚥性肺炎、体液量減少症、股関節・大腿近位の骨折、腎臓又は尿路の感染症、胸椎・腰椎以下骨折損傷などで、内科系疾患が中心です。内科系疾患では包括内の出来高点数が相対的に高く、請求点数には反映されにくい構造的課題が存在しています。
救急搬送受入件数以外の機能評価指標として、下り搬送等受入件数、直接入院、緊急入院、在宅患者緊急入院診療加算、協力対象施設入所者入院加算、介護保険施設等連携往診加算の算定回数などが検討されました。これらの指標は施設によってばらつきがあり、一定程度の幅で分布していることから、複数の指標を組み合わせた総合的な評価の必要性が示唆されています。予定・緊急入院別、手術の有無別による医療資源投入量の差異も確認され、患者群別の評価体系構築の可能性が示されました。
重症度、医療・看護必要度の適正化:B項目測定の効率化とA・C項目の見直し
B項目の測定については、入院初日にB得点が3点以上である割合が、特定機能病院や急性期一般入院料1で低く、急性期一般入院料2〜6や地域包括医療病棟で高いという二極化が確認されました。B項目は要介護度と相関し、入院や手術から4〜7日後には点数の変化が少なくなる傾向が明らかになりました。この結果を踏まえ、術後7日目以降や内科系症例での入院4日目以降における測定間隔の緩和が提案されています。
内科系症例におけるA・C項目の課題も浮き彫りになりました。内科系症例では外科系疾患と比較してA・C項目が一定点数以上となる割合が低く、重症度、医療・看護必要度がつきにくい実態があります。特に感染症患者では、抗菌薬がA項目で評価されないため、救急搬送や緊急入院の割合が高いにもかかわらず適切な評価がされていません。内科学会からの提案を踏まえ、免疫抑制剤の増点や緊急入院の評価強化などが検討されています。
働き方・タスクシフト/シェア:医療従事者の負担軽減に向けた方向性
働き方改革とタスクシフト/シェアについては、本分科会の議題として取り上げられ、医療従事者の負担軽減に向けた検討が行われました。医師の時間外労働規制の本格施行を控え、各医療機関では業務の効率化と役割分担の最適化が急務となっています。特定行為研修を修了した看護師の活用、薬剤師の病棟業務の拡充、リハビリテーション専門職の活動範囲の拡大など、様々な職種へのタスクシフト/シェアの推進が、今後の医療提供体制の持続可能性を確保する上で重要な課題として認識されています。
分科会では、タスクシフト/シェアを単なる業務移管ではなく、各職種の専門性を最大限に活かした協働体制の構築として捉える必要性が示唆されました。これにより、医師の負担軽減だけでなく、医療の質の向上と患者満足度の向上を同時に実現することが期待されています。各医療機関においては、自院の状況に応じた具体的な実施計画の策定と、段階的な導入が求められています。
病棟における多職種でのケア:ADL評価指標の統一化に向けた議論
病棟における多職種でのケアについては、患者の状態を的確に把握し、適切なケアを提供するための共通評価指標の必要性が議論されました。現在、ADL評価にはB項目、Barthel Index、日常生活機能評価、FIMなど複数の指標が混在しており、職種によって評価結果が異なることもあるため、多職種協働における共通認識の評価として、患者ケアや退院支援に役立つADL指標を整備すべきとの意見が出されました。
B項目については、「重症度、医療・看護必要度を把握し、適正な職員の配置数の実現を目指し、看護の必要性及び看護の量(療養上の世話)を測る指標」として施設基準通知に明記されており、人員配置、入退院支援、転倒・転落判断等の病棟マネジメント指標としての活用事例が紹介されました。今後、統一的な評価指標の導入により、看護師、リハビリテーション職、介護職等が共通認識を持って患者ケアにあたることが可能となることが期待されています。
大学病院における逆紹介割合の実態調査:地域医療連携の現状把握
全国医学部長病院長会議による調査では、82大学病院本院を対象に令和7年6月診療実績における逆紹介割合の実態調査が実施されました。78病院から回答を得て(回収率95.1%)、大学病院における逆紹介の現状が把握されました。逆紹介率の向上は、大学病院が高度医療機関としての機能を適切に発揮し、地域医療機関との役割分担を推進する上で重要な指標となっています。
今回の調査結果を踏まえ、各大学病院では地域医療機関との連携強化に向けた取り組みの必要性が確認されました。逆紹介を促進するための体制整備として、地域連携室の機能強化、連携医療機関との定期的な情報交換、逆紹介後のフォローアップ体制の構築などが今後さらに重要となることが示唆されています。地域医療支援病院としての機能評価においても、逆紹介率は重要な評価指標として位置づけられる見込みです。
まとめ:令和8年度改定への戦略的対応と準備の必要性
令和8年度診療報酬改定に向けた今回の議論は、入院医療提供体制の大きな転換点を示しています。急性期医療の地域シェア率導入、DPC制度の精緻化、包括期医療の機能明確化、重症度評価の適正化、働き方改革とタスクシフト/シェアの推進、病棟における多職種協働のためのADL評価指標の統一化、逆紹介による地域連携の強化という7つの重要論点は、いずれも医療機関経営に直結する内容です。医療機関は、これらの変化を的確に捉え、自院の強みを活かした機能選択と、地域における役割の明確化を進める必要があります。特に、人口減少地域における医療機能の維持、高齢者医療への対応強化、医療従事者の確保と育成、多職種協働による質の高い医療提供は、持続可能な医療提供体制構築の鍵となるでしょう。