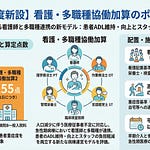入院・外来医療等の調査・評価分科会は、短期滞在手術等の外来移行が十分に進んでいない現状を指摘しました。令和4年度診療報酬改定で診療所での算定は著しく増加したものの、病院での外来実施率は依然として低調です。入院実施の方が外来実施より診療報酬が高く設定されており、医療費増加の要因となっています。分科会は、外来移行を進めるべきという意見で一致した一方、施設要因への配慮も必要だとしています。
短期滞在手術等の算定方法は医療機関の類型ごとに複雑に分かれており、制度の簡素化が課題です。白内障手術の外来実施率は全国平均54%ですが、OECD諸国では90%以上が外来で実施されており、国際的に見て日本の外来移行は大きく遅れています。水晶体再建術を入院で実施すると外来実施の約1.3倍から2倍の診療報酬となるため、医療費適正化の観点からも外来移行の推進が求められます。令和8年度診療報酬改定では、算定方法の統一化と施設基準の見直しが検討課題となっています。
短期滞在手術等の複雑な算定方法と制度の現状
短期滞在手術等の算定方法は、入院・外来の別と医療機関の類型により複数に分かれています。短期滞在手術等基本料1は日帰り手術を対象とし、届出が必要です。短期滞在手術等基本料3は4泊5日までの入院を対象とし、届出は不要ですが、DPC対象病院と診療所では算定できません。外来実施の場合、短期滞在手術等基本料1の届出の有無により、包括される検査等の範囲が異なります。
令和4年度診療報酬改定では、短期滞在手術等基本料1の評価引き上げと麻酔科医の配置要件の見直しを行いました。この改定により、診療所での算定回数が著しく増加しました。病院での算定は令和6年に1万5,447回だったのに対し、診療所では12万3,814回と約8倍の差がありました。対象手術のうち水晶体再建術が算定の大部分を占め、次いで内視鏡的大腸ポリープ切除術、経皮的シャント拡張術の順となっています。
算定方法が複雑であるため、医療機関にとって制度理解と適切な算定が困難な状況です。DPC対象病院では短期滞在手術等基本料3を算定できないため、4泊5日までの入院でもDPC算定または出来高算定となります。DPC対象病院以外の病院では原則として短期滞在手術等基本料3を算定する必要があるなど、医療機関の類型により算定ルールが大きく異なります。分科会では、算定方法を統一すべきという意見が出されました。
外来移行の進捗状況と医療機関間の大きな格差
短期滞在手術等基本料1の対象手術の外来実施率は、手術により大きく異なります。内視鏡的大腸ポリープ切除術は76.7%、水晶体再建術は62.5%、経皮的シャント拡張術は76.4%でした。水晶体再建術の外来実施率は平成28年以降上昇傾向にあり、約6割の手術が外来で実施されています。令和4年度改定での要件見直し後も、外来実施率の伸びに明らかな影響はみられませんでした。
病院における水晶体再建術の外来実施率は約2割にとどまり、低調に推移しています。医療機関別の分析では、水晶体再建術の外来実施率が0%の病院が一定数存在しました。内視鏡的大腸ポリープ切除術でも同様の傾向がみられ、医療機関間で外来実施率に大きなばらつきがありました。外来実施率100%の医療機関がある一方で、全く外来実施していない医療機関も存在するという二極化した状況です。
白内障手術の外来実施率は都道府県別でも大きな差があります。全国平均は54%ですが、最も高い県では約100%、最も低い県では約40%と、約2.5倍の開きがありました。OECD諸国では白内障手術の90%以上が外来で実施されており、日本の54%という水準は国際的に見て著しく低い状況です。第165回社会保障審議会医療保険部会でも、この国際比較における格差が指摘されました。
入院実施による診療報酬増加と医療経済への影響
短期滞在手術等を入院で実施する場合、外来で実施する場合と比較して診療報酬が総じて高くなります。水晶体再建術を病院で実施する場合、外来での短期滞在手術等基本料1なしでは1万4,186点、ありでは1万7,285点です。入院でDPC算定すると1万8,804点、短期滞在手術等基本料3では1万7,457点、地域包括ケア病棟での出来高算定では2万8,640点となります。外来実施と比較すると、入院実施では約1.3倍から2倍の診療報酬となっています。
内視鏡的大腸ポリープ切除術でも同様の傾向がみられます。外来での短期滞在手術等基本料1なしでは7,340点、ありでは9,970点です。入院でDPC算定すると1万4,210点、短期滞在手術等基本料3では1万2,580点、地域包括ケア病棟での出来高算定では1万6,755点となります。入院実施は外来実施の約1.3倍から2.3倍の診療報酬であり、医療費適正化の観点から外来移行の推進が求められています。
令和5年度特別調査では、入院実施の理由として病院の構造的理由と症例ごとの臨床的理由が挙げられました。構造的理由には、回復室の不足や24時間緊急対応体制の確保が困難といった施設要因があります。臨床的理由には、患者の併存疾患や術後管理の必要性が含まれます。DPC作業グループでは、DPC対象病院の中に短期滞在手術等の症例割合が高い医療機関が存在することが指摘され、また当分科会でも地域包括ケア病棟で短期滞在手術等基本料3の対象となる入院例が多いことが指摘されました。
短期滞在手術等基本料3は平成30年度以降も一定程度算定されています。対象となっている手術等は入院外での実施割合が増加しており、制度が継続的に活用されている状況です。対象手術等については平均在院日数が減少していました。多くの手術で令和4年度と比較して令和6年度に平均在院日数が短縮しており、例えば内視鏡的大腸ポリープ切除術2cm未満では2.397日から2.327日へ減少しました。在院日数の短縮は医療資源の効率的活用と医療費適正化に寄与しています。
令和8年度診療報酬改定に向けた今後の方向性
分科会では、水晶体再建術などの一部手術について外来移行を進めるべきという意見で一致しました。外来で実施可能な手術を入院で行うことは、医療資源の効率的活用の観点から見直しが必要です。OECD諸国と比較して外来実施率が著しく低い白内障手術については、特に外来移行の推進が求められます。患者の安全性を確保しつつ、在院期間の短縮によるCOVID-19などの院内感染リスクの低減も期待されます。
短期滞在手術等の算定方法については、統一化すべきという意見が出されました。算定する入院料等によって患者像が異なるとは考えがたいため、医療機関の類型にかかわらず同一の算定ルールを適用することが望ましいとされています。算定方法の簡素化により、医療機関の事務負担軽減と適切な算定の促進が期待されます。現在の複雑な算定ルールは、外来移行の阻害要因の一つとなっている可能性があります。
外来移行の阻害要因のうち、施設要因については一定の配慮が必要という意見も出されました。回復室の整備や24時間緊急対応体制の確保には、一定の投資と人員配置が必要です。中小規模の病院や診療所では、これらの施設基準を満たすことが困難な場合があります。令和8年度診療報酬改定では、外来移行の推進と施設要因への配慮のバランスを取った制度設計が求められています。
まとめ
短期滞在手術等の外来移行を推進するため、令和8年度診療報酬改定では算定方法の統一化と施設基準の見直しが検討課題となります。白内障手術の外来実施率54%をOECD諸国水準の90%以上に引き上げることで、医療費の適正化と医療資源の効率的活用が期待されます。外来移行の推進にあたっては、医療機関の施設要因への配慮も必要であり、段階的な制度改正が求められています。